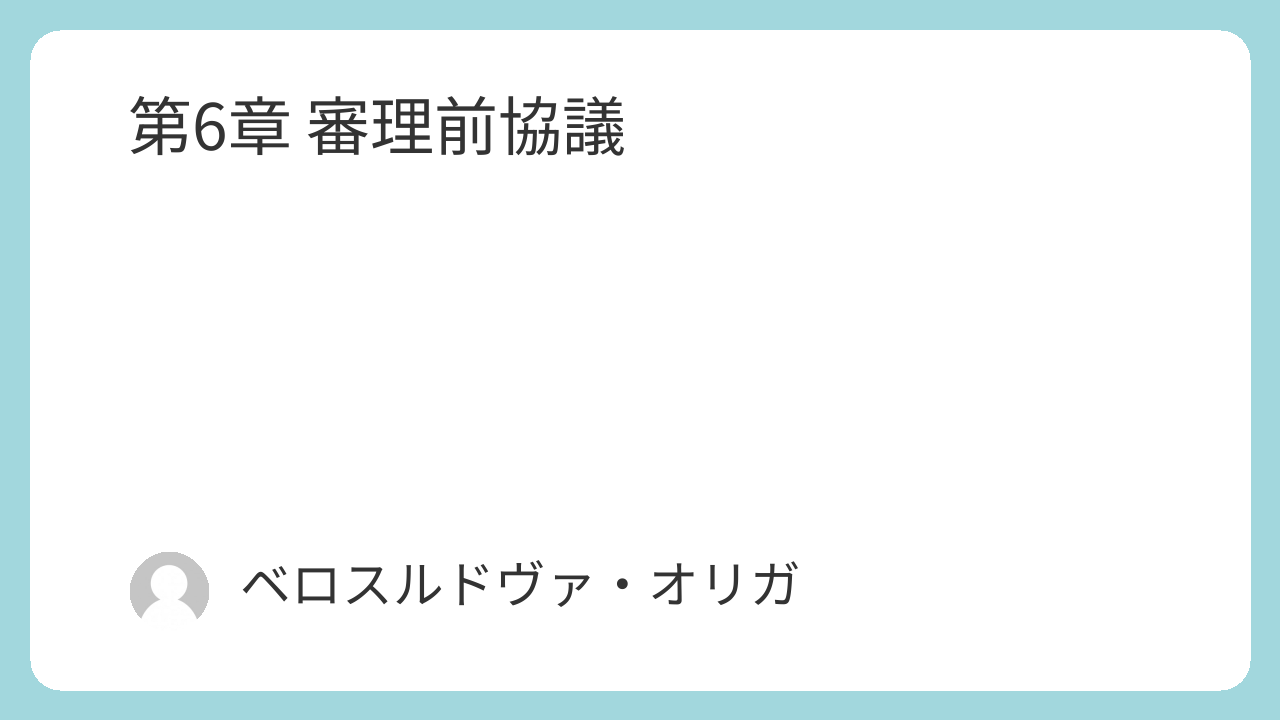6.1 審理前協議の目的:訴訟の管理と争点の最終整理
訴答(Pleading)とディスカバリー(Discovery)を経て、訴訟はいよいよトライアル(事実審理)に近づいてきます。しかし、その前に、「審理前協議(Pretrial Conference)」という手続があります。これは、裁判官と双方の代理人弁護士が一堂に会し、トライアルの進行を計画し、争点を最終的に整理し、和解の可能性も探るための公式な協議の場です(連邦民事訴訟規則16条)。
コモンローの時代には存在しなかったこの手続は、20世紀に入り、訴訟が複雑化する中で導入されました。特に、通知訴答による主張の簡素化、広範なディスカバリーによる情報の氾濫、そして当事者や請求の併合による訴訟関係の多角化といった現代的訴訟の特質は、トライアルを効率的かつ公正に進めるために、裁判官による積極的な訴訟管理(case management)を不可欠なものとしました。審理前協議は、まさにこの裁判官による訴訟管理の中核をなす手続なのです。
審理前協議の目的は多岐にわたりますが、主に以下の3つに集約されます。
第一に、トライアルの効率化です。協議を通じて、当事者双方は、トライアルで提出する予定の証拠リストや証人リストを交換し、文書の真正性や証拠能力について事前に合意(stipulation)を形成します。これにより、トライアルの場で、本来争う必要のない点に時間を費やすことを避け、真に争いのある核心的な問題に審理を集中させることができます。また、トライアル全体のスケジュールや、証人尋問の順序などもこの場で計画され、円滑な議事進行が図られます。
第二に、争点の最終的な明確化です。訴答やディスカバリーを経てもなお、当事者の主張には曖昧な部分が残っていることがあります。審理前協議は、これらの曖昧さを解消し、トライアルで実際に審理される法律上及び事実上の争点を、最終的に特定・限定する機会となります。この協議の結果は、後述する「審理前命令」という公式な書面にまとめられ、それは訴答書面(訴状や答弁書)にさえ優先する、トライアルの進行を規律する役割を果たすことになります。
第三に、和解(settlement)の促進です。ディスカバリーによって互いの手の内がほぼ明らかになり、トライアルを目前に控えたこの段階は、当事者が訴訟のリスクとコストを最も現実的に評価できるタイミングです。裁判官は、中立的な立場から、各当事者の主張の強みと弱みを指摘し、トライアルになった場合の予測される結果を示すことで、当事者間の和解交渉を積極的に後押しします。実際に、多くの事件がこの審理前協議をきっかけとして和解に至り、トライアルを回避しています。近年では、裁判官が調停(mediation)や早期中立的評価(early neutral evaluation)といった裁判外紛失解決手続(ADR)への参加を促すことも、審理前協議の重要な機能の1つとなっています。
ただし、この和解促進機能については、「裁判官による過度な圧力(judicial coercion)が、当事者がトライアルを受ける憲法上の権利を不当に侵害するのではないか」という批判も存在します。裁判官の役割はあくまで和解の「促進」であり、当事者に和解を「強制」することではないということは、常に意識されなければなりません。
6.2 手続と審理前命令
(1)審理前協議の手続
審理前協議の具体的な運用は、裁判所の裁量に大きく委ねられています。多くの裁判所では、事件の複雑さに応じて、訴訟の初期段階でディスカバリーのスケジュール等を定めるための協議(scheduling conference)と、ディスカバリー終了後にトライアルの準備を最終決定するための協議(final pretrial conference)など、複数回の協議が開催されます。
裁判所が審理前協議の開催を命じた場合、代理人弁護士の出席は強制的です。多くの場合、弁護士は事前に、争点、証拠、証人、適用される法規などに関する詳細な「審理前メモランダム(pretrial memorandum)」を裁判所に提出することが求められます。この準備を怠ったり、協議に欠席したりした当事者には、訴えの却下やデフォルト判決といった厳しい制裁が科される可能性があります。
協議に出席する弁護士は、事件について熟知していることはもちろん、事実の認諾や和解について、その場で実質的な判断を下せるだけの権限を有していることが期待されます。そのため、多くの裁判所では、実際にトライアルを担当する弁護士本人の出席を義務付けています。
協議の席で、裁判官は当事者双方の主張を聴取し、争点を整理し、証拠に関する予備的な判断を下し、トライアルの進行について指示を与えます。重要なのは、審理前協議は新たなディスカバリーを行う場ではないということです。また、裁判官が、当事者の合意なく、争いのある事実について認定を下すことも許されません。あくまで、トライアルを円滑に進めるための準備と調整の場なのです。
(2)審理前命令(Pretrial Order)の決定的な重要性
審理前協議の成果は、「審理前命令(Pretrial Order)」 という1つの公式な裁判所命令に集約されます。この命令には、協議で合意された全ての事項(争いのない事実、認諾された証拠など)、トライアルで審理される争点のリスト、証人リスト、証拠リスト、そしてトライアルの進行に関するあらゆる指示が記載されます。
審理前命令が持つ決定的な重要性は、それが訴答書面に取って代わり、その後の訴訟の進行を完全に支配するという点にあります。つまり、たとえ訴状で主張されていた請求であっても、審理前命令の争点リストから漏れていれば、もはやトライアルで主張することはできません。逆に、訴答書面にはなかった主張でも、審理前命令に含まれていれば、それは正式な争点となります。審理前命令は、いわばその訴訟における「最終的な設計図」であり、トライアルは、この設計図に寸分違わず従って遂行されなければなりません。
この厳格な拘束力ゆえに、一度確定した審理前命令を修正することは極めて困難です。連邦民事訴訟規則16条(e)項は、「明白な不正義(manifest injustice) を防ぐために必要な場合」にのみ、修正が許されると定めています。これは、単に弁護士が何かを見過ごしていた、という程度の理由では到底認められない、非常に高いハードルです。この厳格さこそが、審理前協議を意味のあるものにし、トライアルにおける不意打ちを防ぎ、審理を計画通りに進めることを保障するのです。
したがって、弁護士にとって、審理前協議に万全の準備で臨み、自らの主張が審理前命令に正確に反映されるよう全力を尽くすことは、トライアルそのものの準備と同じか、それ以上に重要な責務であると言えるでしょう。この段階での一瞬の油断が、後のトライアルで取り返しのつかない不利益につながる可能性があるからです。