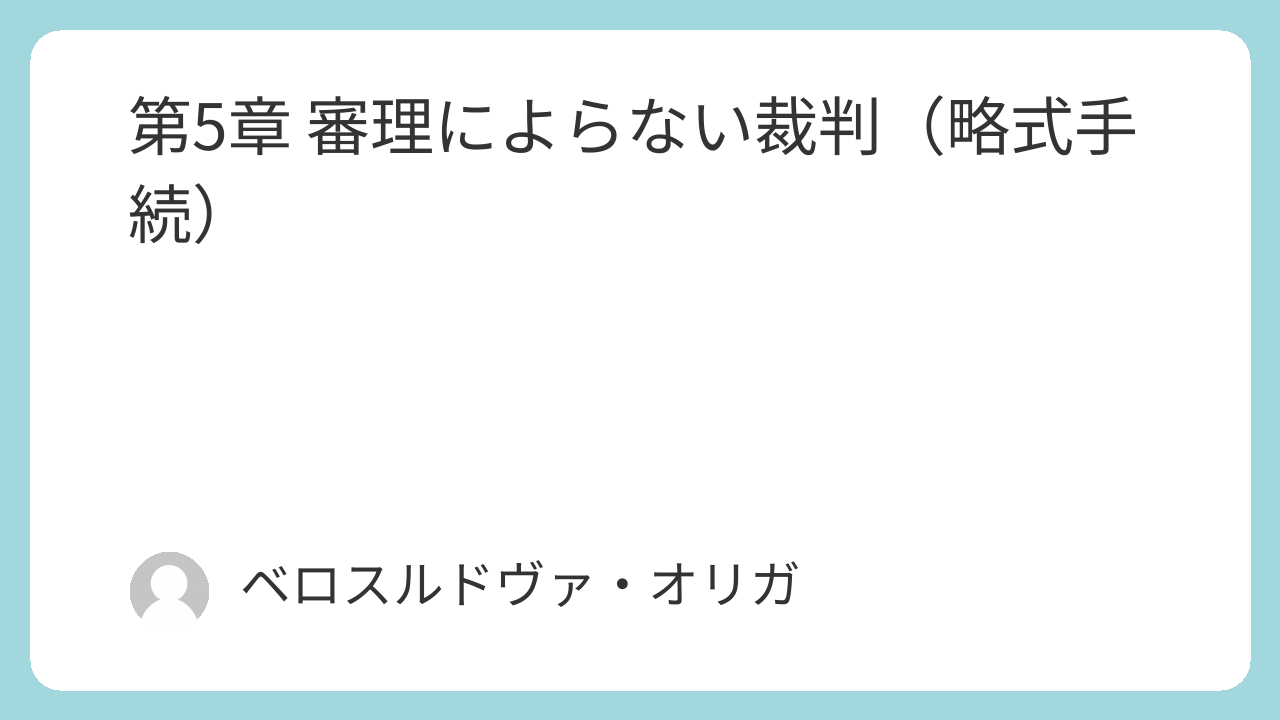5.1 なぜ審理(トライアル)を回避するのか
アメリカの連邦裁判所に提起された民事事件のうち、トライアル(事実審理)まで進むのは全体のわずか数パーセントに過ぎません。訴訟の圧倒的多数は、トライアルという最終段階に至る前に、何らかの形で終結しています。
その最大の理由は、トライアルに伴う莫大なコストと時間、そして結果の不確実性にあります。陪審審理ともなれば、その準備と遂行には膨大な費用と労力がかかります。そのため、当事者双方にとって、トライアルに至る前の段階で紛争を解決することには強いインセンティブが働きます。和解(settlement)がその最も一般的な形態ですが、それ以外にも、裁判所が法的な判断を下すことによって、トライアルを経ずに事件を終結させるための強力な手続が、民事訴訟規則には用意されています。
これらの手続は、単に訴訟を早期に終結させて司法資源を節約するという消極的な目的のためだけにあるのではありません。むしろ、訴答(Pleading)やディスカバリー(Discovery)を通じて明らかになった事実と法律上の主張を吟味し、そもそもトライアルで審理すべき「重要な事実についての争点」が存在するのかどうかを判断するという、積極的な機能を持っています。もし、トライアルを開くまでもなく、一方当事者の勝訴が法的に明らかであるならば、無用な審理を続けることは当事者と司法の双方にとって不利益でしかありません。
本章では、このような「審理によらない裁判」、すなわち略式的な紛争解決手続の主要な三つの形態——サマリー・ジャッジメント、デフォルト判決、そして訴えの取下げ——について解説します。中でも、サマリー・ジャッジメントは、現代アメリカ訴訟において最も強力かつ頻繁に利用される手続であり、その理解は訴訟戦略を立てる上で不可欠です。
5.2 サマリー・ジャッジメント(Summary Judgment)
(1)目的と基準:重要な事実についての争点の不存在
サマリー・ジャッジメント(Summary Judgment)は、訴答の段階を終え、ディスカバリーによって一定の証拠が出そろった段階で、一方または双方の当事者が、「本件にはもはやトライアルで審理すべき重要な事実についての争点(genuine dispute as to any material fact)は存在せず、申立人が法律問題として(as a matter of law)判決を受ける権利を有する」ことを裁判所に示し、トライアルを経ずに勝訴判決を求める手続です(連邦民事訴訟規則56条)。
この手続の本質は、訴答という「書面上の主張」の背後に隠された「事実の真偽」を問うことにあります。訴答の段階では、当事者は自らに有利な主張を展開するため、一見すると事実関係に大きな争いがあるように見えます。しかし、ディスカバリーを通じて、宣誓供述書(affidavit)、デポジション(証言録取)、インタロガトリー(質問書)への回答といった具体的な証拠が収集されると、実は争われているように見えた事実問題が、実際には一方の当事者によって全く裏付けられていない、見せかけの争点(feigned issue)に過ぎないことが判明する場合があります。
サマリー・ジャッジメントは、このような見せかけの争点を審理の対象から排除し、法的な判断のみで決着がつく事件を、トライアルというコストのかかるプロセスから解放するための役割を果たします。裁判所は、この申立てを審査するにあたり、証拠の信用性を評価したり、事実認定を行ったりすることはしません。裁判所の唯一の役割は、提出された証拠を、申立てをされた側(被申立人)にとって最も有利に解釈した上で、それでもなお、合理的な陪審員(あるいは裁判官)が被申立人に有利な判断を下す余地のある「重要な事実についての争点」が存在するか否かを判断することです。
「重要な事実(material fact)」とは、その存否が、適用される実体法の下で、請求または抗弁の成否を左右するような事実を指します。たとえ事実関係に争いがあったとしても、その争点が訴訟の結果に何ら影響を与えないものであれば、それは「重要」な事実ではなく、サマリー・ジャッジメントを妨げる理由にはなりません。
(2)手続と立証責任
サマリー・ジャッジメントの申立ては、通常、ディスカバリーが相当程度進み、事件の全体像が明らかになった時点で行われます。申立人は、申立書とともに、自らの主張を裏付ける証拠(宣誓供述書、デポジションの記録、各種文書など)を提出し、「重要な事実についての争点が存在しない」ことを具体的に示さなければなりません。
ここでの立証責任の分配は、トライアルにおける立証責任(burden of persuasion)の所在と密接に関連しています。
- 申立人が、トライアルで立証責任を負わない争点について申し立てる場合(典型例:被告による申立て): 被告は、原告がその請求の必須要素について、それを裏付ける証拠を何一つ持っていないことを証明するか、又は、ディスカバリー記録などを引用して指摘すれば足ります。この場合、立証責任は原告側に転換され、原告は、自らの請求を裏付ける具体的な証拠を提出して、「重要な事実についての争点」が存在することを示さなければなりません。原告が、単に訴状の記載を繰り返したり、根拠のない主張をしたりするだけでは、この責任を果たしたことにはならず、サマリー・ジャッジメントが認められることになります。
- 申立人が、トライアルで立証責任を負う争点について申し立てる場合(典型例:原告による申立て): 原告は、自らが主張する請求の全ての必須要素について、合理的な陪審員が疑いを差し挟む余地のない、圧倒的な証拠を提出しなければなりません。これは非常に高いハードルであり、被告側は、原告の証拠の信用性に疑問を投げかけたり、相反する証拠を少しでも提出したりすれば、サマリー・ジャッジメントを免れることができる場合が多いです。
裁判所は、提出された証拠を評価する際、被申立人にとって最も有利な形で事実を解釈し、全ての合理的な推認(reasonable inferences)を被申立人の利益になるように働かせなければなりません。証人の信用性が問題となる場合や、当事者の意図や動機といった主観的な要素が争点となる場合には、それらは典型的に陪審が判断すべき問題であるとされ、サマリー・ジャッジメントは認められにくい傾向にあります。
Celotex Corp. v. Catrett(1986年)をはじめとする一連の最高裁判決は、サマリー・ジャッジメントの活用を奨励する傾向を強めています。これにより、連邦裁判所では、根拠の薄い訴訟をトライアル前に終結させるための、より積極的な手段として、サマリー・ジャッジメントが機能するようになっています。
5.3 デフォルト判決(Default Judgment)
被告が、訴状の送達を受けたにもかかわらず、定められた期間内に答弁書を提出せず、その他一切の防御活動を行わない場合、原告は、被告の不作為(default)を理由として、勝訴判決を求めることができます。これがデフォルト判決(Default Judgment)です(連邦民事訴訟規則55条)。
この手続は、2つの段階に分かれています。
第一段階は、「デフォルトの記録(Entry of Default)」です。原告が、被告が応答期間内に応答しなかった事実を宣誓供述書等で示すと、裁判所書記官(clerk)は、事件記録に被告が「デフォルト」状態にあることを公式に記録します。これは判決そのものではありませんが、これによって被告は、事件の責任(liability)に関する一切の抗弁権を失います。
第二段階が、「デフォルト判決の言渡し(Entry of Default Judgment)」 です。
- 原告の請求額が、契約書などで明らかな確定金額(sum certain)である場合、原告の請求に基づき、書記官が判決を言い渡すことができます。
- 請求額が不確定である場合(例えば、人身傷害による慰謝料請求など)、原告は裁判官に対して判決を申し立てます。裁判官は、損害額を算定するために審問(hearing)を開くことができます。被告は、責任そのものを争うことはできませんが、この損害額算定のための審問に参加し、損害額の多寡について争うことを認められる場合があります。
デフォルト判決は、被告が訴訟を完全に無視した場合に下される、いわば欠席判決です。しかし、アメリカの司法制度は、紛争を実体的に解決することを強く志向するため、一度下されたデフォルト判決であっても、被告が、応答しなかったことに「正当な理由(good cause)」(例えば、送達の不備や、病気など)があり、かつ、有効な抗弁事由を有していることを示せば、裁判所は裁量でその判決を取り消し、被告に弁論の機会を与えることがあります。
5.4 訴えの取下げ(Dismissal)
訴訟は、原告自身の意思によって、あるいは裁判所の命令によって、終局判決に至る前に終了することもあります。これを「訴えの取下げ(Dismissal)」と呼びます。
(1)任意的取下げ(Voluntary Dismissal)
原告は、特定の条件下で、自らの意思で訴訟を取り下げることができます(連邦民事訴訟規則41条(a)項)。
- 被告が答弁書またはサマリー・ジャッジメントの申立書を提出する前であれば、原告は、裁判所の許可なく、一方的に訴えを取り下げることができます。この場合の取下げは、原則として不利益がなく、同一の請求について後日再び訴訟を提起することを妨げません。
- 被告が応答した後でも、当事者全員が合意した場合には、取下げが認められることがあります。この場合、裁判所は、取下げが被告に不当な不利益を与えないよう、特定の条件(例えば、原告に被告の訴訟費用の一部負担を命じるなど)を付すことができます。
ただし、この任意的取下げの権利には、濫用を防ぐための重要な制限があります。「2回取下げルール(two-dismissal rule)」 と呼ばれるもので、原告が、同一の請求について、一度任意的取下げを行った後、再び任意的取下げを行うと、その二度目の取下げは「本案についての最終判断(adjudication on the merits)」とみなされ、原告はもはや同一の請求について3度目の訴訟を提起することができなくなります。
(2)非任意的取下げ(Involuntary Dismissal)
裁判所は、被告の申立てにより、又は、自らの職権で、原告の意思に反して訴訟を棄却することができます。これを非任意的取下げといいます(連邦民事訴訟規則41条(b)項)。
非任意的取下げの主な理由としては、「訴追の懈怠(failure to prosecute)」(原告が長期間にわたり訴訟を進行させるための何らの活動も行わない場合)や、裁判所の命令または民事訴訟規則の不遵守が挙げられます。
事物管轄権や人的管轄権の欠如を理由とする取下げなどを除き、非任意的取下げは、原則として本案についての最終判断とみなされ、強力な既判力(claim preclusive effect)を持ちます。訴訟手続の円滑な進行を確保するための制裁としての性格を持っているのです。
これらの「審理によらない裁判」の手続は、訴訟の早期解決と司法資源の効率的配分に貢献する一方で、特にサマリー・ジャッジメントの運用においては、当事者がトライアルで正当な主張を行う機会を奪う危険性もはらんでいます。そのバランスをいかに取るかは、現代アメリカ司法が直面する課題となっています。