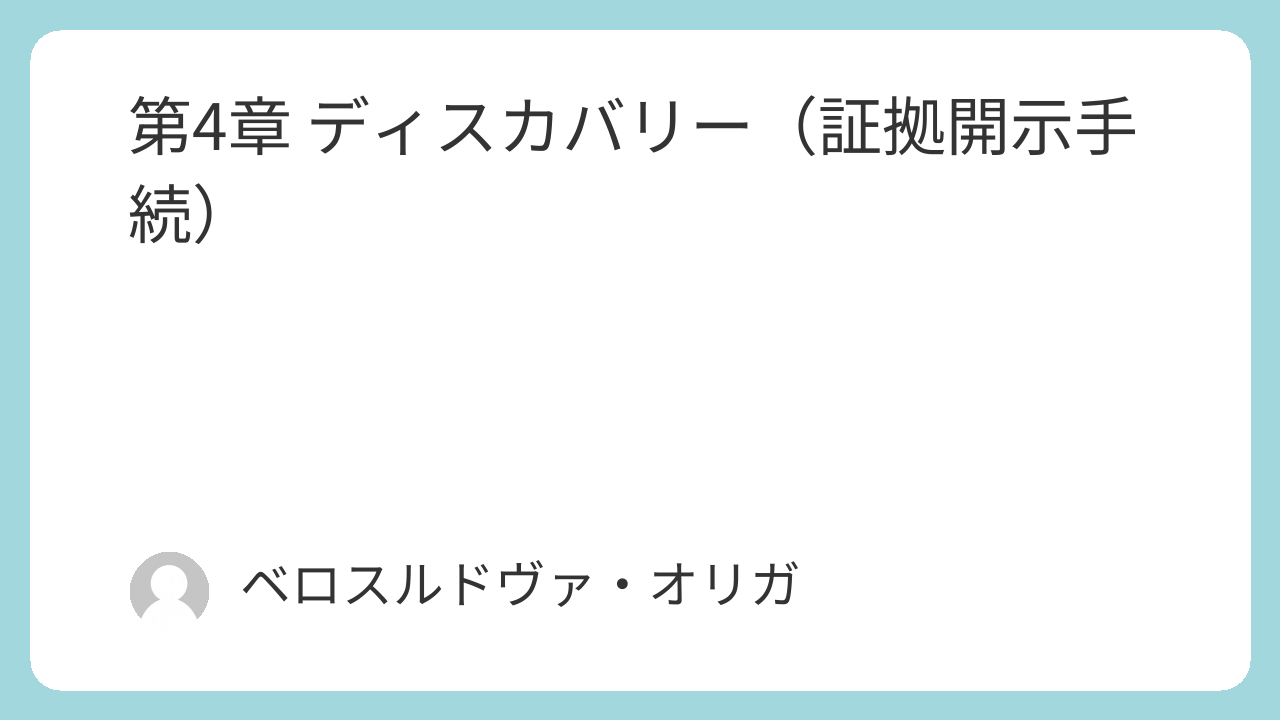4.1 ディスカバリーの目的と範囲:真実発見と不意打ち防止の徹底
アメリカの民事訴訟におけるディスカバリー制度は、単なる証拠収集の手段にとどまらない、より根源的な思想に基づいています。それは、対審構造(当事者主義)を実質的に機能させるため、審理(トライアル)の前に、当事者双方が持つ事件に関する情報を可能な限り互いに開示させ、争点を明確にし、事実関係を白日の下に晒すという思想です。これにより、「trial by ambush」、すなわち、相手方が隠し持っていた証拠によって審理で不意打ちを受ける事態を徹底的に排除し、訴訟を真実の探求の場とすることを目指しています。
コモンローの時代、当事者は訴答によって示された主張の概要しか知ることができず、相手方がどのような証拠を持っているかは、法廷の場でそれが提示されるまで知る由もありませんでした。これでは、真実の発見よりも、弁護士の弁論術や証拠の隠匿といった戦術が勝敗を左右しかねませんでした。1938年の連邦民事訴訟規則の制定とともに導入された近代的なディスカバリー制度は、このような状況を革命的に変えたのです。
ディスカバリーには、主に3つの目的があります。第一に、証拠の保全です。病気や高齢、あるいは国外にいるといった理由で、トライアルの時点で証言を得ることが難しい可能性のある重要な証人の証言を、あらかじめ記録・保存しておきます 。第二に、争点の明確化です。訴答の段階では争いがあるように見えた事実問題も、ディスカバリーを通じて情報交換を行うことで、実際には争いのない点であることが判明することが多いです。これにより、当事者と裁判所は、本当に争いのある重要な争点に審理を集中させることができます。第三に、最も重要な目的が、関連情報の包括的な収集です。当事者は、自らの主張を裏付ける証拠だけでなく、相手方の主張を弾劾するための情報や、事件の背景にある事実関係を、相手方当事者や第三者から広範に収集することができます。
この目的を達成するため、ディスカバリーの対象となる情報の範囲は、極めて広く設定されています。連邦民事訴訟規則26条(b)(1)項によれば、当事者は、「いずれかの当事者の請求または抗弁に関連し、かつ、事件のニーズに比例した(proportional)、秘匿特権のない(nonprivileged)あらゆる事項」についてディスカバリーを行うことができます 。
ここで重要なのは、2つの点です。第一に、開示対象となる情報は、トライアルで「証拠として許容される(admissible in evidence)必要はない」 、という原則です 。たとえ伝聞証拠(hearsay)であっても、あるいはそれ自体は法廷で証拠とならない情報であっても、それが「証拠として許容される情報の発見につながる」と合理的に考えられる限り、ディスカバリーの対象となります 。これにより、当事者は、事件の全体像を把握するために、非常に広範な情報を手に入れることが可能となります。
第二に、「比例性(proportionality)」 の原則です。これは、ディスカバリーの範囲を無制限に広げるのではなく、事件の重要性、争われている金額、当事者の情報へのアクセスしやすさ、当事者の資力、そしてそのディスカバリーが争点解決にどれほど重要か、といった要素を考慮し、ディスカバリーによって得られる利益が、それにかかる負担や費用を上回る場合にのみ、開示が認められるべきである、という考え方です。特に、デジタル情報・E-Discoveryの爆発的な増大に伴い、この比例性の原則は、濫用的なディスカバリーを防ぎ、訴訟コストの高騰を抑制するための重要な制約として、近年ますますその重要性を増しています。
4.2 ディスカバリーの主な手法
ディスカバリーは、主に以下に示す5つの手法を組み合わせて行われます。それぞれに特徴があり、弁護士は訴訟の性質や進行段階に応じて、これらのツールを戦略的に使い分けることになります。
(1)デポジション(Oral Deposition):証言録取
デポジションは、ディスカバリー手続の王様とも呼ばれる、最も強力な手法の一つです。これは、裁判所の外(通常は法律事務所)で、当事者、証人、その他の関係者を召喚し、裁判所の速記官(court reporter)が同席する中、宣誓の上で、相手方弁護士の口頭での質問に答えさせる手続です 。そのやり取りはすべて速記録として反訳され、公式な記録となります 。
デポジションの最大の利点は、相手方当事者や敵対的な証人に対して、準備された回答ではなく、その場で直接、しかも反対尋問のように誘導尋問(leading questions)を交えながら質問を浴びせることができる点にあります 。これにより、証言の矛盾点を突き、予期せぬ情報を引き出し、そして何よりも、その証人がトライアルの法廷でどのような証言をし、陪審にどのような印象を与えるかを、事前に詳細に評価することができます 。また、デポジションでの証言は、トライアルでの証言と矛盾した場合に、その証人の信用性を弾劾するための強力な武器となります。
一方で、デポジションは、弁護士の時間、書記官の費用、証人への日当など、ディスカバリーの中でも最も費用がかかる手法です 。そのため、連邦民事訴訟規則では、原則として一方当事者が行えるデポジションの回数を10回まで、1回の時間も7時間までと制限しています。
(2)インタロガトリー(Written Interrogatory):質問書
インタロガトリーは、一方当事者が、相手方当事者に対して、書面による質問を送り、相手方が宣誓の上で、書面で回答することを求める手続です(連邦民事訴訟規則33条)。デポジションとは異なり、質問の対象は相手方当事者に限定され、第三者に対して用いることはできません 。
インタロガトリーの主な利点は、比較的低コストで、事件に関する基本的な事実関係、請求や抗弁の根拠、関連文書や証人の存在といった情報を網羅的に収集できる点にあります。特に、法人などの組織に対して用いられる場合、その組織が合理的な調査を行えば知りうる全ての情報(個々の従業員の知識を含む)に基づいて回答する義務があるため、組織全体の情報を効率的に得ることができます。
しかし、欠点もあります。質問と回答がすべて書面で行われるため、デポジションのような即時性や追及力に欠けます。回答は、相手方弁護士が慎重に検討・推敲した上で作成されるため、不利な情報が巧みに回避されたり、曖昧な表現でごまかされたりすることが少なくありません。そのため、連邦民事訴訟規則では、送付できる質問の数を原則として25問までに制限しています。
(3)文書、電子情報、および有体物の提出要求(Request for Production of Documents, Electronically Stored Information, and Tangible Things)
これは、相手方当事者が所持、保管、または管理している文書、電子的に保存された情報(ESI)、その他の有体物(製品、機械など)の提出を求め、それを検査・複写・テストすることを可能にする手続です (連邦民事訴訟規則34条)。第三者が保有する文書等については、召喚状(subpoena)を用いて同様の要求を行うことができます。
現代の訴訟において、この手続の極めて重要です。契約書、社内メモ、会計記録といった伝統的な文書に加え、Eメール、電子ファイル、データベースといった電子情報(ESI)が、事件の真相を解明する上で決定的な証拠となることがほとんどだからです。特に、電子情報開示(E-Discovery)は、その膨大な量と技術的な複雑さから、現代ディスカバリーの中心となっています。当事者は、訴訟が予見された時点から、関連する可能性のある電子情報を保全する義務を負い、これを怠って情報を破棄・消去すると、spoliation として厳しい制裁を科される可能性があります 。
(4)自白要求(Request for Admission)
自白要求は、一方当事者が相手方当事者に対し、特定の事実の真実性や、文書の真正性について、認める(admit)か否認する(deny)かを書面で回答するよう求める手続です(連邦民事訴訟規則36条)。
この手続の目的は、証拠収集そのものというよりは、当事者間で争いのない事実を確定させ、トライアルの争点を絞り込むことにあります。相手方が事実を認めれば、その事実についてトライアルで証拠調べを行う必要がなくなり、審理の効率化に大きく貢献します。もし相手方が、合理的な理由なく事実を否認し、後にその事実が真実であったことが証明された場合、否認した当事者は、相手方がその事実を証明するために要した費用(弁護士費用を含む)を負担させられるという制裁が待っています。
(5)身体・精神鑑定(Physical and Mental Examination)
訴訟において、いずれかの当事者の身体的または精神的な状態が重要な争点となっている場合(例えば、人身傷害訴訟における原告の負傷の程度や被告の運転能力など)、相手方当事者は、裁判所の許可を得て、その当事者に対し、専門家による身体または精神の鑑定を受けるよう命じることを求めることができます(連邦民事訴訟規則35条)。
この手続は、個人のプライバシーへの重大な介入となるため、他のディスカバリー手法とは異なり、常に裁判所の事前の許可が必要です。申立てを行う当事者は、鑑定の対象となる心身の状態が「争点となっており(in controversy)」、かつ、鑑定を行うべき「正当な理由(good cause)」 があることを示さなければなりません。
4.3 開示の限界:秘匿特権とワーク・プロダクトの法理
ディスカバリーの範囲は極めて広範ですが、無制限ではありません。たとえ事件に深く関連する情報であっても、特定の重要な社会的価値を保護するために、開示が免除される領域が存在します。その最も重要な2つの盾が、「秘匿特権(Privilege)」と「ワーク・プロダクトの法理(Work-Product Doctrine)」です。
(1)秘匿特権(Privilege)
秘匿特権とは、特定の関係にある者同士の間の、信頼関係を維持するために不可欠な、内密なコミュニケーションを法的に保護し、法廷での証言やディスカバリーにおける開示を拒否する権利です 。これは、たとえその情報が事件の真相解明にどれほど重要であっても、開示を強制されないという、絶対的な保護を与えるものです。
民事訴訟において最も頻繁に問題となるのが、弁護士・依頼者間秘匿特権(Attorney-Client Privilege) です。これは、依頼者が法的助言を求める目的で、弁護士に対して内密に行ったコミュニケーションの内容を保護するものです。この特権の目的は、依頼者が、後に不利な形で開示されることを恐れることなく、弁護士に対して全ての事実を率直に話せるようにすることにあります。これにより、弁護士は正確な事実に基づいて適切な法的助言を与えることができ、ひいては法制度全体の適正な運用が担保されるのです。
このほかにも、医師・患者間、聖職者・信者間、夫婦間などのコミュニケーションを保護する秘匿特権が存在しますが、その範囲や適用の有無は州法によって異なります 。
(2)ワーク・プロダクトの法理(Work-Product Doctrine)
ワーク・プロダクトの法理は、秘匿特権と並ぶ、もう1つの重要な情報開示の制限です。これは、Hickman v. Taylor(1947年) という最高裁判決によって確立された判例法理であり、連邦民事訴訟規則26条(b)(3)項に成文化されています 。
この原則が保護するのは、「訴訟を見越して(in anticipation of litigation)」、当事者またはその代理人(主に弁護士)によって作成された文書その他の有体物です 。これには、弁護士が証人から聴取した内容をまとめたメモ、事件に関する調査報告書、訴訟戦略を記した内部文書などが含まれます 。
この原則の目的は、アメリカの対審構造を健全に機能させることにあります。弁護士は、相手方に自らの手の内をすべて明かさなければならないとなると、事件の不利な側面を調査したり、自らの思考過程を文書に残したりすることを躊躇するようになるでしょう。また、勤勉な弁護士が苦労して集めた情報を、怠惰な相手方弁護士がディスカバリーによって安易に入手できるとすれば、公正な競争が阻害されます。ワーク・プロダクトの法理は、各弁護士が、相手方の干渉を恐れることなく、自由に事件の調査・分析を行い、独自の戦略を練るための「聖域」を確保するのです。
秘匿特権とワーク・プロダクトの決定的な違いは、その保護のレベルにあります。秘匿特権が原則として絶対的な保護を与えるのに対し、ワーク・プロダクトによる保護は相対的(qualified)です 。すなわち、相手方当事者が、その情報を入手することに「実質的な必要性(substantial need)」 があり、かつ、「undue hardship(過度の困難)なしには他の手段で同等の情報を入手できないこと」を証明した場合には、裁判所はワーク・プロダクトで保護された資料の開示を命じることができます。
ただし、ワーク・プロダクトの中でも、弁護士の「精神的印象、結論、意見、または法理論(mental impressions, conclusions, opinions, or legal theories)」 を含む部分については、ほぼ絶対的に近い、非常に高度な保護が与えられます 。
4.4 専門家証人に関する情報の開示
現代の複雑な訴訟では、医学、会計、工学といった専門的知見が不可欠となることが多くあります。当事者は、自らの主張を裏付けるために専門家(Expert Witness)を雇います。このような専門家に関する情報のディスカバリーについては、特別なルールが設けられています (連邦民事訴訟規則26条(a)(2)項、(b)(4)項)。
トライアルで証言することが予定されている専門家については、相手方は広範なディスカバリーを行う権利を有します。証言予定の専門家は、自らが証言する全ての意見、その意見の根拠となった事実やデータ、意見形成に用いた証拠、資格、過去の証言歴などを詳述した専門家報告書(expert report) を作成し、相手方に開示しなければなりません 。さらに、相手方は、その専門家をデポジションにかけることもできます 。これは、専門家の意見がしばしば難解で、その信頼性を評価するためには、トライアルの前に十分な準備を行う必要があるからです。
一方、トライアルで証言する予定はなく、訴訟準備のために助言のみを行う専門家(consulting expert)については、原則として、その意見や事実認識はワーク・プロダクトとして保護され、ディスカバリーの対象とはなりません。これは、当事者が、不利な意見が開示されることを恐れずに、専門家から率直な評価を得られるようにするためです。
4.5 電子情報開示(E-Discovery)の課題
デジタル技術の進展は、ディスカバリーのあり方を根底から変えました。訴訟に関連する情報の大部分が、Eメール、ワード文書、スプレッドシート、データベース、SNSの投稿といった、電子的に保存された情報(ESI)として存在するようになったのです。この電子情報開示(E-Discovery)は、その天文学的な情報量、技術的なアクセスの困難さ、そして莫大なコストから、現代訴訟における最大の課題ともなっています 。
E-Discoveryに特有の問題として、まず情報保全(preservation)の義務が挙げられます 。当事者は、訴訟が合理的に予見された時点から、関連する可能性のあるESIを、通常の業務プロセスによる消去などから保護し、保全する義務を負います。
また、膨大なESIの中から関連情報を探し出すレビュー(review) のコストは、しばしば訴訟費用全体のかなりの部分を占めます 。キーワード検索や、近年ではAIを用いた技術支援型レビュー(Technology Assisted Review, TAR)などの手法が用いられますが、それでもなお、弁護士による膨大な時間のレビューが必要となることが多いです 。
さらに、どのような形式(form of production)でESIを提出するか(例えば、元のアプリケーションで開けるネイティブ・ファイルか、検索可能なPDFか)、そして、ファイルの作成日時や修正履歴といったメタデータを含めるべきか、といった技術的な問題も、当事者間の深刻な争点となります。
これらの課題に対応するため、連邦民事訴訟規則は、E-Discoveryに関する詳細な規定を設けています。当事者は、訴訟の極めて初期の段階で、E-Discoveryに関する計画について協議することが義務付けられており、裁判所は、前述の「比例性」の原則に基づき、開示の範囲やコスト負担について、積極的に管理・介入することが期待されています。
4.6 ディスカバリー違反に対する制裁
ディスカバリー制度が実効性を持つためには、当事者がそのルールを遵守することが不可欠です。相手方が正当な理由なくディスカバリーの要求に応じない場合、要求した側の当事者は、裁判所に対して、開示を命じるよう強制申立て(Motion to Compel)を行うことができます 。
そして、裁判所の命令にさえ従わない、あるいはその他の悪質なディスカバリー妨害行為(例えば、意図的な証拠隠滅)を行った当事者に対しては、裁判所は、その行為の悪質性に応じて、様々な制裁(Sanctions) を科す権限を有します(連邦民事訴訟規則37条)。制裁の内容は、相手方の弁護士費用の負担命令といった金銭的なものから、特定の主張を禁じたり、特定の証拠の提出を禁じたりといった、訴訟の帰趨に直接影響するもの、そして、最終手段として、原告の請求を棄却したり、被告にデフォルト判決を下したりといった、事件を終結させる最も厳しいものまで、多岐にわたります。
ディスカバリーは、アメリカの対審構造を支える屋台骨です。それは、時に濫用され、訴訟コストを高騰させる元凶として批判されることもありますが、同時に、当事者間の情報格差を是正し、真実発見に貢献する、他に代えがたい重要な機能も担っています。この広範かつ複雑なディスカバリーのプロセスを理解し、使いこなすことこそが、アメリカの民事訴訟で勝利するための鍵となります。