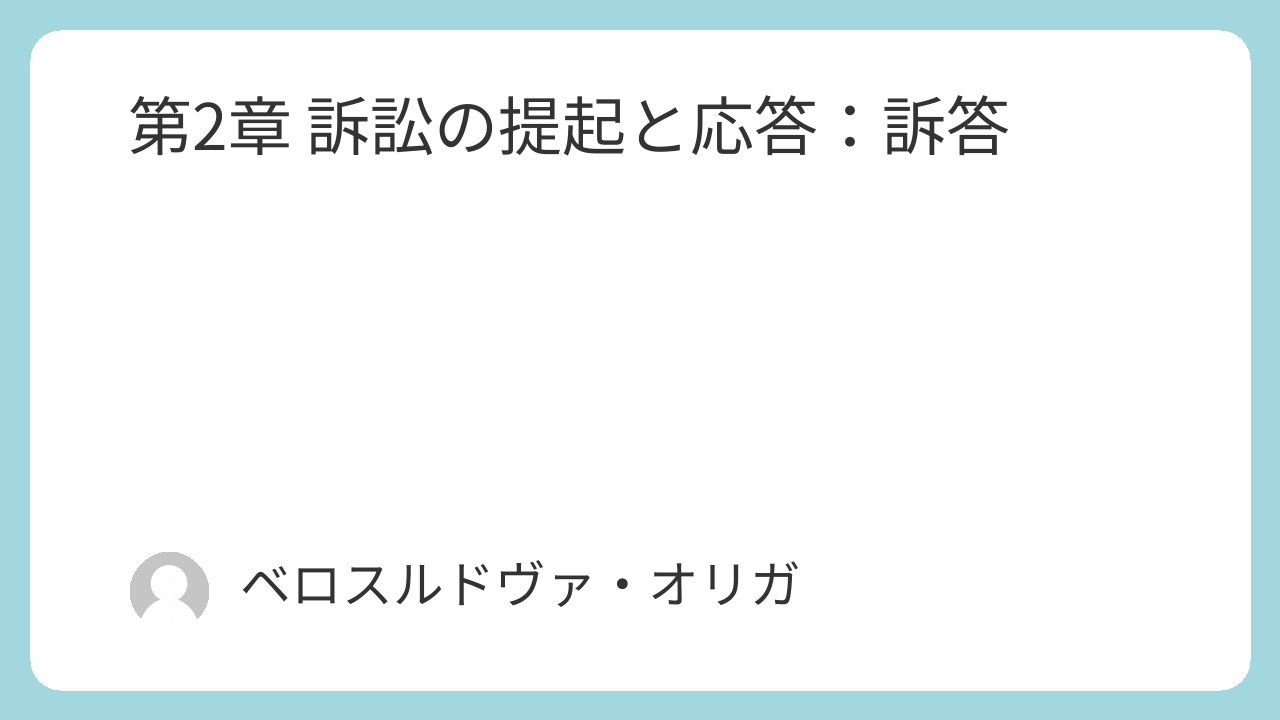2.1 訴答の目的と機能:主張の明確化
訴訟の当事者が、自らの主張や防御の方法を記載した書面を裁判所に提出し、相互に交換する一連の手続を「訴答(Pleading)」と呼びます。これは、法廷での口頭弁論に先立ち、争いの枠組みを定めるための作業です。コモンローの時代、訴答は「writ」という厳格な形式と一体であり、適切なwritを選択し、その定型に従って寸分違わぬ主張を記載することができなければ、たとえ実体的な権利があったとしても、門前払いされました。この過度に形式的な運用は、正義の実現を妨げるものとして厳しく批判されました。
19世紀半ばにニューヨーク州のフィールド法典から始まった近代的な訴答改革は、このような形式主義からの脱却を目指しました。その目的は、訴訟を、当事者の法的主張の真偽を判断する場へと転換させることにありました。現代の訴答手続は、主に2つの重要な機能を担っています。
第一に、法的に意味のない主張を審理の対象から排除することです。原告の訴状が、たとえその記載内容がすべて真実であったとしても、法的に救済を与えられないような主張しか含んでいない場合、被告は訴答の段階でこれを指摘し、訴えの却下を求めることができます。これにより、無益な事実審理に時間と費用を費やすことなく、紛争を早期に解決することが可能となります。この機能は、単に不合理な訴訟を排除するだけでなく、新たな法的権利の創造や、既存の法理論の発展を促す機能も有します。前例のない救済を求める訴えが訴答段階で退けられれば、その判断が上訴の対象となり、上級審が新たな法的判断を下す機会が生まれるからです。
第二に、当事者と裁判所に対して、事件の争点が何であるかを明確に示し、その後の手続の指針となる機能です。被告は、原告が何を根拠にどのような救済を求めているのかを知らなければ、効果的な防御活動を行うことはできません。同様に、裁判所も、当事者の主張内容を把握しなければ、証拠開示(ディスカバリー)の範囲を定めたり、提出される証拠の採否を判断したりといった、訴訟管理を適切に行うことができません。また、訴答を通じて、当事者間で争いのない事実が明らかになれば、それらの事実については証拠調べが不要となり、審理を真の争点に集中させることができます。
このように、訴答は訴訟全体の方向性を定めます。しかし、それがどの程度詳細であるべきかについては、長年にわたって議論されてきました。訴答に厳格な詳細さを求め、争点をできる限り絞り込むべきだという考え方がある一方で、訴答はあくまで大まかな方向性を示すに留め、争点の詳細な特定はディスカバリーなどの他の手続に委ねるべきだという考え方もあります。この思想的な対立が、アメリカにおける2つの主要な訴答システム、すなわち「事実訴答」と「通知訴答」を生み出すことになりました。
2.2 訴答の種類
現代のアメリカ民事訴訟で用いられる訴答書面は、その種類が限定されています。
- 訴状(Complaint): 原告が訴訟を開始するために最初に提出する書面です。原告の請求の根拠となる事実と、求める救済の内容(損害賠償、差止命令など)を記載します。
- 答弁書(Answer): 訴状の送達を受けた被告が提出する書面です。訴状に記載された事実の認否を明らかにするとともに、抗弁や反訴を主張することができます。
- 返答書(Reply): 被告が答弁書で反訴を提起した場合に、原告がそれに対して応答するために提出する書面です。多くの裁判所では、反訴に対する応答以外の場合には、裁判所の特別な許可がない限り、返答書の提出は認められません。
このように、訴答は原則として訴状と答弁書(反訴があれば返答書)で打ち止めとなります。主張の応酬が際限なく続くことはありません。これは、争点の整理という機能を、訴答だけに負わせるのではなく、ディスカバリーや審理前協議といった他の手続と分担させるという訴訟運営の思想を反映したものです。
2.3 訴状の要件
(1)コモンローから近代訴答へ:事実訴答と通知訴答
前述の通り、アメリカの訴答システムは、歴史的に「事実訴答(Fact Pleading)」と「通知訴答(Notice Pleading)」という2つの潮流に大別されます。
事実訴答は、19世紀のフィールド法典に端を発する、伝統的なCode Pleadingの考え方です。これは、原告に対し、「訴因(cause of action)を構成する事実」を簡潔に記載することを要求します。このシステムの理想は、法律専門家ではない一般人でも理解できる平易な言葉で、訴訟の根拠となる具体的な出来事を記述することにより、法廷に持ち込まれた紛争の実態を明らかにすることにありました。しかし、この理想は、「訴因」とは何か、そして「事実」とは何か、という二つの極めて難解な定義問題を巡る、技術的で終わりのない論争を生み出してしまいました。
「事実」の定義を巡っては、「事実(ultimate facts)」のみを記載すべきであり、「証拠事実(evidentiary facts)」や「法律上の結論(conclusions of law)」を記載してはならない、という区別がなされました。例えば、「被告は過失により自動車を運転した」という記載は「法律上の結論」であり不適切とされ、「被告は時速100キロで赤信号を無視して交差点に進入した」といった、より具体的な「事実」の記載が求められました。しかし、この三者の区別は極めて曖昧であり、どのレベルの具体性が要求されるかは裁判官の主観に委ねられ、訴答の適法性を巡る争いが頻発しました。
「訴因」の定義も同様に困難を極めました。これは、原告の「第一次的権利(primary right)」が侵害された場合に一つの訴因が成立するという理論(ポメロイ理論)や、一連の「取引または発生(transaction or occurrence)」から生じる事実の集合体を1つの訴因と捉える理論などが提唱されましたが、いずれも明確な基準とはなり得ませんでした。
このような事実訴答の複雑さと非効率性への反省から、1938年に制定された連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure, FRCP)は、通知訴答(Notice Pleading) という、より簡素で柔軟なシステムを採用しました。連邦民事訴訟規則8条(a)(2)項が要求するのは、「救済を受ける権利があることを示す(showing that the pleader is entitled to relief)、短く平易な請求の陳述(a short and plain statement of the claim)」のみです。
この通知訴答の目的は、被告に対して、どのような性質の請求が、どのような出来事に基づいて提起されたのかについて、「公正な告知(fair notice)」を与えることに集約されます。訴答の段階で、事件のすべての事実関係を詳細に記述したり、厳密な法的理論を構築したりする必要はありません。それらの作業は、訴答に続く広範なディスカバリー手続に委ねられます。この考え方を象徴するのが、長年にわたり連邦裁判所の判断基準とされてきた、Conley v. Gibson(1957年) の判決です。同判決は、「原告がその請求を裏付けるいかなる事実群も証明できないことが明白である(it appears beyond doubt that the plaintiff can prove no set of facts in support of his claim which would entitle him to relief)場合を除き、訴状は請求棄却されてはならない」と判示しました。これは、訴えが棄却されるハードルを極めて高く設定し、訴訟の初期段階で門前払いされることを可能な限り避けるという思想を反映したものでした。
(2)「もっとらしい(Plausible)」主張の要求:「Twombly」と「Iqbal」判決による転換
Conley判決が確立した寛大な「告知」基準は、半世紀にわたり、連邦裁判所における訴答のあり方を定義してきました。しかし、21世紀に入り、この基準は劇的な転換を遂げます。その契機となったのが、Bell Atlantic Corp. v. Twombly(2007年) とAshcroft v. Iqbal(2009年) という、2つの最高裁判決です。
Twombly事件は、地域の電話会社らが、相互の市場に参入しないという反トラスト法違反の共謀を行っているとして、消費者が損害賠償を求めた集団訴訟でした。訴状では、各社が競争を避けるような「並行的な行動(parallel conduct)」をとっている事実は指摘されていましたが、その背後に「共謀の合意」が存在したことを示す直接的な事実は記載されていませんでした。
最高裁判所は、この訴えを棄却しました。そして、Conley判決の「いかなる事実群も証明できないことが明白」という基準は、その言葉があまりに寛大すぎるとして、明確にこれを退けました。それに代わって最高裁が提示したのが、「もっとらしさ(plausibility)」 という新しい基準です。訴状は、単に違法行為が「考えられる(conceivable)」という可能性を示すだけでは不十分であり、救済を受ける権利があることが「もっともらしい(plausible)」 と思わせるに足る、十分な事実を記載しなければならない、とされたのです。Twombly事件では、電話会社らの並行的な行動は、違法な共謀の結果である可能性もあれば、それぞれが独立した経営判断として競争を避けたという、合法的な経済活動の結果である可能性もあります。訴状には、後者の可能性を排し、前者の「共謀」の存在をもっともらしいと思わせるだけの具体的な事実の記載が欠けている、と判断されました。
続くIqbal事件は、この「plausibility」基準が、反トラスト訴訟のような複雑な事件だけでなく、全ての民事事件に適用されることを明確にしました。同事件は、2001年の同時多発テロ後に拘束されたパキスタン人イスラム教徒が、当時の司法長官アシュクロフトとFBI長官ミューラーを相手取り、人種や宗教のみを理由に過酷な環境に拘束されたとして損害賠償を求めたものです。訴状には、両長官が、このような差別的な政策を「認識し、黙認し、意図的に合意した」と記載されていました。
最高裁は、この訴えも棄却しました。そして、「plausibility」基準を適用するための二段階の分析手法を示しました。第一に、裁判所は、訴状に記載された主張のうち、「法律上の結論」に過ぎない部分(例えば「被告らは共謀した」「差別的な意図があった」といった記載)を特定し、それらを真実であると仮定する義務から切り離します。第二に、残された「事実の陳述」のみを取り上げ、それらが全体として、請求内容の「もっとらしさ」を推認させるに足るかを判断します。Iqbal事件では、「長官らが差別的な政策に合意した」という記載は、裏付けのない「結論」に過ぎず、残された事実(テロ後に多数のイスラム系外国人が拘束されたこと等)だけでは、その拘束が、合法的な国家安全保障上の目的ではなく、違法な差別意図によるものであったということを「もっともらしい」と示すには不十分である、と結論付けられました。
これら2つの判決は、アメリカの実務に大きな影響を与えました。原告は、訴訟の初期段階で、ディスカバリーを経ずして、自らの請求を裏付ける具体的な事実を訴状に盛り込むという、より重い負担を負うことになりました。この新しい基準は、根拠の薄い訴訟を早期に排除し、被告を濫訴や高額なディスカバリーの負担から守るという利点がある一方で、原告、特に企業内部の不正など、証拠が被告側の手元に偏在している事件の原告にとっては、訴訟提起のハードルを著しく高くするものでもあります。この「plausibility」基準の具体的な運用は、今なお下級審において模索が続いており、アメリカ民事訴訟における最もホットな論点の1つとなっています。
2.4 答弁書における応答
訴状の送達を受けた被告は、定められた期間内(連邦裁判所では通常21日以内)に、答弁書(Answer)を提出して応答しなければなりません。答弁書は、防御の第一歩であり、その内容は訴訟のその後の展開を大きく左右します。
(1)認否(Admissions and Denials)
答弁書の最も基本的な機能は、訴状で原告が主張する個々の事実について、それを認めるか、否認するか、あるいは知識や情報が不足しているため認否できないか、を明らかにすることです。
- 認諾(Admission): 被告が認めた事実は、争いのない事実として確定し、原告はトライアルでその事実を立証する必要がなくなります。
- 否認(Denial): 被告が否認した事実は、訴訟の争点となり、原告はトライアルで証拠をもってその事実を立証する責任を負います。否認は、訴状の特定の段落や文章を具体的に指定して行う「部分否認(specific denial)」が原則です。訴状の主張の全てをまとめて否認する「包括否認(general denial)」も形式的には可能ですが、一部でも真実であることが明らかな主張まで否認すると、誠実義務違反(連邦民事訴訟規則11条違反)を問われるリスクがあるため、実務上は慎重に用いられます。
- 知識または情報の不足による否認(Denial for Lack of Knowledge or Information, DKI): 被告が、合理的な調査を行っても、ある事実についての知識や情報を持ち合わせておらず、認否ができない場合に用います。これは否認と同等の効力を持ち、立証責任は原告に残ります。
(2)抗弁(Affirmative Defenses)
抗弁とは、たとえ原告が主張する事実がすべて真実であったとしても、なお原告の請求を覆すに足る、新たな事実を主張するものです。これは、原告の主張そのものを攻撃する「否認」とは区別されます。
連邦民事訴訟規則8条(c)項は、時効、詐欺、不法行為、免責、禁反言、寄与過失など、抗弁として主張すべき事項を例示しています。抗弁は、被告が答弁書で明確に主張しなければ、その権利を放棄(waive)したものとみなされ、後の段階で主張することができなくなるのが原則です。これは、原告に対して不意打ちを防ぎ、防御の準備をする機会を与えるためです。
2.5 反訴(Counterclaim)と交差請求(Crossclaim)
被告は、答弁書の中で、単に防御を行うだけでなく、原告に対して積極的に自らの請求を主張することもできます。これが反訴(Counterclaim) です。
反訴には、強制的反訴(Compulsory Counterclaim) と任意的反訴(Permissive Counterclaim) の二種類があります。
- 強制的反訴: 被告の請求が、原告の請求と同一の「取引・原因(transaction or occurrence)」から生じている場合、被告はその請求を反訴として主張することが義務付けられます。もしこれを怠れば、被告はその請求権を永久に失い(請求が遮断される)、別の訴訟として提起することができなくなります。これは、関連する紛争を一つの訴訟で効率的に解決するという、訴訟経済の要請に基づくものです。
- 任意的反訴: 被告の請求が、原告の請求と同一の取引・原因から生じていない場合、被告はそれを反訴として主張することも、あるいは別の独立した訴訟として提起することも、任意に選択できます。
また、複数の被告がいる場合に、ある被告が他の共同被告に対して請求を主張することを交差請求(Crossclaim) といいます。交差請求も、原告の請求・反訴と同一の取引・原因から生じている必要があります。
2.6 訴答の修正と補充
訴訟の進行に伴い、新たな事実が判明したり、法的戦略が変更されたりした場合、当事者は自らの書面を修正する必要が生じることがあります。連邦民事訴訟規則15条は、訴答の修正について寛大な姿勢をとっており、「正義が要求するときは、自由に(freely)」修正を許可すべきであると定めています。
特に、当事者は、訴訟の初期段階(答弁書が提出される前など)であれば、相手方の同意や裁判所の許可なく、一度だけ自由に訴状を修正することができます。その後は、相手方の書面による同意または裁判所の許可が必要となりますが、相手方への不当な不利益(prejudice)とならない限り、許可は広く認められるのが通常です。
訴答の修正において特に重要なのが、「時効との関係における修正の遡及効(Relation Back of Amendments)」 です。修正された請求や加えられた新たな当事者が、本来であれば時効が完成している場合でも、その修正が元の訴状と同一の「行為、取引または発生(conduct, transaction, or occurrence)」から生じているものであれば、修正された訴答は、元の訴状が提出された時点に遡って提出されたものとみなされ、時効による障害を免れることができます。
2.7 訴答に対する異議申し立て
相手方の訴答書面に法的な瑕疵があると考える場合、当事者はそれを攻撃するための様々な申立てを行うことができます。最も重要かつ強力なものが、「請求棄却を求める申立て(Motion to Dismiss for Failure to State a Claim)」(連邦民事訴訟規則12条(b)(6))です。
これは、原告の訴状に記載された事実をすべて真実であると仮定したとしても、法的にみて、原告が救済を受ける権利を有していない、と主張するものです。この申立ては、訴答の「法的十分性」をテストするものであり、Twombly判決・Iqbal判決以降、その重要性は飛躍的に高まっています。裁判所は、この申立てを判断するにあたり、訴状の記載のみを考慮し、外部の証拠を参照することはありません。もし裁判所が外部の証拠を考慮する場合には、この申立ては「サマリー・ジャッジメントを求める申立て」として扱われることになります。
その他にも、事物管轄権の欠如、人的管轄権の欠如、不適切な裁判地、不適切な送達などを理由とする棄却申立てや、訴答内容が曖昧で応答できない場合に、より明確な陳述を求める申立て(Motion for a More Definite Statement)や無関係・中傷的な記載の削除を求める申立て(Motion to Strike)等があります。これらの防御策は、最初の答弁書またはそれに先立つ申立てにおいて主張しなければ、権利放棄とみなされるものが多いです(ただし、事物管轄権の欠如は例外です)。