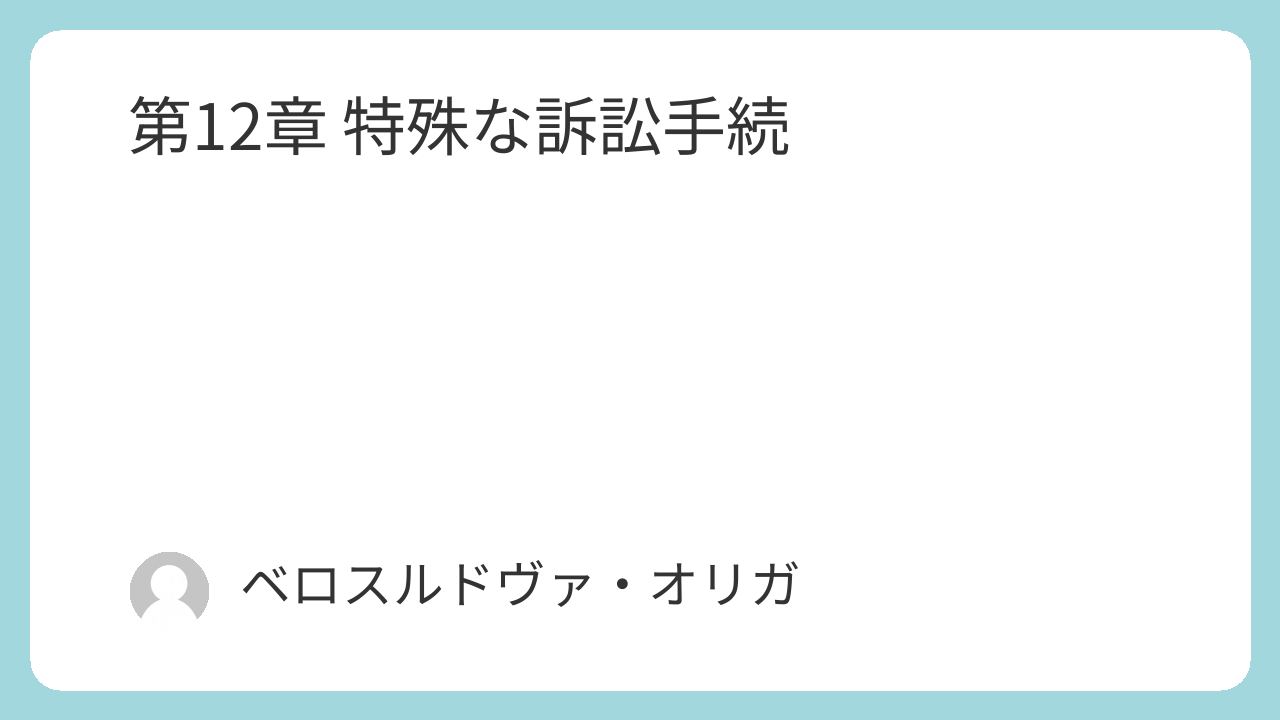第11章までで見てきたのは、主に1人の原告と1人の被告が争う、二当事者間のものでした。しかし、現代社会における紛争は、必ずしもこのような単純な構造をとるとは限りません。1つの欠陥製品が何千人もの消費者に被害を及ぼしたり、一企業の不正行為が多数の株主に損害を与えたり、あるいは1つの保険金を巡って複数の相続人が権利を主張したりと、多数の当事者が複雑に絡み合う紛争が頻繁に発生します。
このような多数当事者間の紛争を、個別の訴訟で解決しようとすれば、司法制度はたちまち麻痺し、矛盾した判決が乱立し、あるいは個々の請求額が小さいが故に誰も訴訟を起こせず、実質的な正義が実現されないという事態に陥りかねません。本章では、このような現代的な課題に対応するために発展してきた3つの強力な「特殊な訴訟手続」(①クラスアクション、②株主代表訴訟、③インタープリーダー)について解説します。
12.1 クラスアクション(集団訴訟)
(1)目的と歴史
クラスアクション(Class Action)は、数ある特殊な訴訟手続の中でも、最も強力で、社会的影響力が大きく、議論の対象となってきた制度です。これは、共通の法律上または事実上の問題を有する、多数の人々(class)を代表して、1人または数人の代表当事者(representative parties)が訴訟を提起し、その判決の効力が訴訟に参加しなかったクラスの構成員(absent class members)にまで及ぶという画期的な手続です。
クラスアクションの最大の存在意義は、司法へのアクセスの保障にあります。例えば、ある銀行が、全ての預金者に対して、違法に1ドルずつの手数料を徴収したとします。個々の預金者にとって、1ドルを取り戻すために訴訟を起こすことは、費用対効果の観点から全く現実的ではありません。その結果、銀行の違法行為は正されることなく、不当な利益が保持されてしまいます。しかし、クラスアクションを用いれば、1人の預金者が数百万人の預金者全体を代表して訴訟を起こし、銀行に対して巨額の賠償を命じることが可能となります。このように、クラスアクションは、個々の請求額は小さいが故に泣き寝入りせざるを得なかった人々の権利を集団の力によって実現するための、不可欠な社会的装置なのです。
この他にも、消費者問題・環境汚染・証券詐欺・雇用差別・製造物責任といった、広範な被害者を生む現代的な紛争を効率的かつ矛盾なく解決する上で、クラスアクションは中心的な役割を果たしています。
(2)認定要件(連邦民事訴訟規則23条)
クラスアクションは、その影響力の大きさ故に、誰でも自由に利用できるわけではありません。訴訟をクラスアクションとして進めるためには、まず裁判所から「認定(certification)」を受けるという、極めて厳格な審査を通過しなければなりません。連邦裁判所における認定要件は、連邦民事訴訟規則23条に定められており、これは多くの州法の手本となっています。
認定を受けるためには、まず、規則23条(a)項に定められた、以下の四つの前提要件をすべて満たす必要があります。
- 多数性(Numerosity): クラスの構成員が、個別に全員を訴訟に併合することが事実上不可能な(impracticable)ほど多数であること。明確な人数の基準はありませんが、通常40人以上が目安とされます。
- 共通性(Commonality): クラスの構成員に共通の法律上または事実上の問題が存在すること。近年の最高裁判例、特にWal-Mart Stores, Inc. v. Dukes(2011年)は、この要件を厳格に解釈し、単に共通の質問が存在するだけでなく、その答えが「クラス全体の主張を1つの結論へと導く」ものであることを要求しています。
- 典型性(Typicality): 代表当事者の請求または抗弁が、クラス全体の請求または抗弁の典型であること。これは、代表当事者の利益とクラス全体の利益が、同じ出来事や法的理論から生じていることを意味します。
- 代表の適切性(Adequacy of Representation): 代表当事者およびその代理人弁護士が、クラス全体の利益を公正かつ適切に保護する能力と意思を有していること。代表当事者と他のクラス構成員との間に利益相反がないことが、特に重要となります。この要件は、訴訟に参加しない構成員を判決の効力で拘束することを正当化する、デュー・プロセス上の根幹をなすものです。
これら4つの前提要件を満した上で、当該クラスアクションが、規則23条(b)項に定められた以下の3つの類型のいずれかに該当する必要があります。
- (b)(1)項クラス(「矛盾回避」型): 個別訴訟を許した場合に、(A)被告に対して矛盾した判決が下されるリスクがある場合、又は、(B)一部の者に対する判決が他の構成員の利益を事実上害する(例えば、限られた基金からの賠償を求める訴訟で早い者勝ちになってしまう)場合に用いられます。
- (b)(2)項クラス(「差止」型): 被告が、クラス全体に対して一般的に適用される行為を行うことを拒否したため、クラス全体に対する差止命令(injunctive relief)又は宣言的判決(declaratory relief)が適切な場合に用いられます。公民権訴訟や雇用差別訴訟が典型例です。
- (b)(3)項クラス(「損害賠償」型): 上のいずれにも該当しないが、共通の問題が、個々の構成員に固有の問題よりも優越(predominate)し、かつ、紛争を解決する上でクラスアクションが他のいかなる方法よりも優れている(superior)場合に用いられます。消費者被害や証券詐欺など、金銭賠償を主たる目的とするクラスアクションのほとんどが、この類型に属します。
(b)(3)項クラスは、その性質上、構成員ひとりひとりの状況(例えば、損害額)が異なるため、認定要件が最も厳格です。特に、この類型のクラスアクションでは、デュー・プロセスの要請から、クラス構成員に対して、①訴訟が提起されたことを知らせる最善の告知(notice)を行い、②希望すればクラスから離脱(opt out)して判決の効力に拘束されない権利を与えることが、義務付けられています。
(3)判決の効力
適切に認定され、手続が進められたクラスアクションの判決は、(b)(3)項でクラスから離脱した者を除き、訴訟に直接参加しなかったクラスの全構成員に対して、請求の遮断及び争点の遮断の効力が及びます。これにより、1つの判決で、数千、数万、時には数百万人の権利関係を、一挙に確定させることが可能となるのです。
12.2 株主代表訴訟(Shareholder-Derivative Suits)
株主代表訴訟は、クラスアクションと類似の構造を持ちますが、その目的と当事者の関係において特殊な訴訟形態です。これは、株式会社の株主が、会社自身に代わって、会社の取締役や役員などに対して訴訟を提起するものです(連邦民事訴訟規則23.1条)。
この訴訟の本質は、取締役の違法行為や忠実義務違反によって会社自身が被った損害を、会社のために回復することにあります。例えば、取締役が自己の利益のために会社に損害を与える取引を行った場合、その損害を賠償するよう求めるのは、本来、会社自身であるべきです。しかし、その会社を経営しているのがまさに不正を働いた取締役自身である場合、会社が自らを訴えることは期待できません。
このような状況で、株主は、いわば「会社の名において」、会社の権利を行使し、不正を働いた経営陣の責任を追及することができます。この訴訟は、株主個人の損害を回復するものではなく、あくまで会社の損害を回復するためのものであるため、もし原告である株主が勝訴した場合、被告である取締役が支払う賠償金は、株主個人ではなく会社に支払われます。
株主代表訴訟を提起するためには、いくつかの特殊な手続要件を満たす必要があります。最も重要なのが「取締役会への要求(demand requirement)」です。株主は、訴訟を提起する前に、まず会社の取締役会に対して、会社自身が不正を働いた取締役を訴えるよう、書面で要求しなければなりません。そして、取締役会がその要求を不当に拒否した場合に初めて、株主は代表訴訟に踏み切ることができます。これは、会社の経営判断はまず第一に取締役会に委ねられるべきである、という会社法の基本原則を尊重するものです。
12.3 インタープリーダー(Interpleader)
インタープリーダーは、前の2つとは異なり、原告となる者のための手続です。これは、ある特定の財産や金銭(stake)を保有している者(stakeholder)が、そのステークに対して、複数の者(「請求者(claimants)」)から、互いに両立しない請求を受けている場合に、自らを用いることができる訴訟手続です(連邦民事訴訟規則22条、および合衆国法典第28編1335条)。
例えば、生命保険会社が、被保険者の死亡保険金(stake)を支払おうとしたところ、被保険者の妻と、前妻との間の子供が、それぞれ自分こそが正当な受取人であると主張してきたとします。もし保険会社が、自らの判断で妻に保険金を支払った後で、裁判所が子供の権利を認めた場合、保険会社は二重に支払いを強制されるリスクを負います。
このような多重責任のリスクを回避するため、ステークホルダーである保険会社は、インタープリーダー訴訟を提起することができます。この訴訟では、保険会社は、保険金を裁判所に供託(deposit)した上で、複数の請求者全員を被告として法廷に呼び出し、「誰がこの金銭を受け取る正当な権利者であるかを、あなた方同士で決めてください」と求めるのです。これにより、ステークホルダーは紛争から安全に離脱し、裁判所が下した単一の判決によって全ての請求者の権利関係が一度に確定されます。
連邦法には、通常の民事訴訟規則に基づく「Rule Interpleader」と、特別な法律に基づく「Statutory Interpleader」の2種類があり、後者は、請求者が複数の州にまたがっている場合でも容易に連邦裁判所の管轄権を確保できるような、緩和された要件が定められています。