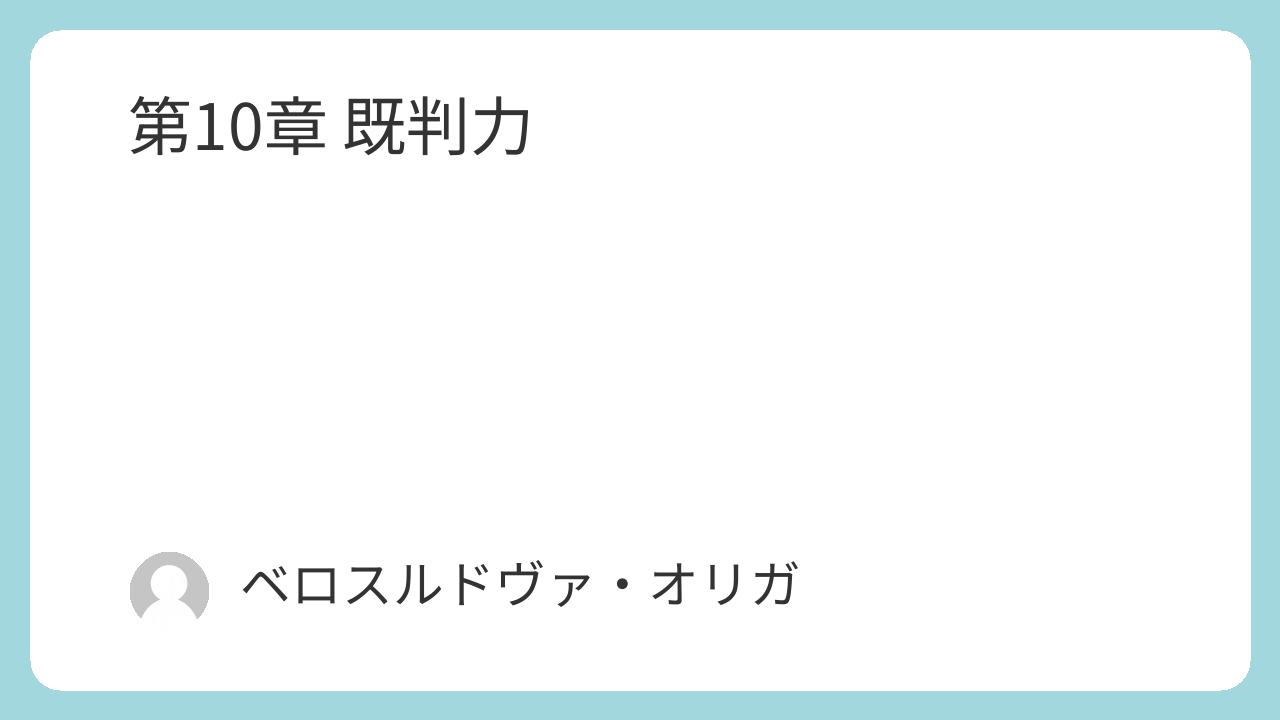10.1 既判力:紛争の蒸し返しを防ぐ
訴訟が終局判決に至り、上訴の機会も尽きたとき、その判断は最終的なものとして確定します。当事者はその判断に法的に拘束され、紛争は解決されたものとみなされます。もし、敗訴した当事者がその結果に不服であるからといって、全く同じ主張で再び訴訟を提起することが許されるならば、訴訟には終わりがなくなり、判決は意味をなさなくなるでしょう。
このような事態を防ぎ、一度なされた司法的判断の安定性(finality)と終結性を確保するための法原理が既判力(Res Judicata)です。ラテン語で「既に裁かれた事柄」を意味するこの言葉は、2つの重要な公共政策をその根底に有しています。第一に、当事者の保護です。何人も、同じ紛争について2度も訴訟の煩わしさに晒されるべきではありません。第二に、訴訟経済です。限りある司法資源を、既に解決されたはずの紛争の再審理に費やすことは、他の解決を待つ事件の審理を遅らせることに繋がり、社会全体の不利益となります。
この既判力の概念は、現代のアメリカ法では、その効果の及ぶ範囲に応じて、2つの異なる法理に分けて理解されています。
- 請求の遮断(Claim Preclusion): これは伝統的に「Res Judicata」と呼ばれてきた法理そのものです。一度、有効な終局判決が本案について下されると、同一の当事者(及びその承継人)は、同一の請求(claim)について、再び訴訟を提起することができなくなります。原告が勝訴した場合、その請求は判決に「吸収(merger)」され、新たな訴えは許されません。原告が敗訴した場合、その請求は判決によって「遮断(bar)」され、同様に再訴は許されません。重要なのは、この法理が、前の訴訟で実際に主張された事項だけでなく、その請求の一部として主張することができたはずの全ての事項にまで及ぶ点です。
- 争点の遮断(Issue Preclusion): これは伝統的に「付随的禁反言(Collateral Estoppel)」と呼ばれてきた法理です。ある訴訟において、特定の争点(issue)が当事者間で実際に争われ、裁判所によって現実に判断され、かつ、その判断が判決にとって不可欠であった場合、その争点についての判断は、後の別の請求に関する訴訟においても、同一の当事者間での再度の争い(再訴)を許さない、というものです。
これら2つの法理は、しばしば混同されますが、その適用要件と効果は明確に異なります。請求の遮断が「請求」という大きな単位で訴訟全体を禁じるのに対し、争点の遮断は「争点」というより小さな単位で、特定の事実または法律問題についての再審理のみを禁じます。以下の各節で、それぞれの法理を詳細に見ていきます。
10.2 請求の遮断(Claim Preclusion):Res Judicata
(1)「請求(Claim)」の範囲:取引アプローチ
請求の遮断の効力がどこまで及ぶかを決定する上で、最も重要かつ難解な問題が、「請求(claim)」の範囲をどのように画定するか、という点です。
コモンローの時代、請求の範囲はwritの種類によって画されていました。しかし、writ制度が廃止された現代においては、より機能的な基準が必要となります。伝統的には、「第一次的権利(primary right)」理論が有力でした。これは、例えば、一個人の身体に対する権利、財産に対する権利はそれぞれ別個の「第一次的権利」であり、1つの不法行為によって身体と財産の両方に損害が生じた場合でも、2つの異なる請求(訴因)が存在すると考えるものでした。この考え方によれば、原告はまず身体への損害について訴訟を起こし、それが終結した後に、財産への損害について別の訴訟を起こすことが可能でした。
しかし、このような考え方は、関連する紛争を細分化し、非効率な訴訟を助長するとの批判を浴びました。これに代わって、連邦民事訴訟規則および判例法リステイトメント(第二次)が採用し、現在のアメリカにおける主流となっているのが「Transactional Approach」です。
このアプローチによれば、「請求」の範囲は、その基礎となる「transaction, or series of connected transactions」から生じる全ての権利・救済を含む、と定義されます。ここでいう「transaction」とは、時間、場所、動機、発生原因において事実関係が密接に関連し、当事者の期待やビジネス上の慣行からみて、一つの単位として扱うのが自然な事実の集合体を指します。
このアプローチの下では、先の例のように、1つの交通事故によって身体と財産の両方に損害を被った場合、たとえ損害の種類が異なっても、それらは全て「同一のtransaction(事故)」から生じたものとして、1つの請求を構成します。したがって、原告は、身体と財産に関する全ての損害賠償を、1つの訴訟でまとめて主張しなければなりません。もし、原告が身体への損害についてのみ訴訟を提起して判決を得た場合、請求の遮断の法理によって、後から財産への損害について別の訴訟を提起することは許されません。なぜなら、その主張は、最初の訴訟で「主張することができたはず」の事項だからです。
この「Transactional Approach」は、当事者に対し、関連する全ての紛争を1回で解決することを強く促すものであり、訴訟経済の理念を色濃く反映しています。
(2)適用要件
請求の遮断が適用されるためには、3つの要件を満たす必要があります。
- 有効な終局判決(A Valid, Final Judgment): 前の訴訟における判決が、有効かつ終局的なものでなければなりません。「有効」とは、判決を下した裁判所が、適切な事物管轄権と人的管轄権を有していたことを意味します。「終局的」とは、前章で述べた終局判決主義の通り、第一審裁判所が本案について最終的な判断を下し、事件がそのレベルでは終結していることを指します。多くの裁判所では、たとえ上訴が係属中であっても、第一審判決は既判力を生じさせると解されています。
- 本案についての判断(On the Merits): 判決が、訴訟の実体的内容、すなわち請求権の当否について下されたものでなければなりません。トライアルの末に下された評決や判決、あるいはサマリー・ジャッジメントは、典型的な「本案についての判断」です。デフォルト判決も、責任に関する限り、本案についての判断とみなされます。一方で、事物管轄権の欠如、人的管轄権の欠如、不適切な裁判地、あるいは必要当事者の欠落といった、手続的な理由による訴えの却下は、本案についての判断ではないため、請求の遮断の効力は生じません。
- 同一の当事者(The Same Parties): 前の訴訟と後の訴訟の当事者が、同一であるか、あるいは「承継関係(privity)」にある者でなければなりません。これについては、10.4で詳述します。
10.3 争点の遮断(Issue Preclusion):Collateral Estoppel
(1)適用要件
請求の遮断が、一度戦った「ステージ」への再入場を禁じるルールであるとすれば、争点の遮断は、一度使われた「武器」の再利用を、たとえ別のステージであっても禁じるルールです。この法理が適用されるためには、以下の厳格な要件がすべて満たされなければなりません。
- 同一の争点(Identical Issue): 前の訴訟で判断された争点と、後の訴訟で問題となっている争点が、事実上および法律上、完全に同一でなければなりません。この要件は厳格に解釈されます。例えば、ある年の所得税に関する判断は、たとえ事実関係が酷似していても、翌年の所得税に関する訴訟の争点とは「同一」ではないと判断されることがあります。
- 実際に争われ、現実に判断されたこと(Actually Litigated and Determined): これは、請求の遮断との最も重要な違いです。争点の遮断は、その争点が、前の訴訟で当事者によって現実に争点として提示され、証拠が提出され、裁判所によって明確に判断された場合にのみ適用されます。したがって、当事者が認諾した事実、デフォルト判決の基礎となった事実、又は法廷で争われなかった事実については、たとえそれが事件にとって重要であったとしても、争点の遮断の効力は生じません。
- 判決にとって不可欠であったこと(Essential to the Judgment): その争点についての判断が、前の訴訟の判決を導き出す上で、必要不可欠なものでなければなりません。もし、裁判所が、ある判決を支持するために2つの独立した理由を挙げた場合、そのどちらか一方だけでも判決を支えることができるため、両方の理由とも「不可欠」ではなかったとみなされ、後の訴訟で争点遮断の効力を持たない、と判断されることがあります。また、ある争点についての判断が、判決の傍論で述べられたに過ぎない場合も、この要件を満たしません。この要件の目的は、当事者と裁判所が、その重要性を十分に認識し、真剣に争い、慎重に判断した争点についてのみ、終結させる効力を与えることにあります。
(2)当事者相互主義(Mutuality)の崩壊
伝統的なコモンローの下では、争点の遮断の効力は「当事者相互主義(mutuality of estoppel)」の原則に支配されていました。これは、前の訴訟の判決を利用して相手方の再訴を封じることができるのは、自らもその訴訟の当事者であり、もし判決が不利なものであったなら、それに拘束されたであろう者に限られる、という考え方です。つまり、「盾」として使われるリスクを負った者だけが、「剣」として使うことができる、という理屈です。
しかし、この原則は、訴訟経済の観点から不合理であるとの批判を浴びました。例えば、バス会社が運行するバスの事故で、50人の乗客が負傷したとします。最初の乗客Aがバス会社を訴え、トライアルの結果、「バス会社の運転手には過失があった」という判断が確定し、Aが勝訴したとします。次に、乗客Bが同じ事故についてバス会社を訴えた場合、伝統的な相互主義の下では、BはAの勝訴判決を利用することはできません。なぜなら、Bは前の訴訟の当事者ではなく、もしAが敗訴していたとしても、Bはその判断に拘束されないからです。その結果、バス会社は、B、C、D…と続く49人の乗客との訴訟で、毎回「運転手の過失」という同じ争点を、ゼロから争う機会を与えられることになり、これは訴訟資源の甚だしい浪費です。
このような不合理を是正するため、カリフォルニア州最高裁判所のBernhard v. Bank of Americ (1942年) 判決を皮切りに、アメリカの裁判所は、この当事者相互主義の原則を大幅に放棄するに至りました。
現代のルールでは、争点の遮断の効力を主張するのが、前の訴訟の当事者でなかった「非当事者(non-party)」であっても、その効力が主張される相手方が前の訴訟の当事者であり、その争点について十分かつ公正に争う機会(full and fair opportunity to litigate)を有していた場合に限り、非相互的な主張が認められます。
この非相互的な争点遮断(non-mutual issue preclusion)には、二つの形態があります。
- 防御的利用(Defensive Use): 後の訴訟の被告が、前の訴訟で原告が別の被告に敗訴した判決を「盾」として利用し、原告の請求を退ける場合。これは、Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation(1971年) で最高裁が是認しました。これにより、特許権者が、ある被告との訴訟で特許が無効と判断された後、別の被告を相手取って同じ特許の有効性を繰り返し争う、といったことができなくなりました。
- 攻撃的利用(Offensive Use): 後の訴訟の原告が、前の訴訟で被告が別の原告に敗訴した判決を「剣」として利用し、被告の責任を証明しようとする場合。これは、先のバス事故の例で、乗客Bが乗客Aの勝訴判決を利用するケースです。最高裁は、Parklane Hosiery Co. v. Shore(1979年) において、この攻撃的利用も原則として認められると判示しましたが、防御的利用に比べて、被告にとって不公平となる危険性が高いため、裁判所は、その適用を許可するか否かについて、より広い裁量を持つとしました。裁判所が考慮すべき要素としては、①後の訴訟の原告が、前の訴訟に容易に参加できたにもかかわらず、意図的に「様子見(wait and see)」を決め込んでいなかったか、②被告にとって、前の訴訟は、将来の訴訟を予測できず、全力で争うインセンティブに欠けるものではなかったか、③前の訴訟の判決が、それ以前の他の判決と矛盾していないか、④後の訴訟において、被告が利用できる、前の訴訟では利用できなかった重要な手続的機会が存在しないか、といった点が挙げられます。
10.4 誰が判決に拘束されるか
最後に、誰が判決の効力に拘束されるのか、という問題があります。
この問いに対する最も基本的な答えは、デュー・プロセスに由来します。すなわち、何人も、自らが当事者として参加し、主張と証拠を提出する機会を与えられた訴訟の結果によってしか、法的に拘束されることはありません。したがって、既判力の拘束力は、原則として、前の訴訟の当事者(parties)であった者にしか及びません。
しかし、この原則には、重要な例外が存在します。それが「承継関係(Privity)」にある者です。これは、形式的には訴訟の当事者ではなかったとしても、前の訴訟の当事者と極めて密接な利害関係を有しており、実質的にその当事者によって利益が代表されていたとみなせる者を、判決の効力が及ぶ範囲に含める法理です。
「承継関係」にあるとみなされる典型的な例は、以下の通りです。
- 財産の承継人: 前の訴訟で争われた財産を、判決後に当事者から譲り受けた者。
- 利益が代表されていた者: 信託における受益者(受託者が当事者であった場合)や、遺産相続人(遺言執行者が当事者であった場合)など、法的な代表関係が存在する場合。
- 訴訟を実質的に支配した者: 表向きは当事者ではないが、背後で訴訟費用を負担し、訴訟戦略を決定するなど、訴訟を事実上コントロールしていた者(例えば、製造物責任訴訟における製造業者の賠償責任保険会社など)。
そして、この原則の最大の例外が、クラスアクション(集団訴訟)です。適切に認定され、手続が進められたクラスアクションの判決は、訴訟に直接参加していなかったとしても、そのクラスの全ての構成員(absent class members)に対して、請求の遮断および争点の遮断の効力が及びます。これは、クラスの代表当事者と代理人弁護士が、不在の構成員の利益を十分かつ公正に代表することが、デュー・プロセス上の要請として担保されていることを前提としています。
既判力は、個々の紛争解決に終止符を打つだけでなく、司法制度全体の安定性と信頼性を支える、不可欠な基盤なのです。