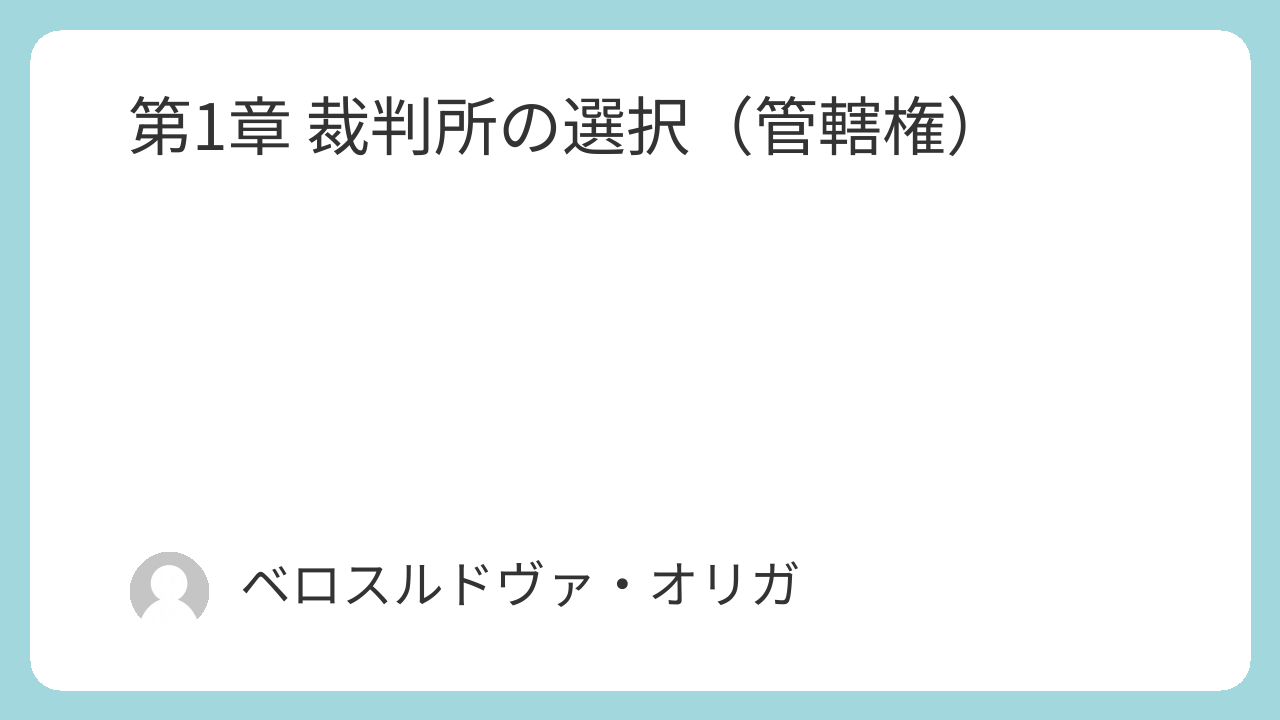1.1 どの裁判所で争うか
アメリカで民事訴訟を開始するにあたり、原告とその代理人弁護士が最初に直面する、そして最も戦略的な判断を迫られる問題が、「どの裁判所で訴訟を提起すべきか」という問いです。これは単に地理的な利便性の問題ではありません。アメリカは、連邦政府と各州がそれぞれ独立した司法権を有する「二元的司法制度」を採用しており、原告は多くの場合、連邦裁判所と州裁判所という二つの異なる裁判所システムの中から、自らにとって最も有利な法廷を選択するという、重大な決断を迫られます。
この裁判所選択が訴訟戦略の根幹をなすのは、どの裁判所を選ぶかによって、適用される手続法はもちろんのこと、場合によっては適用される実体法、陪審員の構成、裁判官の質や傾向、そして審理にかかる時間まで、訴訟の帰趨を左右するあらゆる要素が変動しうるからです。例えば、広範な証拠開示が可能な連邦民事訴訟規則を利用したい、あるいは特定の州法が有利に働く州裁判所を選びたい、といった戦術的な思惑が、裁判所選択の動機となることは日常茶飯事です。
しかし、訴えを受理し、有効な判決を下すために、裁判所は事件と当事者に対して正当な権限を持っていなければなりません。この裁判所の権限の基礎となるのが「裁判管轄権(Jurisdiction)」の概念です。裁判所が事件を審理するためには、3つのハードルを越える必要があります。
第一に、その裁判所が特定の「種類」の事件を取り扱う権限を有しているかという「事物管轄権(Subject-Matter Jurisdiction)」。第二に、その裁判所が特定の「被告」に対して判決を下す人的な権限を有しているかという「人的管轄権(Personal Jurisdiction)」。そして第三に、事物管轄権と人的管轄権が認められた上で、地理的にどの「場所」の裁判所で審理するのが適切かという「裁判地(Venue)」です。
これら3つの要件のうち、いずれか1つでも欠けば、訴えは却下され、又は、移送されることになります。したがって、訴訟を提起する側は、これらの複雑なルールを正確に理解し、自らの主張が認められる可能性が最も高い法廷を戦略的に選ぶ必要があります。一方で、訴えられた被告側も、原告が選択した裁判所の管轄権に瑕疵がないかを鋭く吟味し、もし欠陥があればそれを指摘して訴えを退け、又は、自らにとってより有利な裁判地へ移送させるという防御戦略をとることが可能となります。
1.2 裁判管轄権の基礎
前述のように、裁判所が事件を審理するためには、事物管轄権、人的管轄権、そして裁判地という3つの要件を満たす必要があります。これらはそれぞれ異なる次元の問題であり、明確に区別して理解することが不可欠です。
①事物管轄権(Subject-Matter Jurisdiction) は、裁判所の「権限の種類」に関するものです。つまり、その裁判所が、憲法や法律によって、特定の主題(subject matter)や性質を持つ事件(例えば、連邦法に関する事件、特定の訴額以上の事件、家庭事件、破産事件など)を審理する権限を与えられているか、という観点から判断されます。州裁判所は、一般的に広範な事物管轄権(General Jurisdiction)を有する「一般管轄裁判所」であり、特定の法律で連邦裁判所の専属管轄とされていない限り、ほとんどすべての種類の民事事件を審理できます。これに対し、連邦裁判所は、合衆国憲法第3条に定められた範囲内の事件しか審理できない「制限的管轄裁判所(Courts of Limited Jurisdiction)」です。連邦裁判所が事件を審理するためには、必ず法律上の明確な根拠が必要となります。そして、最も重要な原則は、事物管轄権は当事者の合意によって創設したり、権利放棄したりすることができない、という点です。裁判のどの段階であっても、事物管轄権の欠如が明らかになれば、裁判所は自らの判断で訴えを却下しなければなりません。
②人的管轄権(Personal Jurisdiction) は、裁判所の「権限の及ぶ範囲」に関する問題であり、特定の被告(個人または法人)に対して、その者の権利や義務に関する判決を下す権限が裁判所にあるか、というものです。これは、合衆国憲法修正第14条のデュー・プロセス条項によって規律される被告の憲法上の権利と密接に結びついています。原則として、被告が裁判の行われる州と何らの関係も持たない場合、その州の裁判所が被告に対して判決を下すことは許されません。この人的管轄権は、被告の権利であるため、事物管轄権とは異なり、被告が異議を申し立てずに訴訟に応じるなどした場合、その権利を放棄したものとして扱うことが可能です。
③裁判地(Venue) は、事物管轄権と人的管轄権が共に存在することを前提として、その州や連邦の裁判所システムの中で、地理的に「どの場所」にある裁判所で審理するのが最も適切かを定めるルールです。これは憲法上の要請ではなく、主として当事者や証人の利便性、そして司法行政上の効率性を目的として法律で定められています。例えば、被告の住所地、事件が発生した場所、あるいは契約が履行されるべき場所などが裁判地の基準となります。人的管轄権と同様、裁判地に関するルールは被告の利益を保護するものであるため、被告が異議を申し立てなければ、その瑕疵は治癒される(権利放棄とみなされる)ことになります。
1.3 連邦裁判所の事物管轄権
(1)連邦の裁判所制度の概要:限定された権限
アメリカの連邦裁判所制度を理解する上で最も重要なのは、その権限が合衆国憲法によって創設され、かつ、厳格に限定されているということです。合衆国憲法第3条第2節は、連邦司法権が及ぶ事件のカテゴリーを9つに限定列挙しています。連邦議会は、この憲法上の限界を超えて連邦裁判所の管轄権を拡大することはできず、また、連邦裁判所自身がこの限界を超えて権限を行使することも許されません。
この「限定管轄」の原則は、極めて厳格に解釈・運用されます。州の一般管轄裁判所では管轄権の存在が推定されるのに対し、連邦裁判所では、訴えを提起する原告が、事物管轄権が存在することを積極的に主張し、証明する責任を負います。そして前述の通り、この要件は当事者の合意や権利放棄によって免除されることはありません。
この原則の厳格さを示す古典的な判例が、Capron v. Van Noorden (1804年) です。この事件で原告であるCapronは、ノースカロライナ州の連邦裁判所に訴えを提起し、敗訴しました。ところが、Capronは上訴審において、驚くべきことに、自らが訴えを提起した第一審裁判所に事物管轄権がなかったと主張したのです。訴状には被告がノースカロライナ州の市民であることは記載されていましたが、多様性管轄権の要件を満たすために不可欠な、原告自身の市民権についての記載が欠けていました。最高裁判所はこの主張を認め、第一審判決を破棄しました。自ら連邦裁判所を選んでおきながら、敗訴した途端にその裁判所の権限の欠如を主張して判決を覆すことが認められたこの判決は、連邦裁判所の管轄権の限界を維持することが、信義則や訴訟経済といった事柄にさえ優先するという、連邦主義の根幹にある強い思想を象徴するものとなっています。
現在、連邦裁判所が事物管轄権を行使する主要な根拠は、「連邦問題管轄権」と「多様性管轄権」の二つです。
(2)連邦問題管轄権(Federal Question Jurisdiction)
連邦問題管轄権は、合衆国憲法、連邦法、または合衆国が締結した条約の下で「生じる(arising under)」全ての民事事件に及びます。これは、連邦法の解釈・適用に関する紛争は、その専門性を有する連邦裁判所が判断するのが最も適切であるという考えに基づいています。現代のアメリカでは、連邦法が規律する社会・経済分野が拡大し続けるのに伴い、この連邦問題管轄権の重要性はますます高まっています。
この管轄権の有無を判断する上で、長年にわたり判例法理の中核をなしてきたのが、「Well-Pleaded Complaint Rule」 です。これは、連邦問題が、原告の訴状において、原告自身の請求権(claim for relief)の構成要素として、適切かつ必要不可欠な形で記載されていなければならない、という原則です。たとえ被告が答弁において連邦法上の抗弁を主張したり、あるいは原告が訴状の中で被告が主張するであろう連邦法上の抗弁を「予測」して記載したりしたとしても、それだけでは連邦問題管轄権の基礎とはなりません。
この原則を確立したのが、Louisville & Nashville Railroad Co. v. Mottley(1908年) です。原告Mottley夫妻は、過去の鉄道事故の和解契約に基づき、鉄道会社から生涯有効の無料パスを供与されていました。しかし、連邦議会が鉄道会社による無料パスの発行を禁止する法律を制定したため、鉄道会社はパスの更新を拒否しました。モトリー夫妻は、契約の履行を求めて連邦裁判所に提訴し、訴状の中で、連邦法は自分たちの契約には適用されない、仮に適用されるとしても同法は違憲である、と主張しました。
最高裁判所は、本案の判断に入ることなく、自らの判断で事物管轄権の欠如を指摘し、訴えを却下しました。最高裁によれば、Mottley夫妻の請求権の根拠は、あくまで州法上の「契約」であり、連邦法の問題は、鉄道会社が主張するであろう「抗弁」を予測したものに過ぎません。原告の請求権そのものが連邦法から生じているわけではないため、連邦問題管轄権は存在しない、と判断したのです。この判決は、連邦問題管轄権の有無が、訴訟の初期段階で、原告の訴状のみに基づいて客観的に判断されるべきであるという、明確な基準を示しました。
近年、この原則はさらに洗練されています。州法上の請求であっても、その勝敗が「実質的かつ争いのある」連邦法の問題の解決に依存している場合には、例外的に連邦問題管轄権が認められることがあります。Grable & Sons Metal Products, Inc. v. Darue Engineering & Mfg.(2005年) で最高裁が示した判断基準によれば、州法上の請求が、(1)必然的に連邦法の問題を提起し、(2)その連邦法の問題が実質的であり、かつ実際に争われており、(3)連邦裁判所が管轄権を行使しても、連邦と州の司法責任のバランスを崩さない、という3つの要件を満たす場合に、連邦問題管轄権が認められます。この判断は、事案ごとの慎重な利益衡量に委ねられており、依然として複雑な領域となっています。
(3)多様性管轄権(Diversity Jurisdiction)
多様性管轄権は、アメリカ建国当初から存在する、連邦裁判所の管轄権のもう一つの大きな柱です。これは、(a) 異なる州の市民の間、または (b) 米国の州の市民と外国の市民との間の民事事件で、かつ、(c) 訴額が75,000ドルを超えるものについて、連邦裁判所に管轄権を認めるものです。
この制度が創設された歴史的な目的は、州裁判所が他州の市民に対して抱くかもしれない地域的な偏見や不公平な扱いから、州外の当事者を保護することにあると説明されてきました。州外の当事者に、より中立的であると期待される連邦裁判所という選択肢を与えることで、公正な裁判を保障しようというのです。しかし、現代においては、「このような地域的偏見はもはや過去のものであり、多様性管轄権は連邦裁判所の事件負担を不必要に増大させる時代遅れの制度である」という批判もあります。
多様性管轄権が認められるためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。
第一に、「Complete Diversity Requirement」 です。これは、Strawbridge v. Curtiss(1806年) で確立された原則であり、原告側の「誰か一人」の市民権(citizenship)と、被告側の「誰か一人」の市民権が、同じ州であってはならない、というものです。例えば、ニューヨーク州の市民である原告が、デラウェア州の市民とニューヨーク州の市民を共同被告として訴えたい場合、被告の一人が原告と同じニューヨーク州の市民であるため、この要件は満たされず、多様性管轄権は成立しません。
個人の「市民権」は、その者の「住所(domicile)」がある州によって決まります。「住所」とは、単なる居住地(residence)とは異なり、その者が固定的に生活の本拠を構え、かつ、そこを離れてもいずれは帰還する意思を持つ場所を指します。法人の「市民権」はより複雑です。法人は、その設立準拠法州(state of incorporation)と、主たる事業所(principal place of business)の所在州の、二つの州の市民権を持つとみなされます。主たる事業所がどこであるかについては、長年、裁判所の間で解釈が分かれていましたが、Hertz Corp. v. Friend(2010年) において、最高裁判所は「nerve center test」 を採用しました。これは、法人の役員が、法人の活動を指示、管理、調整する場所、すなわち法人の事実上の本社機能が存在する場所を主たる事業所とみなす、という基準です。
第二に、「訴額要件(Amount in Controversy)」 です。争いの対象となる金額が、利息と訴訟費用を除いて、75,000ドルを超えなければなりません。この金額は、原告が訴状で誠実に主張する金額に基づいて判断され、その請求が「法的な確実性をもって(to a legal certainty)」75,000ドル以下であると立証されない限り、要件は満たされるとみなされます。一人の原告が、一人の被告に対して複数の請求をする場合、それらの請求額を合算して訴額要件を満たすことができます。しかし、複数の原告がそれぞれの請求額を合算したり、一人の原告が複数の被告に対する請求額を合算したりすることは、原則として認められません。
多様性管轄権をめぐっては、当事者がこれを人為的に創出したり、あるいは被告による連邦裁判所への移送を妨害しようとする試みがなされることがあります。例えば、本来の請求権者が、多様性を創出するためだけに、他州の市民に名義上の請求権譲渡を行うような場合です。このような共謀による管轄権の創出は、連邦法(合衆国法典第28編第1359条)によって明確に禁止されています。
なお、多様性管轄権には、連邦裁判所が伝統的に介入を避けてきた2つの例外分野が存在します。それは家事関係事件(divorce, alimony, child custodyなど)と遺産事件(probate matters)です。これらの分野は、伝統的に各州が規律すべき問題であると考えられているため、たとえ当事者間に多様性があり、訴額要件を満たしていても、連邦裁判所は審理を差し控えるのが一般的です。
(4)補充的管轄権(Supplemental Jurisdiction)
連邦裁判所が、連邦問題管轄権や多様性管轄権といった独立した事物管轄権の根拠を持つ請求(アンカー・クレーム)を審理する場合、そのアンカー・クレームと密接に関連する、それ自体では独立した管轄権の根拠を持たない他の請求についても、併せて審理する権限を持つことがあります。これが補充的管轄権(Supplemental Jurisdiction) です。この制度は、司法の効率化と、当事者間の紛争の一回的解決を目的としています。
この管轄権は、歴史的には「付随的管轄権(Ancillary Jurisdiction)」 と「ペンダント管轄権(Pendent Jurisdiction)」 という、2つの異なる判例法理として発展してきました。しかし、1990年に制定された合衆国法典第28編第1367条によって、これらの法理は「補充的管轄権」という1つの概念に統合・成文化されました。
同条(a)項は、アンカー・クレームと同一の「事件または争訟(case or controversy)」の一部をなす全ての他の請求について、補充的管轄権が及ぶと定めています。この「事件または争訟」の範囲は、United Mine Workers of America v. Gibbs(1966年) で示された「common nucleus of operative fact」という基準によって判断されるのが一般的です。
しかし、この補充的管轄権の適用には、特に多様性管轄権がアンカー・クレームの根拠となっている場合に、重要な制限が課せられています。同条(b)項は、多様性管轄権の「完全な多様性の要件」を潜脱するような形で補充的管轄権を行使することを禁じています。例えば、原告が、連邦民事訴訟規則14条(第三者訴訟)、19条(必要当事者の併合)、20条(任意的当事者の併合)、24条(訴訟参加)に基づいて加えられた当事者に対して請求を行う場合、その請求が完全な多様性の要件を破壊するものであれば、補充的管轄権を行使することはできません。これは、Owen Equipment & Erection Co. v. Kroger(1978年) の判例法理を成文化したものです。
また、同条(c)項は、たとえ補充的管轄権が存在する場合でも、裁判所がその行使を裁量で拒否できる4つの場合を定めています。①州法の請求が、新規または複雑な問題を含んでいる場合、②州法の請求が、連邦裁判所の本来の管轄権の基礎となる請求よりも実質的に優越する場合、③連邦裁判所が、本来の管轄権の基礎となる全ての請求を棄却した場合、④その他、例外的な状況において、管轄権の行使を拒否すべきやむを得ない理由がある場合です。
(5)移送(Removal)
原告が州裁判所に訴訟を提起した場合でも、その事件が本来、連邦裁判所の事物管轄権の下にあるものであれば、被告は、事件を州裁判所から連邦裁判所に移送することができます。これは、原告が持つ裁判所選択権とバランスをとるために、被告に与えられた権利です。
移送が認められるための基本的な要件は、その事件が、もし原告によって最初に提起されていたとしたら、連邦裁判所が事物管轄権を有したであろう、ということです。したがって、連邦問題管轄権または多様性管轄権のいずれかの要件を満たす必要があります。
ただし、多様性管轄権に基づく移送には、重要な制限があります。すなわち、被告のいずれか1人が、訴訟が提起された州の市民である場合には、移送は認められません。これは、多様性管轄権の本来の目的が州外当事者の保護にあることから、自州の裁判所で偏見を受けるおそれのない地元(in-state)の被告にまで、連邦裁判所への逃げ道を与える必要はない、という考えに基づいています。
移送の手続は、被告が、事件が係属している州裁判所の所在地を管轄する連邦地方裁判所に、移送申立書(Notice of Removal)を提出することによって開始されます。この申立ては、原則として、被告が訴状の送達を受けてから30日以内に行わなければなりません。
1.4 人的管轄権(Personal Jurisdiction)
事物管轄権が「何を」審理できるかという問題であるのに対し、人的管轄権は「誰を」法廷に引き出し、その者に対して拘束力のある判決を下すことができるか、という問題です。これは、被告の財産を差し押さえる、あるいは特定の行為を命じるといった判決の実効性を担保する上で不可欠の要件であり、その根底には、憲法上のデュー・プロセスが保障する個人の自由と公正さへの配慮があります。
(1)伝統的な管轄権理論:「Pennoyer v. Neff」事件と物理的支配
人的管轄権に関する現代的理論の出発点であり、比較対象として常に参照されるのが、Pennoyer v. Neff(1877年) で最高裁判所が確立した伝統的な管轄権理論です。この理論の核心は、各州がその領域内において絶対的な主権を持つという考え方にあり、裁判所の人的管轄権は、州の領域内における物理的な支配力に基礎を置いていました。
この理論の下では、裁判所が被告に対して人的管轄権(in personam jurisdiction)を行使するためには、原則として、被告が州の領域内に物理的に存在(presence)し、その場で訴状の送達を受ける必要がありました。たとえ一時的な滞在であっても、州内で送達を受ければ、その被告は州の裁判権に服することになりました。
また、被告本人が州内にいなくても、その財産が州内に存在すれば、裁判所はその財産に対する管轄権(in rem jurisdiction・quasi-in-rem jurisdiction)を行使できました。この場合、判決の効力は、差し押さえられた財産の価額を限度とするものに限定されました。Pennoyer事件では、訴訟開始時に被告の財産が差し押さえられていなかったことが、管轄権が否定される決定的な理由となりました。
この物理的支配を基礎とする厳格な領域主権の考え方は、交通や通信が未発達であった19世紀においては一定の合理性を有していました。しかし、経済活動が州境を越えて活発化し、企業が全国的に事業を展開するようになると、この理論は現実との間に深刻な乖離を生じさせることになります。州内で広範な事業活動を行いながら、訴状の送達を避けるために役員が州外に留まる法人や、自動車で他州に入り込み事故を起こしてすぐに立ち去る個人に対して、有効な裁判権を及ぼすことが困難になったのです。このような社会経済の変化に対応するため、裁判所は「同意(consent)」や「住居(domicile)」といった概念を援用し、物理的プレゼンスの原則に様々な例外を設けることで、管轄権の範囲を徐々に拡大させていきました。
(2)現代的管轄権論:「International Shoe Co.」事件とミニマム・コンタクト理論
伝統的な管轄権理論の抜本的な転換点となったのが、International Shoe Co. v. Washington(1945年) です。この画期的な判決において、最高裁判所は、人的管轄権の基礎を、物理的な支配力という硬直的な概念から、デュー・プロセスの理念に根差した、より柔軟な基準へと移行させました。
最高裁が示した新しい基準は、州が州外の被告に対して人的管轄権を行使するためには、被告が「ミニマム・コンタクト(最小限の接触)」 を有し、かつ、その管轄権の行使が「公正な手続と実質的正義(traditional notions of fair play and substantial justice)」 の伝統的な観念に反しないこと、というものです。
この「ミニマム・コンタクト」理論は、管轄権の有無を、被告の物理的な所在という単一の要素で判断するのではなく、被告、州、そして訴訟という三者間の関連性を総合的に評価することを要求します。この評価にあたり、裁判所は、被告が州法によって提供される利益や保護を「意図的に享受(purposefully avails itself)」 したかどうかを特に重視します。例えば、州内で継続的に商品を販売する、州の住民を対象に広告を出す、あるいは州法に準拠した契約を締結するといった行為は、被告が意図的に州との関連性を形成した証となります。
International Shoe Co.判決以降の判例法理の積み重ねにより、人的管轄権は、「特定管轄権(Specific Jurisdiction)」 と「一般管轄権(General Jurisdiction)」 という2つの類型に整理されるようになりました。
特定管轄権は、被告の州との「接触」が、訴訟の原因となった紛争そのものから「生じている(arise out of or relate to)」場合に成立します。例えば、カリフォルニア州の住民が、アリゾナ州に本社を置く企業からオンラインで商品を購入し、その商品に欠陥があって負傷した場合、カリフォルニア州の裁判所は、その特定の欠陥商品に関する訴訟について、アリゾナの企業に対して特定管轄権を行使できる可能性が高いと言えます。たとえその企業がカリフォルニア州との接触がその一度きりの取引だけであっても、訴訟がその接触自体から生じているからです。
一方、一般管轄権は、被告の州との「接触」が、訴訟の原因となった紛争とは直接関係がない場合でも、その接触が非常に「継続的かつ体系的(continuous and systematic)」 であり、被告が実質的にその州を「本拠地(home)」 としているとみなせる場合に成立します。この管轄権が認められると、被告は、その州で生じた紛争であるか否かを問わず、あらゆる訴訟についてその州の裁判権に服することになります。近年の最高裁判例、特にGoodyear Dunlop Tires Operations, S. A. v. Brown(2011年) やDaimler AG v. Bauman(2014年) は、この一般的管轄権の成立要件を極めて厳格に解釈する傾向にあります。個人であればその「住居(domicile)」、法人であればその「設立準拠法州」または「主たる事業所」のいずれかが「本拠地」とみなされるのが通常であり、それ以外の州で一般管轄権が認められるのは、極めて例外的な場合に限られます。
(3)ロングアーム法(Long-Arm Statutes)
インターナショナル・シュー判決が示した憲法上の許容範囲内で、各州は、州外の被告に対して人的管轄権を及ぼすための具体的な法的根拠として、「ロングアーム法(Long-Arm Statute)」 と呼ばれる法律を制定しています。
原告が州外の被告に対して訴訟を提起する場合、(1)州のロングアーム法がその被告に対する管轄権行使を許容しており、かつ、(2)その管轄権の行使が憲法上のデュー・プロセスの要請(ミニマム・コンタクト)を満たしている、という2つのステップをクリアする必要があります。
ロングアーム法には、州内で発生した不法行為、州内で締結・履行された契約、州内の不動産の所有など、管轄権の根拠となる被告の行為を具体的に列挙するタイプと、憲法が許容する最大限の範囲まで管轄権を及ぼすことを包括的に定めるタイプの2種類があります。
(4)インターネット時代の人的管轄権
インターネットの普及は、人的管轄権の分析に新たな難問を投げかけています。ウェブサイトを通じて全国的、全世界的に事業を展開する企業に対して、どの州の裁判所が管轄権を行使できるのでしょうか。この問題について、多くの裁判所は、ウェブサイトの性質を「双方向性(interactivity)」 の度合いに応じて分類するアプローチ(いわゆる「ジッポ・テスト」)を参考にしています。単に情報を掲載しているだけの受動的なウェブサイトであれば管轄権は否定されやすく、逆に、サイトを通じて顧客と積極的に情報のやり取りをしたり、契約を締結したりする双方向性の高いウェブサイトであれば、管轄権は肯定されやすい、という考え方です。しかし、これも絶対的な基準ではなく、最終的には、被告がそのウェブサイトを通じて、特定の州を意図的にターゲットとし、その州の住民と取引関係に入ろうとしたかどうかが、ミニマム・コンタクトの有無を判断する上で重要な要素となります。
1.5 準拠法の決定:エリー原則(Erie Doctrine)
連邦裁判所が多様性管轄権に基づいて事件を審理する場合、裁判所は手続については連邦法(連邦民事訴訟規則など)を適用しますが、実体法については、いずれかの州法を適用しなければなりません。では、どの州の、どのような法を適用すべきなのでしょうか。連邦裁判所における準拠法選択のルールを支配する基本原則が、エリー原則(Erie Doctrine) です。
(1)「Swift v. Tyson」事件から「Erie Railroad Co. v. Tompkins」事件へ
この原則の歴史は、二つの画期的な最高裁判決によって画されています。1842年のスウィフト対タイソン事件(Swift v. Tyson) 判決から約100年間、連邦裁判所は、州の制定法が存在しない商取引などの「一般的(general)」な問題については、特定の州の判例法に拘束されず、連邦裁判所が独自に形成する「連邦一般コモンロー(federal general common law)」 を適用することができる、とされていました。これは、州ごとに異なる判例法ではなく、統一的な連邦のルールを適用することで、商取引の予測可能性を高めようという政策的配慮に基づくものでした。
しかし、この運用は深刻な問題を生みました。第一に、州裁判所が連邦裁判所の判断に従わなかったため、同じ州内にある州裁判所と連邦裁判所で、同じ取引について異なる法が適用され、異なる判決が下されるという事態が頻発しました。第二に、この不統一性を利用した「フォーラム・ショッピング」 が横行しました。当事者は、自分に有利な法を適用してくれる裁判所を求めて、州裁判所と連邦裁判所を戦略的に使い分けたのです。特に、Black & White Taxicab & Transfer Co. v. Brown & Yellow Taxicab & Transfer Co.(1928年) では、原告が、自社に不利な州法判例の適用を回避するためだけに、本社を他州に移して多様性を創出し、連邦裁判所に提訴するという露骨なフォーラム・ショッピングが最高裁によって容認され、大きな批判を浴びました。
このような状況を抜本的に覆したのが、1938年のErie Railroad Co. v. Tompkins判決です。この判決で最高裁判所は、Swift判決を覆し、「連邦一般コモンローは存在しない」と宣言しました。そして、連邦裁判所は、多様性事件において、連邦憲法または連邦制定法が規律する事項を除き、州の制定法のみならず、州の判例法(コモンロー)にも従わなければならない、と判示したのです。
このエリー原則の根拠は三つあります。第一に、Swift判決の基礎となった1789年裁判所法34条(Rules of Decision Act)の解釈が誤っていたこと。第二に、Swift判決がもたらしたフォーラム・ショッピングと、州内における法の不統一という弊害。そして最も重要な第三の根拠は、連邦裁判所が州の権限に属する事項について独自のコモンローを形成することは、合衆国憲法に違反する、という点です。連邦政府は憲法によって与えられた権限しか持たず、州のコモンローが規律すべき領域に連邦裁判所が介入することは、連邦主義の原則と権力分立に反する、とされたのです。
(2)手続法と実体法の区別
エリー原則は、連邦裁判所が「実体法」について州法に従うことを要求します。では、「手続法」についてはどうなるのでしょうか。この「実体」と「手続」の区別は、エリー原則を適用する上で最も難解な問題の一つであり、その後の判例法理の変遷の中心となってきました。
エリー判決直後のGuaranty Trust Co. v. York(1945年) で、最高裁判所は「Outcome-Determinative Test」 という基準を打ち立てました。これは、あるルールが「実体的」か「手続的」かという形式的な分類ではなく、もし連邦裁判所が州のルールに従わなかった場合に、訴訟の「結果(outcome)」が州裁判所で訴訟を行った場合と実質的に異なることになるのであれば、そのルールは「実体的」なものとみなし、連邦裁判所は州のルールに従わなければならない、という考え方です。このテストは、エリー原則の目的であるフォーラム・ショッピングの防止と、州内における法の適用の公平性を確保しようとするものでした。しかし、このテストを厳格に適用すれば、些細な手続ルールの違いでも結果に影響を与えうるため、連邦民事訴訟規則のほとんどが州のルールに取って代わられてしまう、という批判を招きました。
次に、Byrd v. Blue Ridge Rural Electric Cooperative, Inc.(1958年) で、最高裁はOutcome-Determinative Testを修正し、「利益衡量テスト(Balancing Test)」 を導入しました。これは、州のルールが訴訟の結果に影響を与える可能性があるとしても、それに対抗する重要な連邦の政策(countervailing federal interests)が存在する場合には、両者の利益を衡量し、連邦の利益が優越する場合には連邦のルールを適用できる、というものです。Byrd事件では、事実認定を裁判官が行うか陪審が行うかという州のルールに対し、陪審による事実認定を保障するという連邦の強い政策(憲法修正7条の精神)が優越するとされました。
そして、この問題を最終的に整理したのが、Hanna v. Plumer(1965年) です。この判決は、問題となっている事項が、有効な連邦民事訴訟規則によって直接規律されているか否かで、分析の枠組みを二分しました。
もし、連邦民事訴訟規則が直接適用される場面であれば、問われるべきは、その規則が、議会から最高裁に規則制定権を委任した法律(Rules Enabling Act)の範囲内(すなわち、当事者の「実体的権利を剥奪、拡大、または変更」しない)で制定された有効なものか、という点です。そして、連邦民事訴訟規則は、この要件を満たす限り、たとえ州のルールと抵触し、訴訟の結果に影響を与えるとしても、連邦裁判所において適用されます。
一方、連邦民事訴訟規則が直接規律していない場面(判例法理や、規則の射程外の問題)であれば、エリー原則の本来の目的に立ち返り、「twin aims of Erie」、すなわち①フォーラム・ショッピングの助長の回避、②法の不公平な適用の回避、という観点から、州のルールを適用すべきか否かを判断します。
このHanna判決による分析枠組みは、今日のエリー原則の解釈における基本的な指針となっています。
(3)連邦コモンローの存在
エリー判決は「連邦“一般”コモンロー」の存在を否定しましたが、「連邦コモンロー」そのものを完全に否定したわけではありません。合衆国憲法や連邦法によって連邦政府に与えられた権限が及ぶ、連邦の重要な利益が関わる特定の限定された分野においては、連邦裁判所が判例を通じて独自の法(連邦コモンロー)を形成することが認められています。
連邦コモンローが適用される典型的な分野としては、①合衆国政府が当事者となる契約や不法行為、②州と州の間の紛争(州境や水利権など)、③米国の国際関係に関わる問題、④連邦法の条文に隙間がありそれを解釈で補う必要がある場合、などが挙げられます。これらの分野では、州法を適用するのではなく、全国的に統一されたルールを適用する必要性が高いと判断されるのです。