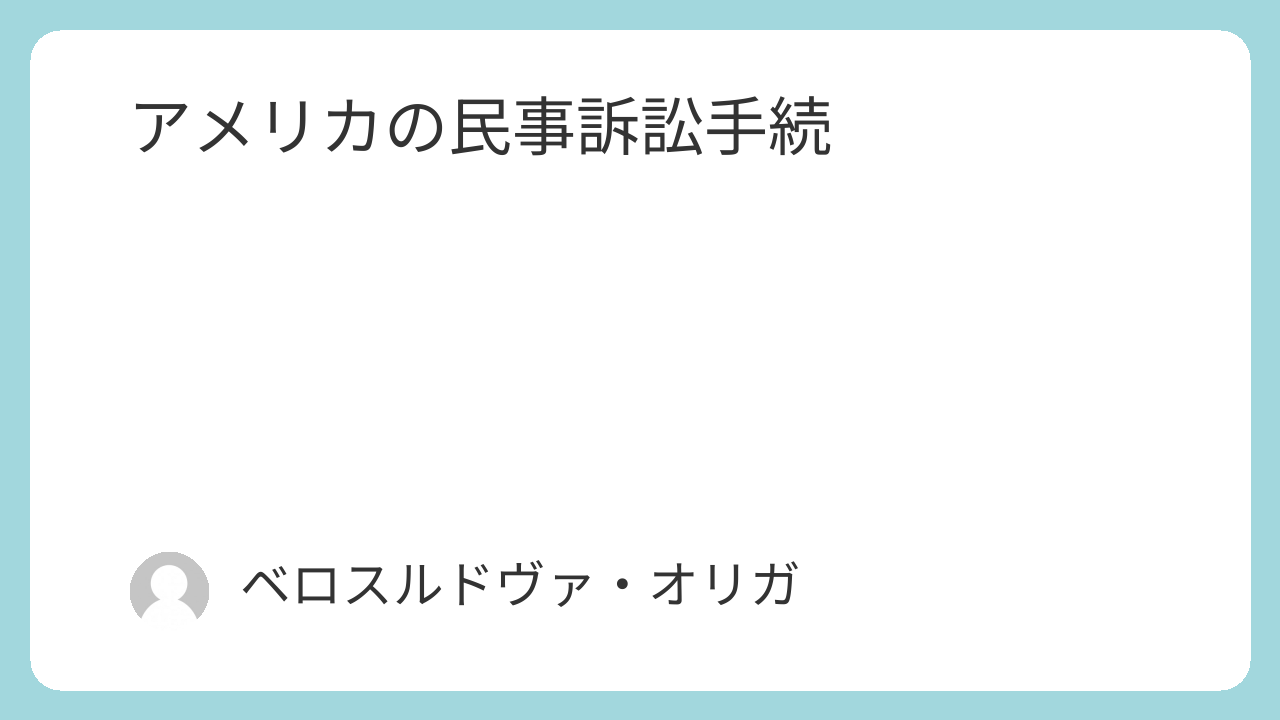アメリカの民事訴訟制度は、思想的背景から具体的な手続の運用に至るまで、日本の制度とは大きく異なっています。コモンローの伝統に根差したその複雑な構造は、難解で、近寄りがたいものに映るかもしれません。本稿は、訴訟の開始から判決の執行に至るまで、訴訟の全プロセスを時系列に沿って体系的に解説し、難解な専門用語や制度的背景を丁寧に紐解くことで、アメリカの民事訴訟手続の全体像を理解できるようになることを目的としています。
アメリカの民事訴訟を理解する上で、まず押さえるべき最も根源的な思想が「対審構造(Adversarial System)」、すなわち「当事者主義」です。アメリカの法廷において、裁判官は中立な審判役に徹し、訴訟の進行や証拠の提出、主張の展開といった活動の主導権は、完全に両当事者の弁護士に委ねられています。
この当事者主義を支えるもう一つの柱が、「デュー・プロセス(Due Process of Law)」、すなわち「公正な手続の保障」という憲法上の大原則です。これは、何人も正当な法の手続によらなければ、生命、自由または財産を奪われることはない、という考え方です。民事訴訟の文脈においては、主に「手続的デュー・プロセス」が問題となり、具体的には、訴えられた者に対して、訴訟が提起されたことを知らせる「告知(Notice)」と、自らの主張を述べる「聴聞の機会(Opportunity to Be Heard)」が十分に保障されなければならない、とされています。この原則は、裁判所が当事者に対して管轄権を行使できるかという根源的な問題から、証拠開示(ディスカバリー)の範囲、判決の執行に至るまで、あらゆる手続の妥当性を判断する際の究極的な基準となります。
アメリカでは、手続法は単なる「ルール」以上の意味を持ちます。それは、当事者の実体的な権利義務を具体化し、実現するための不可欠な器であり、時として手続そのものが実体的な権利と不可分に結びついています。例えば、どの裁判所で訴訟を提起すべきかという「裁判管轄権」の問題は、単なる地理的な利便性の問題にとどまらず、どの州の法律が適用されるか、ひいては勝敗そのものを決定づける戦略的な第一歩です。また、アメリカ訴訟の最大の特徴とも言える広範かつ強力な「ディスカバリー(証拠開示手続)」は、審理(トライアル)の前に当事者双方が持つ証拠のほとんどを開示させ、事件の真相を白日の下に晒すことを可能にします。このディスカバリーをいかに制するかが、訴訟の行方を大きく左右すると言っても過言ではありません。
第1部 訴訟の開始
第2部 審理の準備
第6章 審理前協議(Pretrial Conference)