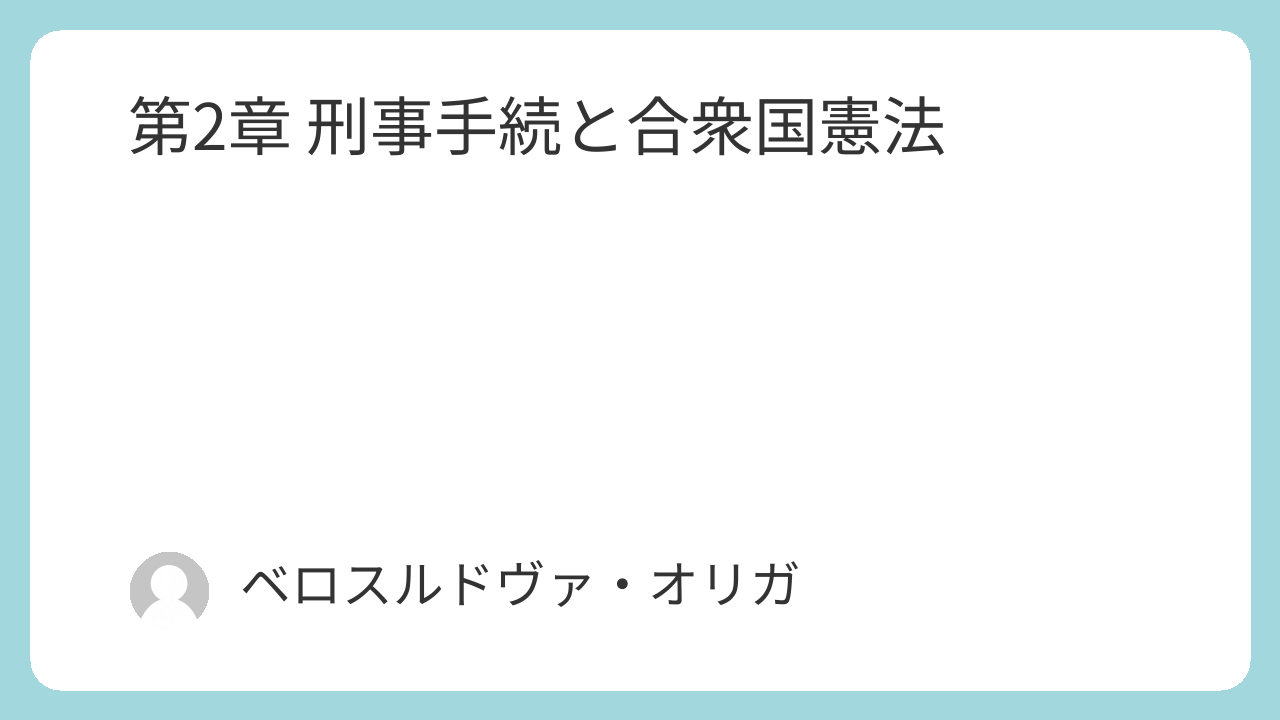アメリカの刑事手続は、合衆国憲法、特にその修正条項である「権利章典(Bill of Rights)」によって深く形作られています。しかし、今日では当たり前とされるこれらの憲法上の保障が、当初から各州の刑事手続に適用されていたわけではありません。本章では、当初は連邦政府のみを拘束するものであった権利章典が、修正14条の「デュー・プロセス条項(Due Process Clause)」を通じて、いかにして州政府にも適用されるようになったのか、その経緯について解説します。この歴史的・法理的変遷を理解することは、現代アメリカ刑事司法の根幹をなす連邦と州の二元的な権利保障構造を把握する上で不可欠です。
1. 権利章典(Bill of Rights)と修正14条
合衆国憲法が1789年に発効した当初、そこには個人の権利を具体的に保障する条項がほとんど含まれていませんでした。これに対する強い懸念から、1791年に最初の10カ条の修正、すなわち「権利章典」が追加されました。この中には、不合理な捜索・差押えの禁止(修正4条)、自己負罪拒否特権や二重の危険の禁止(修正5条)、迅速な公開裁判や弁護人依頼権(修正6条)など、刑事手続に関する極めて重要な保障が含まれています。
しかし、これらの権利章典の保障は、誰の権力行使を制約するものなのでしょうか。この根本的な問いに対し、合衆国最高裁判所は、Barron v. City of Baltimore(1833年)判決において、「権利章典は連邦政府の権力行使のみを制約し、州政府には適用されない」という判断を下しました。これにより、19世紀半ばまで、各州の刑事手続は、それぞれの州憲法や州法によって規律されるのみで、連邦憲法による直接的な制約を受けることはありませんでした。
この状況を劇的に変化させるきっかけとなったのが、南北戦争後の1868年に批准された修正14条です。この修正条項は、次のように規定しています。
「いかなる州も、合衆国市民の特権または免除を縮減する法律を制定し、または執行してはならない。また、いかなる州も、法の適正手続(due process of law)によらずに、何人からも生命、自由または財産を奪ってはならない。また、その管轄内にある何人に対しても、法の平等な保護を否定してはならない。」
このうち、特に「デュー・プロセス条項」が、権利章典の保障を州に及ぼすための鍵となりました。問題は、この条項が具体的に何を意味し、権利章典の各条項とどう関係するのかでした。
2. デュー・プロセス(適正手続)と州への適用
修正14条の成立後、デュー・プロセス条項が権利章典の保障を州に「編入(incorporate)」するものであるか否かをめぐり、長きにわたる法廷闘争と学術的論争が繰り広げられました。
当初、最高裁判所は編入に対して消極的な姿勢を取りました。19世紀末から20世紀初頭にかけての判例では、デュー・プロセス条項は、権利章典の各条項をそのまま州に適用するものではなく、州の手続が「fundamental fairness」の原則に反していないかを個別に判断する基準であるとされました。このアプローチの下では、州の手続が連邦の手続と異なっていても、それが「秩序ある自由(ordered liberty)」の概念に反するような、文明社会の良心に衝撃を与えるものでない限り、合憲とされました。例えば、Palko v. Connecticut(1937年)判決では、修正5条の二重の危険の禁止は、州に適用されるほど「基本的」な権利ではないと判断されました。
この「fundamental fairness」アプローチは、柔軟性がある一方で、予測可能性に欠け、裁判官の主観に左右されやすいという批判を免れませんでした。何が「fundamental」で、何がそうでないかの基準が曖昧であったため、被告人の権利保障が不安定な状態に置かれたのです。
3. 選択的編入(Selective Incorporation)理論の確立
こうした状況の中、最高裁判所は20世紀半ばから、より明確な基準を求めて編入(incorporate)理論へと舵を切り始めます。この過程で、2つの主要な理論が対立しました。
1つは、ヒューゴ・ブラック判事が強力に主張した「全面編入(Total Incorporation)」論です。これは、修正14条の起草者たちは、権利章典の全ての条項をそのまま州に適用する意図を持っていたとする見解です。この理論は、解釈の明確さと最大限の権利保障を利点としますが、州の独立性を大きく損なうとして、少数意見に留まりました。
最終的に最高裁判所が採用し、今日に至るまで支配的な法理となっているのが「選択的編入(Selective Incorporation)」理論です。これは、「fundamental fairness」アプローチと「全面編入」論の中間に位置する理論です。選択的編入論によれば、権利章典に含まれる権利のうち、「アングロ・アメリカンの法体系における秩序ある自由のスキームに基礎を置く」、すなわちアメリカの司法制度にとって「根本的(fundamental)」と見なされる権利が、それぞれ選択的にデュー・プロセス条項に編入され、州に適用されます。そして、一度編入された権利は、連邦政府に適用されるのと全く同じ基準と内容で、州政府にも適用されます(いわゆる「Jot-for-Jot」の原則)。
1960年代のウォーレン・コート時代に、この選択的編入が精力的に進められました。
- 違法収集証拠排除法則(Mapp v. Ohio, 1961年、修正4条)
- 弁護人依頼権(Gideon v. Wainwright, 1963年、修正6条)
- 自己負罪拒否特権(Malloy v. Hogan, 1964年、修正5条)
- 対面権(Pointer v. Texas, 1965年、修正6条)
- 陪審裁判を受ける権利(Duncan v. Louisiana, 1968年、修正6条)
など、刑事手続に関する権利章典の主要な保障が、次々と州に適用されると判断されました。今日では、刑事手続に関連する権利章典の条項のうち、修正5条の大陪審による起訴を受ける権利と修正8条の過大な保釈金の禁止を除き、ほぼ全ての条項が州に編入されています。この選択的編入理論の確立により、アメリカ全土で適用される刑事手続の「憲法上の最低基準」が形成されたのです。
4. デュー・プロセスの独立した内容
デュー・プロセス条項の役割は、権利章典の条項を組み込むことだけに留まりません。この条項は、編入された権利とは別に、それ自体が独立した内容を持つ「独立したデュー・プロセス(Free-standing Due Process)」として機能します。これは、たとえ権利章典の特定の条項に違反していなくても、政府の行為が根本的な公正の観念に反する場合には、デュー・プロセス違反となり得ることを意味します。
この独立したデュー・プロセスは、主に2つの側面に分けられます。
- 手続的デュー・プロセス(Procedural Due Process): これは、政府が個人の生命・自由・財産を奪う際に、公正な手続を踏むことを要求します。刑事手続の文脈では、例えば、検察官が意図的に虚偽の証拠を使用することの禁止(Mooney v. Holohan, 1935年)や、犯罪の全ての構成要件を「合理的な疑いを超えて(beyond a reasonable doubt)」証明する立証責任を検察官に課すこと(In re Winship, 1970年)などが、手続的デュー・プロセスに根差すものとされています。これらは、権利章典に明文の規定はありませんが、公正な裁判に不可欠な要素として憲法上保障されています。
- 実体的デュー・プロセス(Substantive Due Process): これは、手続の公正さとは無関係に、政府の行為の「内容(substance)」そのものが、あまりに不合理で恣意的であるために許されないとする法理です。刑事法の分野では、例えば、法律の文言が不明確すぎて通常の人間が何を禁止されているのか理解できないような「漠然性の故に無効(Void for Vagueness)」の法理が、この実体的デュー・プロセスの一環として理解されています。
5. 憲法解釈の指針
最高裁判所が、ある権利が「根本的」であるか否かを判断したりデュー・プロセスの内容を定めたりする際には、特定の解釈手法に依拠します。主な指針としては、歴史(憲法制定者や修正条項起草者の意図、コモンロー上の伝統)、政策(その判断が社会や司法制度に与える実践的な影響)、判例(stare decisisの原則に基づき、過去の判決を尊重する姿勢)が挙げられます。これらの要素を総合的に勘案することで、憲法の条文は、時代や社会の変化に対応しながら解釈され、適用されていくのです。
刑事手続の憲法化は、アメリカの連邦主義と個人の権利保障の関係を根本から変革しました。これにより、州の刑事司法に対する連邦裁判所の監督権限が確立され、全米の被告人に共通の憲法上の保護が与えられることになったのです。