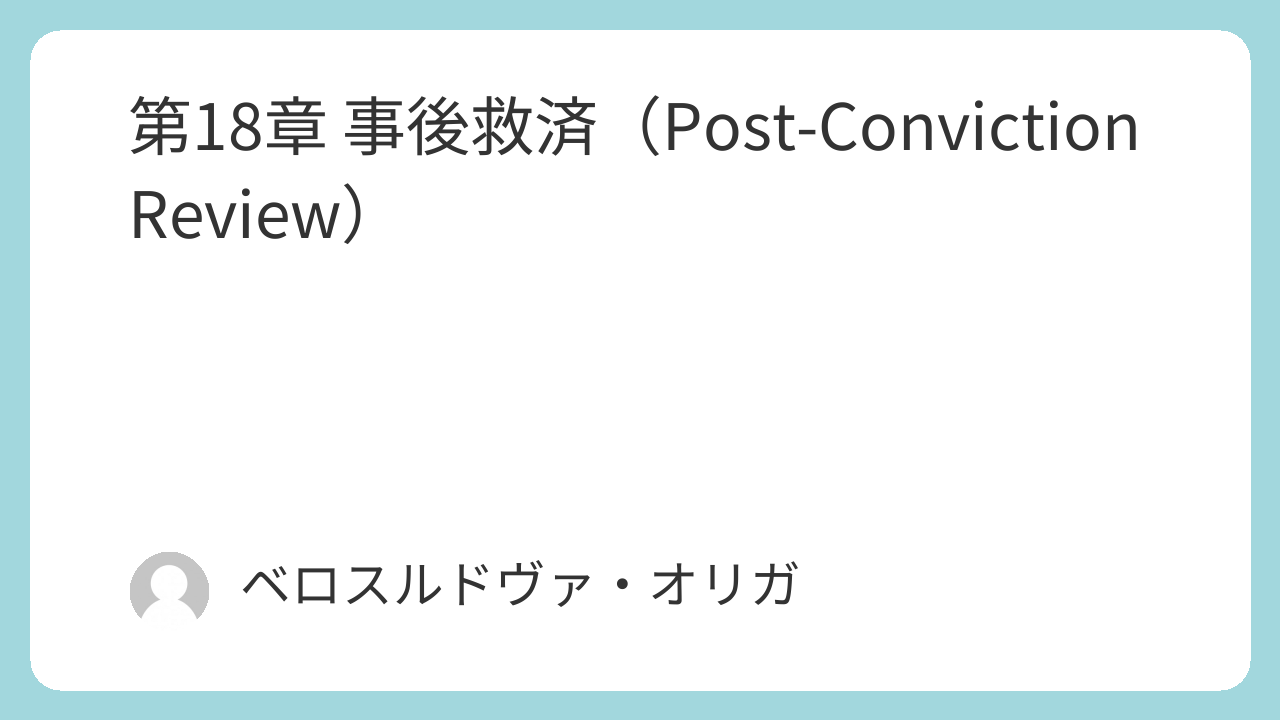被告人が有罪判決を受け、第一審から最上級裁判所に至るまでの直接の上訴(direct appeal)の道をすべて尽くしたとしても、それで法的な争いの可能性が完全に閉ざされるわけではありません。アメリカの司法制度は、司法判断の終結性(finality)を重んじる一方で、根本的な憲法上の権利侵害や重大な不正義を是正するための、最後のセーフティネットを用意しています。それが、事後救済(Post-Conviction Review)又はCollateral Attackと呼ばれる一連の特別な手続です。本章では、この通常の上訴とは異なる救済制度の概要を説明し、その中核をなす連邦人身保護令状(Federal Habeas Corpus)の機能と、その利用に課せられた厳しい手続上の制約について解説します。
1. Collateral Attackの概要
Collateral Attackとは、有罪判決を下した元の刑事手続を直接争うのではなく、その判決に基づく身柄拘束の合法性を、新たな独立した民事訴訟として間接的に攻撃する手続です。これは、直接の上訴とはいくつかの点で根本的に異なります。
- 争点: 上訴は、主に下級審の審理記録に現れた法律上の過誤を審査の対象とします。一方、Collateral Attackでは、審理記録には現れないような問題、例えば、公判廷外での弁護人の非実効的な活動、検察官による無罪証拠の隠匿、新たに発見された無罪を証明する証拠などを主張することができます。
- 範囲: 上訴に比べ、Collateral Attackで主張できる争点の範囲は格段に狭いです。通常、管轄権の欠如や、根本的な憲法上の権利侵害といった、ごく重大な欠陥に限定されます。
- 手続: 被告人(請願者(petitioner))は、自らの身柄を拘束している者(通常は刑務所長)を相手方(respondent)として、新たな訴訟を提起します。
2. 連邦人身保護令状(Federal Habeas Corpus)
コラテラル・アタックのための最も重要かつ歴史ある手段が、人身保護令状(Writ of Habeas Corpus)です。ラテン語で「汝、身体を有せよ(you have the body)」を意味するこの令状は、「偉大なる令状(The Great Writ)」とも称され、政府による不法な身柄拘束から個人を保護するための、コモンロー上の最も基本的な権利として尊重されてきました。
特に重要なのが、州の裁判所で有罪判決を受け、身柄を拘束されている者が、その拘束が合衆国憲法に違反すると主張して、連邦裁判所に救済を求める連邦人身保護令状です。これにより、連邦裁判所は、州の刑事司法手続が連邦憲法の定める基準を遵守しているかを監督するという、連邦主義の下で極めて重要な役割を担っています。
3. 機能と手続的制約
連邦人身保護令状は強力な救済手段ですが、州の司法判断に対する敬意(comity)と、刑事裁判の終結性を確保する必要から、その利用には数多くの厳しい手続上のハードルが設けられています。特に、1996年に制定された反テロリズム及び効果的死刑法(Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, AEDPA)は、これらの制約を大幅に強化しました。
(1) 州における救済手続の完了(Exhaustion of State Remedies)
州の受刑者が連邦人身保護令状を申し立てるための絶対的な前提条件として、まず、主張しようとする連邦憲法上の問題を、州の裁判制度を通じて完全に尽くしていることが要求されます。これは、州の直接上訴から、州が定める事後救済手続に至るまで、利用可能な全ての機会を用いて州裁判所に是正の機会を与えなければならないことを意味します。連邦裁判所が介入する前に、まず州自身にその誤りを正す機会を与えるという、連邦と州の敬意の原則に基づく要件です。
(2) 手続的懈怠(Procedural Default)
請願者が、州の定める手続規則(例えば、異議申立の期限や上訴期間)に従わなかったために、州裁判所でその請求が実体判断に至らなかった場合、その請求は「手続的に懈怠した(procedurally defaulted)」ものと見なされます。この場合、連邦裁判所も、原則としてその請求の実体審理を拒否します。この手続的懈怠の壁を乗り越えるためには、請願者は以下のいずれかを証明しなければなりません。
- 懈怠に「正当な理由(cause)」があり、かつ、憲法違反によって「現実の不利益(actual prejudice)」を被ったこと。
- この請求を審理しないことが、「根本的な司法の誤謬(fundamental miscarriage of justice)」、つまり、無実(factually innocent)の人間を処罰し続ける結果となること。
(3) 連邦裁判所による審査基準の厳格化(AEDPA)
たとえ請求が手続的に適切に提出されたとしても、AEDPAは、連邦裁判所が州裁判所の判断を覆すための基準を極めて厳格なものにしました。連邦裁判所が人身保護令状による救済を与えることができるのは、州裁判所の判断が、以下のいずれかに該当する場合に限られます。
- 「明確に確立された連邦法(clearly established Federal law)」、つまり、合衆国最高裁判所の判例に反する判断であった場合。
- その判例を「不合理に適用した(involved an unreasonable application of)」ものである場合。
ここでいう「不合理」とは、単に誤っているというだけでは不十分であり、いかなる公正な法律家もそのような結論には至らないであろうというほど、客観的に見て不合理でなければなりません。これは州裁判所の判断に対する最大限の敬譲を示すものであり、連邦人身保護審査のハードルを著しく高くしています。
(4) 再度の申立ての制限(Successive Petitions)
AEDPAはまた、一度連邦人身保護令状の申立てが棄却された後に、二度目以降の申立て(second or successive petition)を行うことを厳しく制限しています。再度の申立てを行うためには、まず連邦上訴裁判所から許可を得なければならず、その許可は、新たに発見された無罪を証明する強力な証拠が存在する場合など、極めて例外的な状況でしか与えられません。