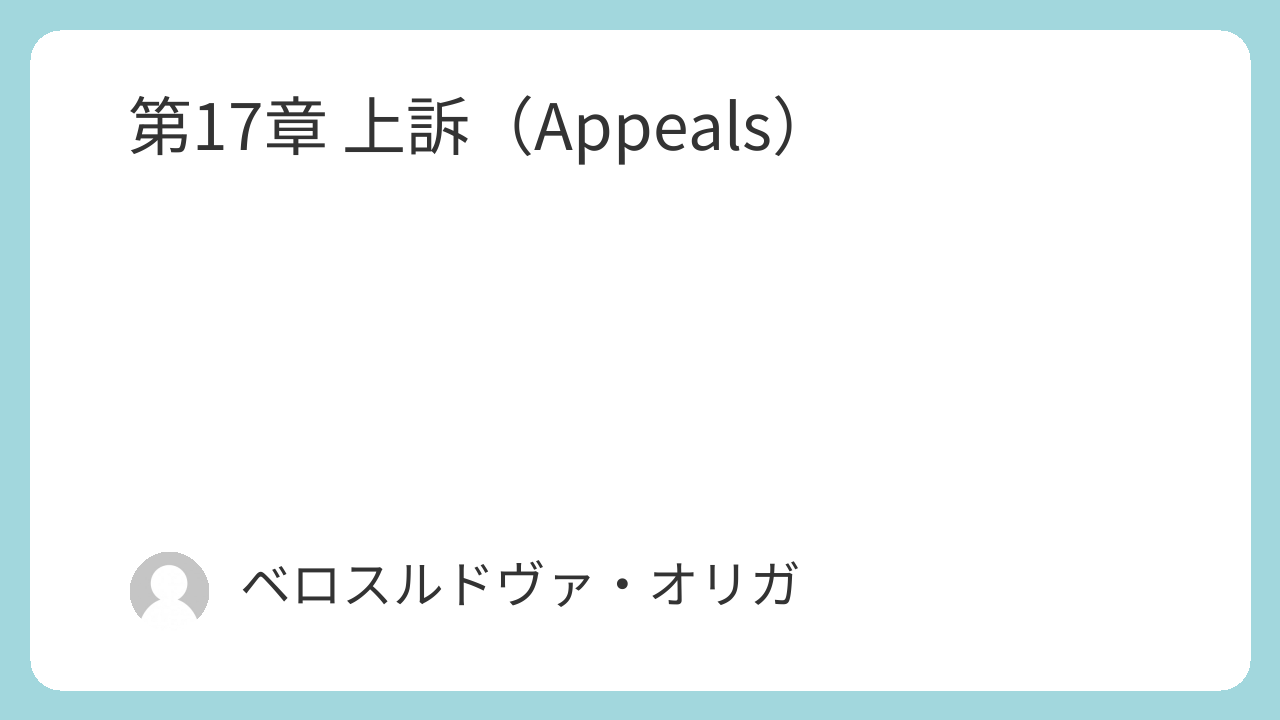刑事裁判は、公判での評決や量刑宣告で完全に終結するわけではありません。アメリカの司法制度は、下級審(trial court)の判断に過誤があった可能性を想定し、上級審(appellate court)による審査の機会を設けています。これが上訴(Appeal)です。有罪判決を受けた被告人は、公判手続や量刑判断において法的な過誤があったと主張し、判決の取消しや再審理を求めることができます。しかし、上訴審は事件を最初からやり直す場ではありません。そこには、下級審の判断を尊重し、司法の終結性を確保するという要請との間で、厳格な審査のルールが存在します。本章では、この上訴制度の構造、上訴審が用いる審査の範囲と基準、そして下級審の過誤が判決に与えた影響を評価するための二大原則、「無害な過誤の法理」と「明白な過誤の法理」について解説します。
1. 上訴制度の構造
合衆国憲法は、刑事被告人に上訴する絶対的な権利を保障していません。しかし、連邦および全ての州は、法律によって、有罪判決を受けた被告人に、少なくとも一度は上訴する権利(first appeal as of right)を保障しています。この最初の権利に基づく上訴は、通常、中間上訴裁判所(Intermediate Appellate Court)に対して行われます。中間上訴裁判所の判断に不服がある当事者は、さらにその法域の最高裁判所(通常は州最高裁判所または合衆国最高裁判所)に対し、裁量による上訴(discretionary review)を求めることができます。
上訴審の役割は、事実を再認定することではありません。陪審や裁判官による事実認定は、原則として尊重されます。上訴審の主な任務は、下級審の手続記録(公判の速記録、提出された証拠物など)を精査し、そこに法律上の過誤(errors of law)がなかったかを審査することです。
2. 審査の範囲と基準(Standard of Review)
上訴審が下級審の判断を審査する際には、問題となっている判断の性質に応じて、異なる審査基準(Standard of Review)を用います。
- 法律問題の審査(De Novo Review): 下級審における法律の解釈や適用に関する問題(例えば、特定の法律の合憲性、陪審説示の正確さ、証拠法則の解釈など)については、上訴審は「De Novo」、すなわち「新たに(from the new)」判断を行います。これは、上訴審が自ら法律問題を完全に再検討し、独自の結論を導き出すことを意味します。
- 事実認定の審査(Clearly Erroneous Standard): 裁判官裁判における裁判官による事実認定については、その認定が「明白に誤っている(clearly erroneous)」場合にのみ、それを覆すことができます。これは、実際に証人の態度や口調を直接見聞した事実審の裁判官の判断を尊重する趣旨です。
- 裁量判断の審査(Abuse of Discretion Standard): 下級審の裁判官に裁量が与えられている事項(例えば、証拠の許容性に関する判断、公判の進行管理、量刑判断など)については、上訴審は、その裁量権の行使が「裁量権の濫用(abuse of discretion)」にあたるか否かを審査します。裁判官の判断が不合理または恣意的でない限り、覆されることは稀です。
3. 無害な過誤の法理(Harmless Error Doctrine)
上訴審が下級審の手続に法的な過誤を発見したとしても、それだけで直ちに有罪判決が覆されるわけではありません。刑事裁判は人間が行うプロセスであり、完璧な裁判はあり得ないからです。もし、判決の結果に何ら影響を与えなかったような些細な誤りのために、全ての有罪判決を取り消さなければならないとすれば、司法制度は機能不全に陥ってしまいます。この問題意識から生まれたのが、「無害な過誤の法理(Harmless Error Doctrine)」です。この法理は、発見された過誤が、被告人の実質的な権利に影響を与えず、判決の結果に貢献しなかった「無害な」ものである場合には、有罪判決を維持することを認めます。
過誤が「無害」であったか否かを判断する基準は、その過誤が憲法上のものか否かによって異なります。
(1) 憲法上の過誤(Constitutional Error)
下級審の過誤が、被告人の憲法上の権利(例えば、違法収集証拠の不当な採用、対面権の侵害など)を侵害するものであった場合、その過誤は極めて深刻なものと見なされます。この場合、Chapman v. California(1967年)判決で確立された厳格な基準が適用されます。すなわち、有罪判決を維持するためには、検察官(政府)側が、その憲法上の過誤が「合理的な疑いを超えて無害であった(harmless beyond a reasonable doubt)」ことを証明しなければなりません。これは非常に高いハードルであり、検察官側は、その過誤がなくても、陪審が同じ有罪評決に達したであろうことを、事実上議論の余地なく示さなければなりません。
(2) 憲法以外に関する過誤(Non-Constitutional Error)
過誤が、連邦刑事訴訟規則や証拠法則の違反といった、憲法上の問題に至らないものであった場合、より緩やかな基準が適用されます。Kotteakos v. United States(1946年)で示されたこの基準によれば、過誤は、それが「評決に対して実質的かつ有害な効果または影響を及ぼした(had a substantial and injurious effect or influence in determining the jury’s verdict)」のでない限り、無害と見なされます。この基準の下では、過誤の有害性を証明する責任は、事実上、上訴する被告人側にあります。
(3) 構造的過誤(Structural Error)
無害な過誤の分析が一切適用されず、その存在自体が自動的に判決の取消しを要求する、根本的な過誤がいくつか存在します。これを「Structural Error」といいます。これは、過誤が特定の証拠に限定されず、裁判の枠組み全体に影響を及ぼし、その影響を事後的に評価することが不可能な性質を持つものです。最高裁判所が構造的過誤と認定した例には、以下のようなものがあります。
- 弁護人を受ける権利の完全な否定
- 公平でない裁判官による裁判
- 陪審員の選任における人種差別
- 公開裁判を受ける権利の否定
- 「合理的な疑い」の定義に関する陪審説示に欠陥がある場合
4. 明白な過誤の法理(Plain Error Doctrine)
原則として、被告人は、下級審で過誤があったと考える時点で直ちに異議(objection)を申し立てなければなりません。これを怠った場合、その争点を上訴で主張する権利は、原則として放棄(waived)されたものと見なされます。
しかし、この原則には重要な例外があります。それが「明白な過誤の法理(Plain Error Doctrine)」です。たとえ下級審で異議が申し立てられなかったとしても、その過誤が極めて明白かつ深刻である場合には、上訴審は、司法の公正さと廉潔性を守るために、職権でその過誤を取り上げ、是正することができます。
この救済が認められるための要件は、無害な過誤の場合よりもはるかに厳格です。United States v. Olano(1993年)によれば、被告人は以下の4つの要件を全て満たさなければなりません。
- 過誤(Error)が存在すること。
- その過誤が「明白(plain)」であること(現行法の下で明らかであること)。
- その過誤が被告人の「実質的な権利(substantial rights)」に影響を与えたこと。
- その過誤が、「司法手続の公正さ、廉潔性、または公的評価(the fairness, integrity or public reputation of judicial proceedings)」を深刻に害するものであること。
この最後の要件は、たとえ過誤が被告人の権利に影響を与えたとしても、上訴審が是正を拒否する裁量を留保するものであることを意味します。明白な過誤の法理は、当事者の怠慢を救済するためのものではなく、司法制度そのものの信頼性が揺らぐような、極めて例外的な事態に対処するためのものです。