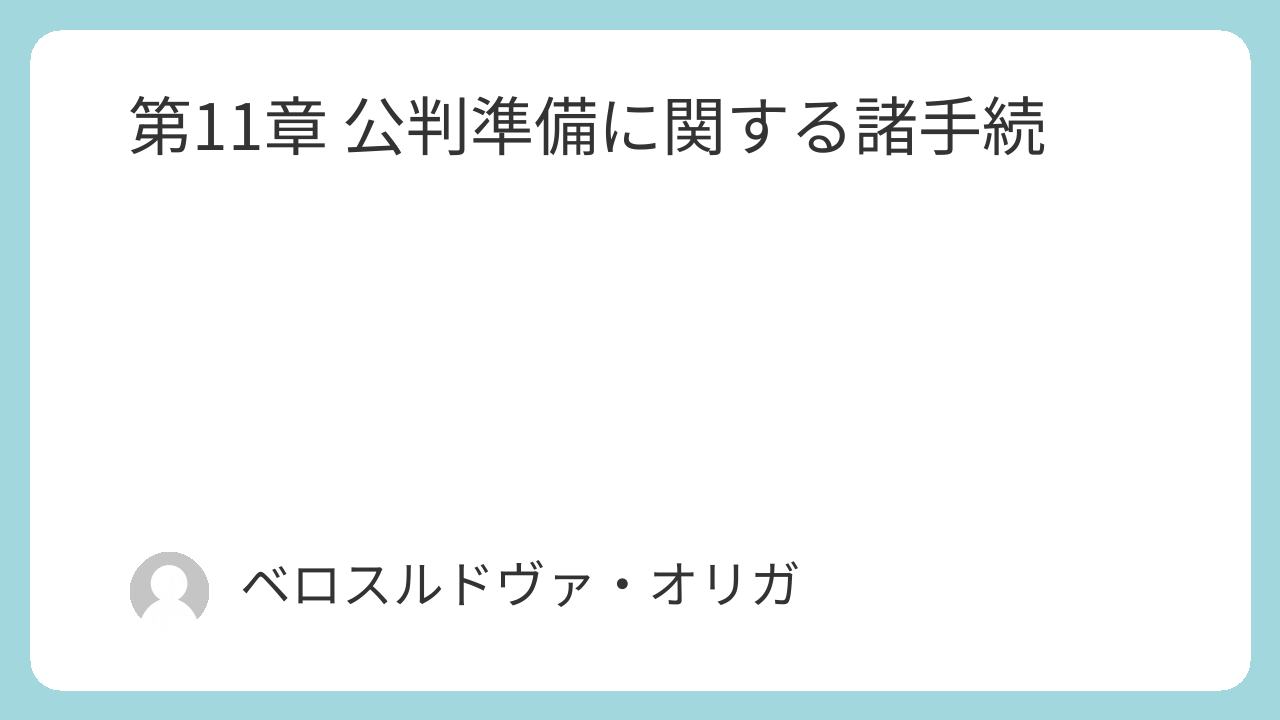公判準備段階における申立てや交渉が、公判の行方を大きく左右することも少なくありません。本章では、公正かつ効率的な裁判を実現するための基盤となる4つの重要な手続、すなわち、事件が審理される地理的な場所を決定する「裁判地」、複数の訴因や被告人を1つの手続で審理するかを決定する「併合と分離」、不当な遅延から被告人を保護する「迅速な裁判」の権利、当事者間で証拠を交換する「証拠開示」について、その法的な枠組みと実務上の重要性を詳述します。
1. 裁判地(Venue)
裁判地(Venue)とは、刑事事件が審理される地理的な場所(通常は郡や連邦の地区)を指します。その決定は、被告人が公正な裁判を受ける権利に直結する重要な問題です。
(1) 犯罪発生地主義
原則として、刑事裁判は犯罪が発生した州および地区で行われなければなりません。この「犯罪発生地主義」は、合衆国憲法3条及び修正6条によって保障されています。この原則の背後には、複数の理念が存在します。事件の証拠や証人がその地域に集中しているため、裁判を効率的に進めることができるという実務的な要請、地域社会が自らのコミュニティで発生した犯罪を裁くことへの関心、被告人が自らの地域社会の構成員からなる陪審によって裁かれる利益です。
(2) 裁判地の変更(Change of Venue)
しかし、犯罪発生地で裁判を行うことが、逆に被告人の公正な裁判を受ける権利を脅かす場合があります。特に、メディアの過熱報道などによって、地域社会に被告人に対する強い偏見や予断(Prejudice)が蔓延し、公平な陪審員を選定することが事実上不可能になるケースがこれにあたります。
このような状況において、被告人は裁判地の変更を申し立てることができます。申立てが認められるためには、弁護側は、公判前の報道が非常に広範かつ扇動的であり、その結果として、その地域では公平な陪審を期待できないことを具体的に証明する必要があります。裁判所は、報道の量と内容、コミュニティの規模、実際に陪審員候補者を選定する予備尋問(Voir Dire)の結果などを総合的に考慮して、裁判地の変更を認めるか否かを判断します。この手続は、地域的な偏見から被告人を隔離し、憲法が保障する公平な陪審による裁判を実現するための、最後のセーフガードとして機能します。
2. 併合と分離(Joinder and Severance)
司法の効率性を高めるため、刑事訴訟規則は、1つの手続で複数の訴因(charges)や複数の被告人(defendants)をまとめて審理すること(併合)を認めています。しかし、この効率性の追求が、被告人の公正な裁判を受ける権利を害する危険も伴います。
(1) 訴因の併合・分離
1人の被告人に対する複数の訴因は、それらが「類似の性質を持つ」又は「同一の行為・取引に基づいているか、共通の計画や企ての一部を構成している」場合に併合することができます。例えば、同一犯による一連の連続強盗事件などがこれにあたります。
しかし、併合によって被告人に不利益が生じるおそれがある場合、被告人は訴因の分離(severance of offenses)を申し立てることができます。不利益が生じる典型的なケースは以下の通りです。
- 証拠の累積効果: 本来は別個に評価されるべき各事件の証拠が、陪審員の頭の中で混ざり合い、全体として被告人が「犯罪者らしい」という印象を強めてしまう危険。
- 他の犯罪の証拠による汚染: ある訴因については証拠が弱いが、別の訴因(特に社会的に非難の強い犯罪)の証拠が強力である場合に、その強力な証拠のイメージが弱い訴因の事実認定に不当な影響を与える危険。
- 防御権の制限: 被告人が、ある訴因については証言したいが、別の訴因については黙秘権を行使したいと考える場合に、併合されているとその選択が事実上不可能になる。
(2) 被告人の併合・分離
複数の被告人が「同一の行為・取引に共同で参加した」とされる場合に、併合して共同で裁判にかけることができます。共謀事件や共同正犯の事件が典型例です。
共同被告人は、併合によって不当な不利益を受けると主張し、被告人の分離(severance of defendants)を求めることができます。分離が問題となる最も重要な状況は、Bruton Ruleとして知られています。これは、共同被告人の一人(A)が行った自白が、もう一人の被告人(B)に言及し、その罪を認める内容を含んでいる場合に関するものです。Aが公判で証言しない限り、BにはAの自白について反対尋問する機会がないため、Bの憲法修正6条上の対面権(Confrontation Clause)が侵害されます。たとえ裁判官が陪審に対し、「この自白はAに対する証拠としてのみ考慮し、Bに対しては考慮してはならない」という指示(limiting instruction)を与えたとしても、陪審員がその指示に従うことは現実的に困難です。したがって、このような場合、原則として裁判を分離するか、自白からBに関する部分を完全に削除する必要があります。
3. 迅速な裁判(Speedy Trial)の権利
修正6条は、「すべての刑事訴追において、被告人は、迅速な…裁判を受ける権利を有する」と保障しています。この権利は、以下の3つの重要な利益を保護することを目的としています。
- 抑圧的な公判前勾留を防ぐこと。
- 訴追され、解放されている被告人の不安や懸念を最小限に抑えること。
- 時間の経過による証拠の散逸や証人の記憶の減退によって、被告人の防御能力が損なわれる可能性を限定すること。
この権利が侵害されたか否かを判断するため、最高裁判所はBarker v. Wingo(1972年)判決において、以下の4つの要素を総合的に衡量する均衡審査(balancing test)を確立しました。
- 遅延の期間(Length of delay): 遅延が「推定的に不利益(presumptively prejudicial)」と見なされるほど長期間(通常は1年程度が目安)に及んでいるか。これが他の3要素を検討するためのトリガーとなります。
- 遅延の理由(Reason for the delay): 遅延が検察側の意図的な戦術によるものか、裁判所の過密状態のような中立的な理由か、それとも弁護側の申立てによるものか。
- 被告人による権利の主張(Defendant’s assertion of his right): 被告人が迅速な裁判を求める権利を適時に主張したか。
- 被告人への不利益(Prejudice to the defendant): 遅延によって、前述の3つの利益(勾留、不安、防御能力)がどの程度害されたか。
この憲法上の権利に加え、連邦および多くの州では、より具体的な期限を定めた迅速裁判法(Speedy Trial Act)が制定されています。例えば、連邦の法律は、起訴から公判開始までの期間を原則として70日以内と定めています。
4. 証拠開示(Discovery)
対審制度が「闇討ち裁判(trial by ambush)」に陥ることを防ぎ、真実発見に資するため、公判前に当事者間で証拠を交換する手続が不可欠です。これが証拠開示(Discovery)です。
(1) 検察側の開示義務:ブレイディ・ルール
証拠開示に関する最も重要な憲法上のルールが、Brady v. Maryland(1963年)判決とその後の判例によって確立された、いわゆるブレイディ・ルール(Brady Rule)です。このルールは、検察官に対し、被告人の有罪・無罪または量刑に関して「有利(favorable)」でありかつ「重要(material)」な証拠を、被告人の請求の有無にかかわらず、開示することを義務付けます。
- 有利な証拠: これには、被告人の無実を示す証拠(無罪証拠、exculpatory evidence)だけでなく、検察側証人の信用性を低下させる証拠(弾劾証拠、impeachment evidence)も含まれます。
- 重要な証拠: 証拠が「重要」であるとは、「その証拠が開示されなかった場合、裁判の結果に対する信頼を揺るがすに足る合理的な確率」が存在することを意味します。
検察官がこの開示義務に違反した場合、それはデュー・プロセス違反となり、有罪判決が覆される可能性があります。
(2) 弁護側の開示義務
多くの法域では、弁護側にも証拠開示義務(reciprocal discovery)が課されています。これは通常、弁護側が検察側に証拠開示を請求した場合に、その見返りとして発生します。弁護側が開示を求められる典型的な情報には、アリバイの抗弁を主張する意図や、そのアリバイを裏付ける証人のリスト、そして弁護側が公判で使用を予定している専門家証人の報告書などがあります。