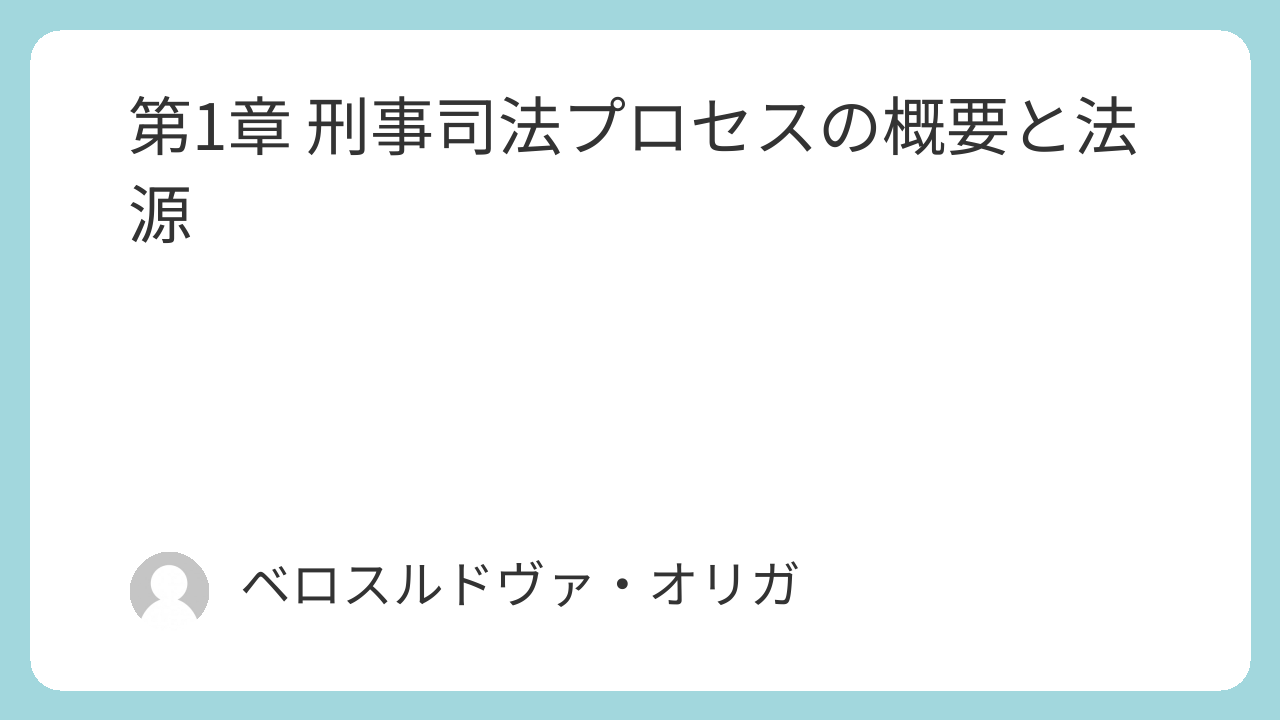本章では、アメリカの刑事司法制度を理解するための基礎となる2つの要素、すなわち手続の全体像と、それを規律する法の源泉について解説します。個別の論点に入る前に、まず犯罪の発生から最終的な司法的救済に至るまでの一連の流れを俯瞰し、次いで、このプロセスを支える連邦と州の二元的な法構造、憲法・制定法・判例法といった法源の役割を明らかにします。これにより、次章以降で紹介する各手続が、制度全体のどこに位置づけられ、いかなる法的基盤に基づいているのかを明確に理解することができるようになります。
1. 刑事手続の全体像
アメリカの刑事手続は、大きく「捜査」「訴追」「公判」「判決後手続」の4つの段階に分けることができます。
(1) 捜査段階 (Investigative Stage)
刑事手続は、犯罪が発生した又はその疑いがあるという情報から始まります。警察などの捜査機関は、まず逮捕前捜査(Pre-arrest Investigation)として、事情聴取、現場検証、監視活動などを行い、証拠を収集します。この段階で、捜査機関が特定の人物による犯罪の実行について「相当な理由(Probable Cause)」が認められる等の要件を満たす場合、その人物を逮捕(Arrest)することになります。逮捕は、裁判官が発付する逮捕令状に基づく場合と、現行犯等令状なしで行われる場合があります。
逮捕後、捜査は新たな段階に入ります。逮捕後捜査(Post-arrest Investigation)として、被疑者の身柄を拘束した上で、より詳細な証拠収集が行われます。これには、逮捕に伴う捜索(Search Incident to Arrest)、所持品の検査、そしてミランダ警告で知られる権利の告知を経た上での取調べ(Interrogation)などが含まれます。この段階で収集された証拠、特に被疑者の自白は、その後の手続において極めて重要な役割を果たします。
(2) 訴追段階 (Charging Stage)
捜査が一段落すると、事件は検察官の手に委ねられます。検察官は、警察から送付された捜査資料を検討し、訴追の決定(Charging Decision)を行います。証拠が不十分である場合、不起訴とする広範な裁量が検察官には認められています。
訴追が決定されると、正式な刑事手続が開始されます。まず、被疑者は裁判官の面前で行われる初出廷(Initial Appearance)に臨み、訴追事実の告知、弁護人依頼権の確認、そして保釈の決定などが行われます。
その後、訴追を継続するに足る「相当な理由」が存在するかを判断するための審査手続が待っています。この審査には主に2つの形式があります。1つは、裁判官が公開の法廷で証人尋問などを行い判断する予備審問(Preliminary Hearing)です。もう1つは、非公開で市民(陪審員)が検察官の提示する証拠のみを審査し、起訴の可否を判断する大陪審による審査(Grand Jury Review)です。連邦の重罪事件では憲法上、大陪審による起訴状(Indictment)が必須とされていますが、州によっては予備審問を経て検察官が略式起訴状(Information)を提出する方法も広く採用されています。
(3) 公判段階 (Trial Stage)
起訴が確定すると、事件は公判段階へと移行します。公判準備の中心となるのが、公判前申立て(Pretrial Motions)と証拠開示(Discovery)です。弁護側は、違法に収集された証拠の排除を求める申立て(Motion to Suppress)や、起訴状の欠陥を指摘する申立てなどを行うことができます。また、証拠開示手続を通じて、検察側が保有する証拠(特に被告人に有利な証拠)を入手し、防御の準備を整えます。
この段階で、多くの事件はPlea Bargainingによって解決されます。被告人が有罪を認める(Guilty Plea)見返りに、検察官が訴因の取り下げや軽い量刑の求刑を約束するもので、アメリカ刑事司法の実務において中心的な役割を担っています。
Plea Bargainingが成立しない場合、事件は公判(Trial)に進みます。アメリカの刑事公判の最大の特徴は、陪審裁判が原則であることです。市民から選ばれた陪審員が事実認定を行い、有罪か無罪かの評決を下します。公判では、冒頭陳述、証拠調べ(証人尋問、証拠物の提出)、最終弁論、裁判官による陪審への説示といった一連の手続が、厳格な証拠法に基づいて進められます。
(4) 判決後手続 (Post-conviction Stage)
陪審が有罪の評決を下した場合、手続は量刑(Sentencing)段階に移ります。裁判官は、量刑ガイドラインや法律の定める範囲内で、被告人に科される刑罰(懲役、罰金など)を決定します。
判決に不服がある被告人は、上訴(Appeals)を行うことができます。上訴審では、主に公判手続における法律上の誤りがなかったかが審査されます。さらに、通常の上訴手続が尽きた後も、Collateral Remediesと呼ばれる事後的な救済手段が存在します。その代表が人身保護令状(Habeas Corpus)であり、特に憲法上の権利侵害を理由として、身柄拘束の違法性を争うために用いられます。
2. 連邦と州の二元構造(Federalism)
アメリカの刑事手続を理解する上で不可欠なのが、連邦制度と州制度が併存する二元構造(Federalism)の理解です。アメリカには単一の刑事司法制度が存在するわけではありません。連邦政府の制度に加え、50の州とコロンビア特別区が、それぞれ独立した刑事司法制度を運営しています。つまり、合計で52の異なる法域が存在し、それぞれが独自の法体系を持っています。
この多様性は、刑事手続の具体的な運用に大きな違いをもたらします。例えば、前述の通り、大陪審による起訴を必須とするか否か、陪審員の人数(伝統的には12人ですが、州によっては6人でも合憲とされます)、評決の全員一致を要求するか否かなど、多くの点で法域による差異が見られます。
連邦法と州法の関係は、合衆国憲法によって規律されます。合衆国憲法、特にその修正条項(権利章典)は、全ての法域に適用される最低限の保障(a constitutional floor)を定めています。州は、この憲法上の基準を下回ることは許されませんが、独自の州憲法や法律によって、連邦憲法が要求する以上の、より手厚い権利を住民に保障することは自由です。したがって、ある捜査手法が連邦憲法上は合憲とされても、特定の州の憲法下では違憲と判断されることもあり得ます。
3. 刑事手続の法源
これら52の法域における刑事手続は、主に4つの法源によって形作られています。
- 憲法(Constitutions): 最も重要な法源は合衆国憲法です。特に、不合理な捜索・差押えを禁じる修正4条、自己負罪拒否特権や二重の危険の禁止を定める修正5条、弁護人依頼権や迅速な裁判、陪審裁判の権利を保障する修正6条、残虐で異常な刑罰を禁じる修正8条、これらの権利を州にも適用する根拠となる修正14条が、刑事手続の根幹をなします。これに加えて、各州が持つ独自の州憲法も、その州における重要な法源となります。
- 制定法(Statutes): 連邦議会や州議会が制定する法律も、刑事手続を具体的に規律します。連邦レベルでは合衆国法典(U.S. Code)が、州レベルでは各州の刑事訴訟法典などがこれにあたります。これらの制定法は、犯罪の定義、捜査機関の権限、裁判所の構成、量刑の範囲などを詳細に定めています。
- 裁判所規則(Court Rules): 裁判所自身が、その運営や訴訟手続を円滑に進めるために定める規則も重要な法源です。連邦裁判所における連邦刑事訴訟規則(Federal Rules of Criminal Procedure)はその代表例であり、起訴状の記載方法から証拠開示の範囲、公判の進行に至るまで、実務的な手続を網羅的に規定しています。多くの州も同様の規則体系を有しています。
- 判例法(Case Law): 裁判所、特に上級審による判決は、法の解釈を具体的に示し、将来の事件を拘束する判例となります。とりわけ、合衆国最高裁判所の判決は、憲法解釈に関する最終的な権威を持ち、全米の刑事手続に決定的な影響を与えます。Miranda v. Arizona(1966年)が取調べのあり方を一変させたように、判例の積み重ねによって、刑事手続の法理は絶えず発展し、形成され続けています。