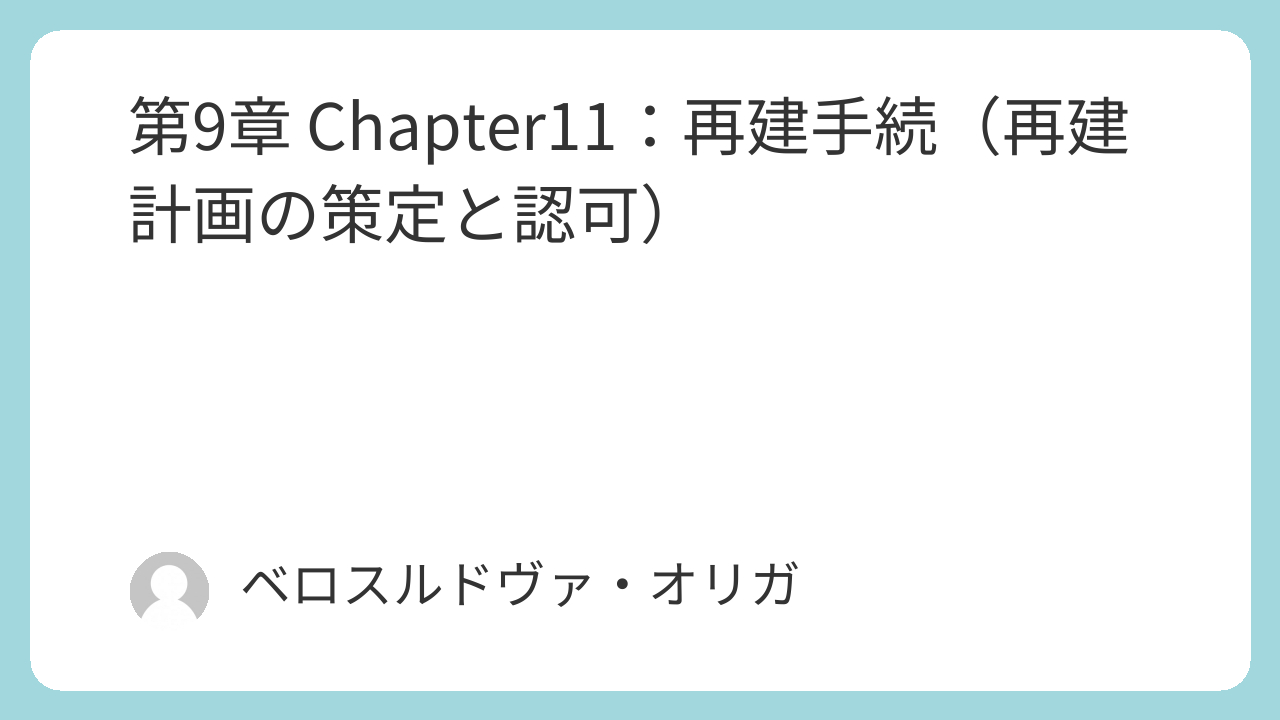前章で取り扱ったChapter11の手続の前半は、申立て直後の混乱を鎮め、事業運営を安定化させ、DIPファイナンス等を通じて当面の運転資金を確保することに費やされます。しかし、Chapter11の最終的なゴールは、安定した事業基盤の上に、企業の将来像を描く「再生計画(Plan of Reorganization)」を策定し、全ての利害関係者の承認を取り付け、裁判所の最終的なお墨付きである「認可(Confirmation)」を得ることにあります。
再建計画(Plan of Reorganization)の策定
再生計画は、倒産した企業がどのように債務を処理し、どのような姿で再生するのかを具体的に定める、法的拘束力を持つ契約書であり、会社の新たな憲法とも言えるものです。その策定プロセスは、Chapter11手続における主導権争いの中心となります。
排他的提出期間(Exclusivity Period)
Chapter11の大きな特徴の1つに、再生計画の提出権に関する「排他的提出期間(Exclusivity Period)」の存在があります。連邦倒産法典1121条によれば、原則として、申立後の最初の120日間は、債務者(DIP)のみが再生計画を提出する排他的な権利を有します。
この120日間という期間は、DIPにとって極めて重要な戦略的価値を持ちます。DIPが外部からの干渉を受けずに、自らのペースで再建の道を模索し、債権者との交渉を進めることができるからです。この期間中、債権者委員会や個別の債権者は、たとえDIPの提案に不満があったとしても、自ら対案を提出することはできません。DIPは、この排他権を交渉のレバレッジとして利用し、債権者に対して自らの計画案への同意を促すことができます。
この排他的提出期間は、裁判所の判断により延長することが可能です。ただし、延長には「正当な理由」が必要であり、単に時間稼ぎを目的とした延長は認められません。大規模で複雑な事件では、この期間が数度にわたって延長されることも珍しくありませんが、法律は、申立てから18ヶ月を超える延長は原則として認めないという上限を設けています。
排他的提出期間内にDIPが計画を提出しなかった場合や、提出した計画が定められた期間内(申立て後180日)に債権者の同意を得られなかった場合、この排他権は消滅します。そうなれば、債権者委員会・個別の債権者・管財人といったあらゆる利害関係者が、それぞれ独自の再生計画を提出することが可能となります。これは、手続の主導権がDIPの手から離れ、複数の計画案が乱立する「プラン・ウォー(Plan War)」へと突入する可能性を意味し、DIPにとっては最も避けたい事態です。
再建計画の内容(Contents of the Plan)
再生計画に何を盛り込むべきかについては、連邦倒産法典1123条が詳細なルールを定めています。計画には、必ず含めなければならない「必須条項」と、任意に含めることができる「任意条項」があります。
- 必須条項(Mandatory Provisions):
- 債権者・持分権者の分類: 計画は、全ての債権(Claim)と持分(Interest)を、後述するルールに従って性質の類似したグループ(クラス)に分類しなければなりません。
- 「変更されないクラス」の特定: 計画によって、その法的・契約上の権利が一切変更されないクラスを明記します。
- 「変更されるクラス」の処遇: 計画によって権利が変更される(impaired)各クラスについて、その具体的な処遇(例えば、債務の何パーセントをいつ支払うか、債務を株式に転換するかなど)を明記します。
- クラス内の平等な処遇: 同じクラスに属する全ての債権者または持分権者は、原則として全く同じ処遇を受けなければなりません。
- 計画実行のための適切な手段: 計画を実現するための具体的な方法を提示しなければなりません。例えば、DIPによる事業継続、資産の売却、他社との合併、新たな役員や取締役の選任、新株の発行、定款の変更などが含まれます。
- 任意条項(Permissive Provisions):
- 未履行契約の引受・拒絶: 申立て時点で未履行であった契約について、計画の中で引受けまたは拒絶を選択することができます。
- 資産の売却: 倒産財団の資産の全部または一部を、再生計画の一環として売却することを定めることができます。これは、第5章で解説した363条売却とは別の、計画に基づく売却です。
- その他、法典の規定に反しない、計画の実行に適切ないかなる条項も盛り込むことができます。
再生計画は、これらの要素を組み合わせ、債務者の具体的な状況に合わせてオーダーメイドで作成される、極めて創造的な文書なのです。
開示説明書と同意勧誘(Disclosure and Solicitation)
DIPが再生計画案を策定したとしても、直ちに債権者の投票を求めることはできません。その前に、債権者が計画の賛否について「情報に基づいた判断(informed judgment)」を下せるようにするための、極めて重要な情報開示プロセスを経なければなりません。その中心となるのが「開示説明書(Disclosure Statement)」です。
開示説明書(Disclosure Statement)
開示説明書は、再生計画案に添付される詳細な説明文書であり、その目的は、連邦倒産法典1125条が定める「適切な情報(Adequate Information)」を、投票権を持つ全ての債権者と持分権者に提供することにあります。これは、証券取引における目論見書(Prospectus)に類似した役割を果たします。
「適切な情報」とは、特定のクラスの典型的な債権者が、計画について情報に基づいた判断を下すことを合理的に可能にするような種類と詳細さを持つ情報、と定義されています。この基準は柔軟であり、事件の規模や複雑さに応じて、開示の程度は変わってきます。
開示説明書には、通常、以下のような内容が含まれます。
- 企業の歴史と、Chapter11申立てに至った経緯
- 再生計画案の各条項の要約と、それが各クラスに与える影響の詳細な解説
- DIPが作成した、再生後の企業の財務予測(キャッシュフロー、損益計算書、貸借対照表など)
- 清算分析(Liquidation Analysis): もしこの再生計画が実行されずに、会社がChapter 7で清算された場合に、各クラスの債権者がどれくらいの分配を受けられるかの試算。これは、後述する「最善の利益テスト」をクリアしていることを示すために不可欠です
- 倒産財団の資産と負債の状況
- 再生後の企業の経営陣に関する情報
この開示説明書は、債権者に送付される前に、必ず倒産裁判所の承認を得なければなりません。裁判所は、開示説明書の内容が「適切な情報」を含んでいるかどうかを審査するための審理を開きます。この審理で、債権者委員会などは、情報が不十分である、あるいは誤解を招くといった異議を述べることができます。裁判所の承認を得て初めて、DIPは次のステップである同意勧誘に進むことができます。
同意勧誘(Solicitation of Votes)
裁判所が開示説明書を承認すると、DIPは、投票権を持つ全ての債権者と持分権者に対し、以下のものをパッケージとして送付し、計画への賛成票を正式に要請(勧誘)します。
- 再生計画案
- 裁判所が承認した開示説明書
- 賛否を投じるための投票用紙(Ballot)
- 計画認可審理の日時を通知する裁判所の命令
債権者は、これらの資料を熟読し、自らの利益を考慮して、定められた期限までに賛成または反対の票を投じることになります。
債権者の分類と投票(Classification and Voting)
再生計画に対する投票は、個々の債権者がバラバラに行うのではなく、同じような権利を持つ者同士がグループ(クラス)にまとめられ、クラス単位で賛否が集計されます。この「分類」と「投票」のルールが、計画認可の行方を左右します。
債権者の分類(Classification of Claims)
1122条に基づき、再生計画は、請求権や持分をクラスに分類しなければなりません。その際の基本原則は、1つのクラスには「実質的に類似した(substantially similar)」権利のみを含めることができるというものです。
- なぜ分類が重要か: 分類は、単なる整理作業ではありません。どの債権をどのクラスに入れるかによって、投票結果が大きく変わる可能性があるからです。例えば、あるクラスが計画に反対した場合でも、そのクラスをさらに細分化して、賛成してくれそうな債権者だけで新たなクラスを作ることができれば、後述するクラムダウンの要件を満たせるかもしれません。
- 分類の限界: このような戦略的な分類には限界があります。裁判所は、明確なビジネス上の理由なく、実質的に類似した債権を別々のクラスに分けることを、不当な操作として認めないことがあります。一般的に、担保権の内容・優先順位・契約上の権利などが、類似性を判断する基準となります。
- 典型的なクラス分け:
- 管理費用債権や優先的税金債権(これらは通常、投票権のない優先的な扱いを受けるため、分類されないことが多い)
- 特定の担保物を持つ担保付債権者(通常、担保物ごとに一つのクラスを形成する)
- 一般無担保債権者(社債権者、取引債権者など)
- 劣後債権者
- 株主(持分権者)
投票(Voting)
- 投票権を持つ者: 計画によってその権利が「変更される(impaired)」クラスに属する債権者と持分権者のみが、投票権を有します。
- 「変更(Impairment)」とは: 計画が、あるクラスの法的、衡平法上、契約上の権利を、いささかでも変更する場合、そのクラスは「変更される」ものとみなされます。例えば、支払期日を延長する、利率を下げる、元本を一部カットするといった変更はもちろん、保証人を外すといった僅かな変更でもインペアメントに該当します。逆に、権利が全く変更されず、申立て前の状態と完全に同じ条件で支払いが保証されるクラスは「変更されない(unimpaired)」クラスとなり、計画に同意したものとみなされ、投票権は与えられません。
- 計画の下でいかなる財産も受け取らない(つまり、100%カットされる)クラスは、計画に反対したものとみなされ、やはり投票権は与えられません。
- クラスによる承認の要件: あるクラスが計画を「承認した」とみなされるためには、そのクラスに属する債権者(または持分権者)のうち、実際に投票した者を母数として、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。
- 債権者のクラスの場合:
- 金額基準: 投票した者の請求権総額の3分の2以上が賛成すること。
- 頭数基準: 投票した者の過半数(2分の1超)が賛成すること。
- 持分権者のクラスの場合:
- 投票した者の持分総額の3分の2以上が賛成すること(頭数要件はありません)。
- 債権者のクラスの場合:
この二重の要件は、「少数の大口債権者」や「多数の小口債権者」だけでクラスの意思を決めてしまうことを防ぐための仕組みです。
計画の認可要件(Confirmation Requirements)
全ての投票が集計された後、手続は最終段階である「認可審理(Confirmation Hearing)」へと進みます。ここで、計画提出者は、裁判官に対し、計画が連邦倒産法典1129条に定められた全ての要件を満たしていることを証明しなければなりません。充足すべき要件の数自体も多い上、要件該当性は厳格に判断されます。
同意による認可(Consensual Confirmation)
最もスムーズな認可の形は、全ての「変更されるクラス」が計画を承認した場合です。この場合でも、計画は第1129条(a)項に列挙された十数個の要件を全てクリアしなければなりません。その中でも特に重要な要件は以下の通りです。
- (a)(1) 法典遵守: 計画そのものが、法典の適用ある規定(例えば、前述の分類のルールなど)に準拠していること。
- (a)(3) 善意(Good Faith): 計画が、法典の目的(債務の再編と債権者への分配の最大化)に合致した、誠実な意図で提出されたものであり、何か違法な目的を達成するための手段として利用されていないこと。
- (a)(7) 最善の利益テスト(Best Interests of Creditors Test): これは、クラスとしては計画に賛成したものの、その中で個人的に反対票を投じた債権者を保護するための、極めて重要なセーフガードです。このテストは、変更される各クラスの全ての債権者について、計画の下で受け取る分配の価値が、「もし会社がChapter 7で清算された場合に受け取れたであろう分配の価値」以上であることを要求します。
- この証明のため、計画提出者は、詳細な「清算分析」を裁判所に提出する必要があります。裁判所は、この分析に基づき、Chapter 11による再建が、清算よりも全ての債権者にとって有利な結果をもたらすことを確認します。もし、清算した方がより多くの分配を得られるのであれば、その再生計画は認可されません。
- (a)(8) 全クラスの承認: 変更される全てのクラスが、前述の投票要件に従って計画を承認したこと。
- (a)(11) 実行可能性テスト(Feasibility Test): 計画の認可が、その後の清算や、さらなる再建手続の必要性につながる可能性が低いこと。つまり、再生後の企業が、合理的に見て存続可能であることを証明しなければなりません。計画提出者は、説得力のある事業計画と財務予測を提示し、再生後の企業が計画通りの債務返済を遂行し、事業を継続していけることを示さなければなりません。
これらの要件が全て満たされた場合、裁判所は計画を認可する命令を下します。
クラムダウン(Cramdown)
仮に1つでも「変更されるクラス」が計画に反対(否決)した場合であっても、再建の道が閉ざされる訳ではありません。連邦倒産法典は、このような状況を打開するための手段が、1129条(b)項に定められた「Cramdown」です。
クラムダウンとは、文字通り、反対するクラスの喉に計画を「押し込む(cram down)」ことを意味する、強制的な認可手続です。
強制認可の要件
計画提出者がクラムダウンを求めるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 計画が、1129条(a)項の要件のうち、全クラスの承認を要求する(a)(8)項以外の全てを満たしていること。
- 変更されるクラスのうち、少なくとも1つのクラスが計画を承認していること。これは、債権者の中に全く支持者のいない計画が強制認可されることを防ぐための重要な要件です。
- 裁判所が、計画が「不当に差別せず(does not discriminate unfairly)」、かつ、反対した各クラスに対して「公正かつ衡平(is fair and equitable)」であると判断すること。
「公正かつ衡平(Fair and Equitable)」の要件と絶対的優先の原則
クラムダウンの核心は、この「公正かつ衡平」という要件にあります。その具体的な意味は、反対したクラスの種類によって異なります。
- 反対した担保付債権者クラスに対して:
再生計画は、少なくとも、(i)そのクラスの債権者が自らの担保物を対象とする担保権を保持し続け、かつ、(ii)その担保物の価値以上の現在価値を持つ現金の支払いを受けることを定めなければなりません。 - 反対した無担保債権者クラスに対して:
ここで、倒産法における最も厳格かつ重要な原則の1つである「絶対的優先の原則(Absolute Priority Rule, APR)」が登場します。
絶対的優先の原則とは、反対した無担保債権者のクラスが、その請求権の全額について弁済を受けない限り、そのクラスよりも劣後するいかなるクラス(通常は株主のクラス)も、計画の下でいかなる財産も受け取ったり保持したりすることはできないというルールです。つまり、無担保債権者への配当が100%に満たない計画をクラムダウンしようとする場合、既存の株主の権利は完全に消滅(ワイプアウト)させられなければならず、彼らが再生後の会社の株式を保持することは、原則として許されないのです。 - ニュー・バリュー例外(New Value Exception): この厳格な絶対的優先の原則を巡り、長年議論されてきたのが、「ニュー・バリュー」の論点です。これは、旧株主が、その過去の株主という地位「に基づいて(on account of)」ではなく、再生後の企業に対して「新たな価値(New Value)」を現金等で提供することを対価として、再生後の企業の新たな株式を取得することは許されるのではないかという考え方です。もしこれが認められれば、旧株主は、無担保債権者が全額弁済されなくとも、会社を「買い戻す」形で経営権を維持することが可能となります。
連邦最高裁判所は、この問題について何度か判断を示していますが、確たる「例外」として認めたことはありません。しかし、下級審の判例の積み重ねにより、極めて厳格な条件下では、旧株主による新たな出資が認められる余地があると解されています。その「新たな価値」は、(i) 新規のもので(過去の貢献ではない)、(ii) 実質的なもので(名目的な金額ではない)、(iii) 現金または現金同等物であり、(iv) 会社の再建に必要不可欠であり、(v) 提供する価値が、それによって得られる再生後の会社の株式価値と合理的にみて等価である、といった厳しい要件を満たす必要があります。このニュー・バリューを巡る攻防は、クラムダウンにおける最も激しい争点の一つです。
認可命令が確定すると、計画は債務者、債権者、株主といった全ての関係者を法的に拘束する、新たな契約となります。申立て前の債務は計画に従って処理され、会社は新たな資本構成の下で、倒産裁判所の監督から離れ、再生への道を歩み始めることになります。