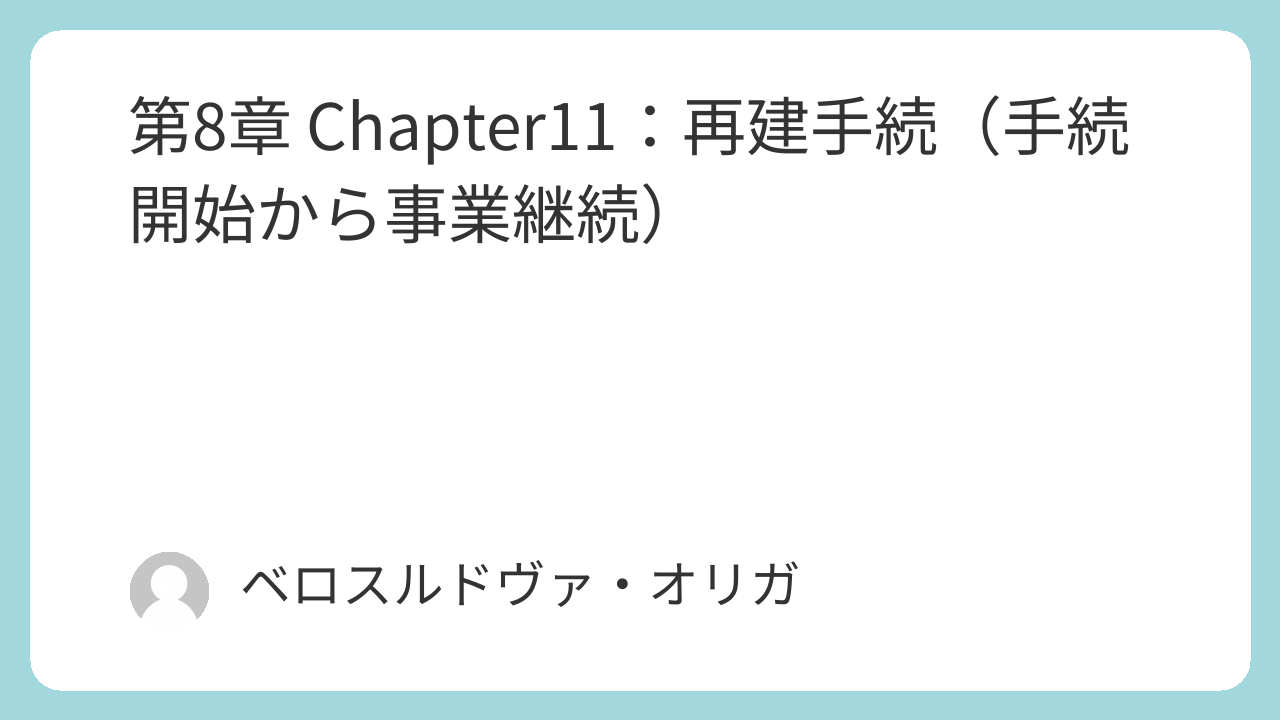日本の新聞やニュースでしばしば「Chapter11」という言葉を耳にするように、連邦倒産法典のチャプターの中でも、Chapter11は、アメリカ国内のみならず、世界的に最も影響力のある制度となっています。Chapter7が事業の「死」を司る手続であるとすれば、Chapter11は事業の「再生」を追求する手続です。
その鍵は、危機に瀕した企業を直ちに解体するのではなく、事業活動を継続させることによって生まれる「事業継続価値(Going-Concern Value)」を最大限に維持・向上させるという思想にあります。工場、従業員、ブランド、顧客網といった資産は、バラバラに売却されれば価値が著しく毀損しますが、一体として機能し続けることで、清算価値をはるかに上回る価値を生み出します。Chapter11は、この事業継続価値こそが、債務者、債権者、従業員、そして社会全体にとって最大の利益となるとの信念に基づいています。
Chapter 11の特徴と柔軟性
Chapter11は、個人事業主からFortune500に名を連ねる巨大多国籍企業まで、あらゆる規模の事業者が利用できる、極めて柔軟性の高い制度です。その目的は、自動的停止(Automatic Stay)という保護された環境の下で、債務者が債権者と交渉し、債務を削減・再編し、事業運営を合理化するための「再生計画(Plan of Reorganization)」を策定し、最終的に裁判所の認可を得て実行に移すことにあります。
この手続の根幹を支えるのが、次節で詳述するDIP(占有継続債務者)制度です。事業内容を最もよく知る既存の経営陣が、原則として経営の主導権を握り続けることで、経営の継続性を保ち、迅速かつ実情に即した意思決定が可能となります。管財人が全ての権限を掌握するChapter 7とは、この点で根本的に異なります。
DIP型(占有継続債務者:Debtor in Possession)原則
Chapter 11を申し立てた債務者は、申立てと同時に、特別な法的地位を獲得します。それが「占有継続債務者(Debtor in Possession)」、通称「DIP」です。これは、Chapter 11の基本原則であり、その成否を左右する最も重要な概念です。
DIPとは、その言葉通り、「財産を占有し続ける債務者」を意味します。Chapter 7では申立てと同時に管財人が選任され、債務者から財産の管理処分権を剥奪するのに対し、Chapter 11では、原則として管財人は選任されず、債務者自身(法人の場合はその経営陣)が引き続き事業の運営と財産の管理を行います。
しかし、DIPはもはや単なる申立て前の債務者ではありません。法典上、DIPは、管財人が有するほぼ全ての権利・権限・義務を負うことになります。これには、第4章で解説したストロング・アーム条項や偏頗行為否認といった強力な否認権の行使、第5章で解説した未履行双務契約の引受・拒絶権や資産の売却権限なども含まれます。つまり、DIPは、一方では自らの事業を運営する経営者でありながら、もう一方では、全ての債権者の利益のために行動する倒産財団の「受託者(Fiduciary)」という、2つの顔を持ちます。
この受託者としての義務は極めて重いものです。DIPは、もはや株主の利益だけを考えて経営判断を下すことは許されません。その決定は、担保付債権者・無担保債権者・従業員といった、全ての利害関係者(ステークホルダー)の利益を公平に考慮したものでなければならず、常に倒産財団の価値を最大化するという目的に沿ったものでなければなりません。この受託者義務への違反は、経営陣の解任や、後述する管財人の選任といった事態を招きかねません。
もちろん、DIPが野放しにされるわけではありません。その活動は、債権者委員会や連邦管財官、そして最終的には倒産裁判所の厳格な監督下に置かれます。しかし、事業の日常的な運営について、その内容を最も熟知した経営陣に委ねるというDIP制度の存在こそが、Chapter 11を硬直的な法的手続ではなく、柔軟でビジネス志向の再建プロセスたらしめている根源なのです。
なお、例外的に、DIPによる詐欺、不正行為、著しい能力不足や経営上の重大な過失といった「正当な理由」が存在する場合には、利害関係者の申立てに基づき、裁判所がDIPに代わって「Chapter 11管財人」を選任することがあります。しかし、これはDIPの経営に対する信頼が失われた場合に限られる、例外的な措置です。
手続の初期段階:First Day Motionsと初日命令
企業がChapter 11を申し立てた瞬間、事業は深刻な危機に直面します。自動的停止によって債権者からの直接的な取立ては止まるものの、事業運営そのものが麻痺してしまう危険性があるからです。銀行口座は凍結され、従業員は給与が支払われるか不安になり、重要なサプライヤーは商品の供給を停止し、顧客は将来を懸念して離れていくかもしれません。この申立て直後の混乱期を乗り切り、事業の崩壊を防ぎ、安定した運営を確保するために行われる一連の緊急手続が「First Day Motions」です。
これは、債務者がChapter 11の申立てと同時又は直後(通常は24時間から48時間以内)に裁判所に提出する、一連の緊急許可申立てのことです。裁判所は、これらの申立てについて緊急に審理を開き、事業継続に不可欠と判断された事項について許可を与えます。これが「First Day Orders」です。このFirst Day Ordersを得られるかどうかが、Chapter 11の成否を占う最初の関門となります。
以下に、典型的なFirst Day Motionsを挙げます。
- キャッシュ・マネジメント・システムの維持申立て(Cash Management Motion): 大企業は通常、複数の銀行にまたがる複雑な口座システム(キャッシュ・マネジメント・システム)を構築し、日々の資金移動を行っています。申立てによってこれらの口座が凍結されれば、事業は即座に停止します。この申立ては、既存の銀行口座や資金管理システムを申立て後も継続して使用するための許可を求めるものです。
- 従業員の給与・福利厚生の支払許可申立て(Employee Wages and Benefits Motion): 従業員は、企業の最も重要な資産の1つです。申立前に発生した未払いの給与や経費、福利厚生(健康保険など)が支払われなければ、従業員の士気は著しく低下し、大量離職による事業価値の毀損は避けられません。この申立ては、これらの申立前の従業員債権を、他の一般無担保債権者に先んじて支払うための特別な許可を求めるものです。これは、厳密には倒産法の優先順位ルール(賃金債権に上限もある)の例外となりますが、事業継続の必要性から裁判所は合理的な範囲でこれを認めるのが一般的です。
- 重要取引先(クリティカル・ベンダー)への支払許可申立て(Critical Vendors Motion): 債務者の事業にとって、代替の利かない部品やサービスを提供する、極めて重要なサプライヤーが存在する場合があります。このようなサプライヤーが、申立前の未払いを理由に取引を停止すれば、債務者の生産ラインは止まってしまいます。この申立ては、このような「重要取引先(Critical Vendor)」に対する申立て前の債務を優先的に支払う許可を求めるものです。これは、債権者平等の原則に対する例外であり、「必要性の法理(Doctrine of Necessity)」に基づき、その支払いがなければ事業に回復不能な損害が生じ結果として全ての債権者の利益を害する場合にのみ、限定的に認められます。
- 公共料金の支払保証に関する申立て(Utilities Motion): 電気・ガス・水道・電話といった公共サービス事業者は、倒産を理由に一方的にサービスを停止することはできませんが、申立後20日以内に、将来の支払いに関する「適切な保証(Adequate Assurance)」を債務者が提供しない限り、サービスを停止することができます。この申立ては、保証金の預託や支払保証状の提供といった、具体的な保証方法について裁判所の承認を得るものです。
プレパッケージ型・プリアレンジ型申立て
伝統的なChapter11手続は、申立後にゼロから債権者と交渉を始めるため、時間と費用がかかり、事業価値が毀損するリスク(いわゆる「Melting Ice Cube問題」)を伴います。この問題を克服するため、実務では、申立前に再建の準備を整えておく、より効率的な手法が発展してきました。
- プレパッケージ型申立て(Pre-packaged Plan, “Pre-pack”): これは、Chapter11の「究極の」迅速化手法です。債務者は、破産を申し立てる前に、債権者と再生計画の内容について交渉を完了させるだけでなく、その計画案に対する債権者の投票(同意勧誘、Solicitation)まで済ませてしまいます。計画の承認に必要な賛成票が集まった段階で、完成した再生計画と共にChapter11を申し立てます。申立て後のプロセスは、その計画を裁判所が法的に認可(Confirmation)する手続きに集約されるため、Chapter11の期間を数ヶ月、場合によっては数週間にまで短縮することができます。
- プリアレンジ型申立て(Pre-arranged or Pre-negotiated Plan): プレパッケージ型ほどではありませんが、これも迅速化の手法です。この場合、債務者は、破産を申し立てる前に、主要な債権者(銀行団や債権者委員会など)との間で再生計画の主要な条件について合意を形成しておきます。しかし、全債権者に対する公式な投票は、申立後に行われます。申立前に主要な利害関係者とのコンセンサスが形成されているため、申立後の交渉がスムーズに進み、手続期間を大幅に短縮することが期待できます。
これらの手法は、Chapter11がもはや「不意打ちの倒産」だけでなく、事業再編のための戦略的なツールとして計画的に利用されていることを示しています。
事業継続と資金調達
Chapter11を申し立てた企業にとって、最大の課題は「資金繰り」です。事業を継続するためには、従業員への給与、サプライヤーへの支払い、賃料といった日々の運転資金が不可欠です。しかし、申立てによって企業の信用は失墜し、通常の金融市場からの資金調達は事実上不可能となります。この状況を打開するために、連邦倒産法典は、DIPが資金を確保するための2つの特別なメカニズムを用意しています。それが「Cash Collateralの使用」と「DIP Financing」です。
DIPファイナンス(Section 364)とCash Collateralの使用(Section 363)
Cash Collateralの使用:
多くの企業は、運転資金を調達するために、売掛金や在庫を担保に銀行から融資を受けています。この場合、銀行は、売掛金が回収されて得られる現金や在庫の売却代金といった「現金・現金同等物」に対して担保権(Lien)を有しています。このように、担保権の対象となっている現金を「Cash Collateral」と呼びます。 原則として、Chapter11を申し立てたDIPは、Cash Collateralを、たとえ日々の運転資金のためであっても自由に使用することはできません。それは、他人の財産(銀行の担保権益)を使用することに他ならないからです。363条(c)(2)項によれば、DIPがCash Collateralを使用するためには、以下のいずれかが必要となります。
- 担保権者である債権者の同意
- 裁判所の許可
- 追加担保の提供: 申立て後に取得した新たな資産(在庫や売掛金など)に、代替となる担保権(Replacement Lien)を設定する。
- 金銭の定期的支払い: 担保価値の減少分を補うために、定期的に金銭を支払う。
- その他、裁判所が認める同等の保護
DIPファイナンス(DIP Financing):
Cash Collateralだけでは運転資金が不足する場合、DIPは新たに外部から資金を借り入れる必要があります。この、Chapter11手続中に受ける新たな融資を「DIPファイナンス」と呼びます。しかし、通常であれば、既に経営破綻した企業にお金を貸す人はいません。 そこで364条は、この極めてリスクの高い融資を引き受けるDIPレンダー(貸手)に対して、投資の安全性を確保するための、段階的な強力なインセンティブ(スーパー・プライオリティ(超優先権))を与えています。
レベル1:通常の管理費用債権(Section 364(a), (b)): DIPは、裁判所の許可を得て、無担保の融資を受けることができます。この融資に基づく請求権は、第6章で解説した「管理費用債権」として、他の多くの債権に優先する地位を得ます。
レベル2:スーパー・プライオリティ又は無担保資産への担保権(Section 364(c)): もし管理費用債権の地位だけでは貸手が見つからない場合、裁判所はさらに強力な保護を与えることができます。
- スーパー・プライオリティ管理費用債権: 他の全ての管理費用債権よりもさらに優先して弁済される、最優先の請求権。
- 無担保資産への第一順位担保権: 倒産財団に属する資産のうち、まだ誰も担保に取っていない「自由な資産(unencumbered assets)」に対して、第一順位の担保権を設定する。
レベル3:Priming Lien(Section 364(d)): これがDIPレンダーに与えられる究極の保護です。もし自由な資産もなく、レベル2の保護でも貸手が見つからない場合、裁判所は、既に存在する担保権(既存の担保権者のもの)と同順位またはそれよりもさらに優先する、最上位の担保権(Priming Lien)をDIPレンダーに与えることを許可できます。ただし、このプライミング・リエンは、既存の担保権者の権利を直接的に侵害するものであるため、極めて厳格な要件が課されます。DIPは、Priming Lienが設定されたとしても、既存の担保権者が依然として「適切な保護」を受けていることを証明しなければなりません。例えば、担保物の価値が、既存の融資額と新たなDIPファイナンスの合計額を十分に上回っている(エクイティ・クッションがある)ことなどを証明する必要があります。
このDIPファイナンスの確保は、Chapter11の成否を左右する最も重要な要素です。DIPファイナンスが得られなければ、企業は運転資金を失い、事業価値は日々毀損し、再生の道は閉ざされてしまいます。逆に、十分なDIPファイナンスを確保できれば、企業は安定した事業運営を取り戻し、時間をかけて再生計画を練り上げることができるようになります。