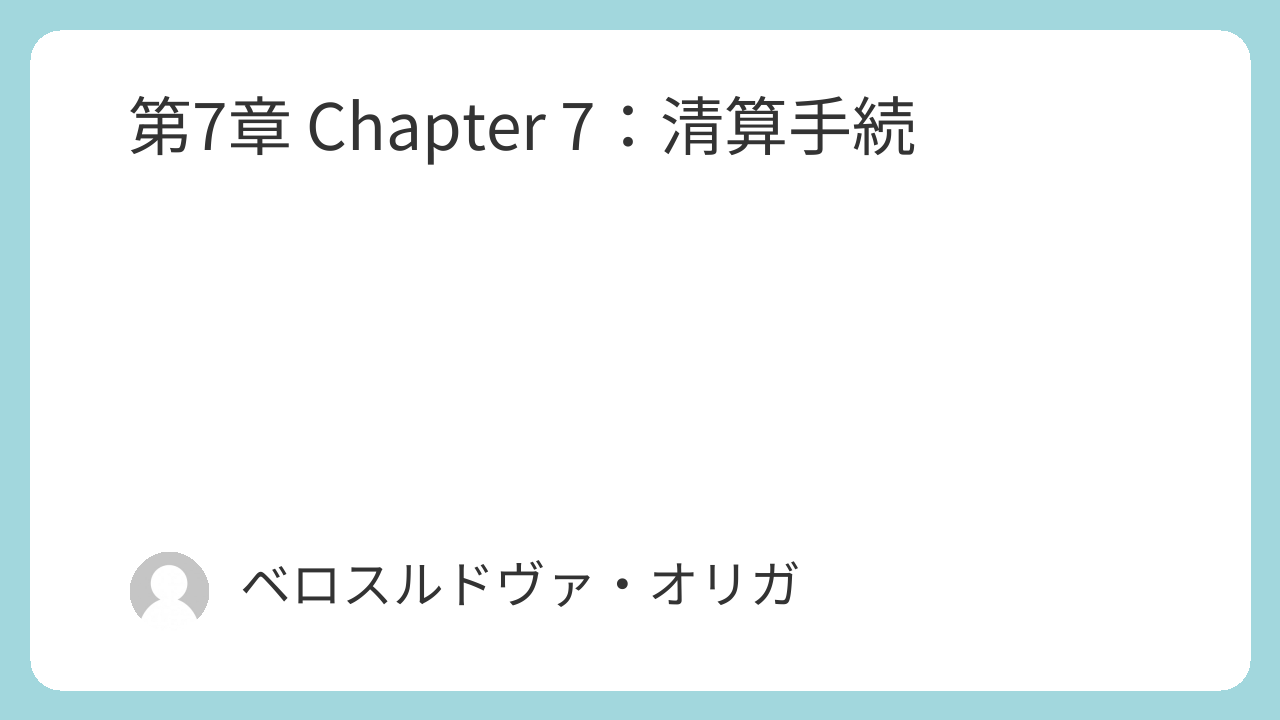Chapter 7は、連邦倒産法典の中で最も基本的かつ古典的な形態の倒産手続であり、「清算(Liquidation)」または「Straight Bankruptcy」として知られています。そのプロセスは、再生を目指すChapter 11の複雑な交渉や計画策定とは対照的です。Chapter 7の目的は、債務者の資産を公平かつ効率的に現金化し、その代金を法が定める優先順位に従って債権者に分配することにあります。
法人にとって、Chapter 7は通常、その事業活動の完全な終焉を意味します。一方、個人債務者にとって、Chapter 7は終わりであると同時に、新たな始まりでもあります。資産(生活に必要な免除財産を除く)を提供するという代償を支払うことで、過去の負債の重荷から解放される「免責(Discharge)」を得て、経済的な「フレッシュスタート」を切るための、最も直接的な道筋なのです。
Chapter 7の目的と流れ
Chapter 7手続の基本的な流れは、以下の通りです。
- 申立てと管財人の選任: 任意申立て又は非任意申立てにより手続が開始されると、連邦管財官は、直ちに民間の弁護士等から構成される管財人パネルの中から、1人の「管財人(Trustee)」を任命します。Chapter 11のDIP(占有継続債務者)制度とは異なり、Chapter 7では常に中立的な第三者である管財人が手続の主導権を握ります。
- 債権者集会: 申立て後、通常20日から40日以内に、債務者、管財人、そして債権者が一堂に会する「債権者集会(Meeting of Creditors)」が開かれます。ここで、管財人や債権者は、債務者に対し、その財産や財務状況について宣誓の上で質問することができます。
- 資産の収集・換価: 管財人は、倒産財団に属する全ての資産(個人の場合は免除財産を除く)を収集し、最も合理的な方法で売却・現金化(換価)します。これには、否認権を行使して申立て前に流出した資産を取り戻す作業も含まれます。
- 配当: 換価によって得られた資金は、第6章で解説した分配の優先順位(管理費用、優先的債権、一般無担保債権の順)に従って、債権者に配当されます。
- 免責: 個人債務者の場合、資産の有無や配当の多寡にかかわらず、免責不許可事由がなければ、裁判所は免責許可決定を下します。これにより、債務者は申立て前の債務の支払義務を免れます。
管財人の選任と役割(資産の換価と配当)
Chapter 7における管財人は、倒産財団の受託者として、手続の成功に不可欠な役割を担います。その職務は多岐にわたりますが、核心部分は「財団の資産を最大化し、それを債権者に公平に分配する」ことにあります。
管財人の主な権限と義務は以下の通りです。
- 調査義務: 債務者の財務状況を徹底的に調査し、提出された書類に虚偽がないか、隠された資産がないかを確認します。
- 資産の収集と管理: 債務者から倒産財団に属する全ての財産を引き継ぎ、管理します。
- 否認権の行使: 第4章で詳述したストロング・アーム条項、偏頗行為否認、詐害的譲渡否認といった強力な権限を行使し、不当に流出した財産を財団に回復させます。
- 資産の換価: 収集した資産を、オークションや相対取引など、最も高い価格で売却できると判断した方法で現金化します。
- 債権の確定: 債権者から提出された債権届出を精査し、不適切なものがあれば異議を申し立てます。
- 分配の実施: 確定した債権に対し、法典の定める優先順位に従って、換価代金を分配します。
- 免責への異議申立て: 債務者に免責不許可事由があると判断した場合には、裁判所に免責に反対する意見を申し立てます。
管財人は、特定の債権者や債務者の利益のためではなく、あくまで倒産財団全体の利益のために行動する、中立かつ独立した存在です。
個人における適用とミーンズテスト(Means Test)
Chapter 7が提供する「フレッシュスタート」は強力な救済策ですが、それは無条件に与えられるものではありません。2005年のBAPCPA改正により、この制度の「濫用」を防ぐため、個人債務者がChapter 7を利用するための資格審査、すなわち「Means Test」が導入されました。その趣旨は、「返済能力があるにもかかわらず、清算型のChapter 7を利用して安易に債務を免れようとする債務者」をふるいにかけ、返済計画を立てるChapter 13手続へと誘導することにあります。
Means Testは、連邦倒産法典707条(b)項に基づき、二段階のプロセスで行われます。
- 第一段階:所得の中央値テスト(Median Income Test)
まず、債務者の「現在の月収(Current Monthly Income)」(申立て前6ヶ月間の平均月収)を、その債務者が居住する州の、同規模世帯の所得の中央値と比較します。- 収入が中央値以下の場合: 原則としてミーンズテストはここで終了し、債務者はChapter 7を利用する資格があるとみなされます。濫用の推定は働きません。
- 収入が中央値を超える場合: 第二段階の、より詳細な計算に進みます。
- 第二段階:可処分所得テスト(Disposable Income Test)
収入が中央値を超える場合、次に、債務者に債務の一部を返済する能力が実質的にあるかどうかを判定します。これは、債務者の「現在の月収」から、法律で定められた各種の「控除可能な生活費」を差し引いて、「可処分所得」を算出する計算です。ここで控除される生活費は、債務者が実際に支出している金額ではなく、国税庁(IRS)が定める全国基準や地域基準に基づいた標準的な金額と、実際の担保付債務(住宅ローンなど)や優先的債務の支払額などが中心となります。 この計算の結果、算出された月間の可処分所得を60倍(5年分)した金額が、法で定める一定の基準額を上回る場合、「濫用の推定(Presumption of Abuse)」が生じます。
この「濫用の推定」が生じた場合、債務者がChapter 7を継続するためには、その推定を覆すだけの「特別な事情(Special Circumstances)」(例えば、深刻な病状や、最近の失業など)が存在することを、証拠をもって裁判所に証明しなければなりません。この証明に失敗した場合、裁判所はそのChapter 7の申立てを棄却するか、あるいは債務者の同意を得て、事件をChapter 13に移行させることになります。
免責(Discharge)
フレッシュスタートの実現
個人債務者にとって、Chapter 7手続の最終目標は、裁判所から「免責許可決定(Order of Discharge)」を得ることです。免責とは、申立て前に存在したほとんどの債務について、債務者の個人的な支払義務を法的に消滅させる、裁判所の命令です。
免責の効力は、連邦倒産法典524条が定める「免責の命令(Discharge Injunction)」によって確保されます。これは、債権者が、免責された債務に関して、訴訟の提起、電話や手紙による請求、給与の差押えといった、いかなる回収行為をも行うことを、永久的に禁止する強力な法的命令です。この差止命令により、債務者は過去の負債の呪縛から完全に解放され、将来の収入を自らの生活再建のために用いることが可能となります。
免責不許可事由と非免責債権
しかし、この強力な免責は、全ての債務者に無条件で与えられるわけではありません。「誠実ではあるが不運な債務者」を救済するという理念に基づき、不誠実な行為を行った債務者に対しては、免責そのものが許可されない場合があります。連邦倒産法典727条は、免責を認めない「免責不許可事由」を列挙しています。主なものとしては、以下のような行為が挙げられます。
- 債権者を害する意図での財産の譲渡、移転、隠匿
- 正当な理由なき、会計帳簿などの財務記録の隠匿、偽造、または不作成
- 倒産手続における、宣誓下での虚偽の陳述(偽証)
- 資産の減少や喪失に関する、合理的な説明の不能
- 裁判所の適法な命令に従うことの拒否
- 過去8年以内に、Chapter 7またはChapter 11で免責を受けていること
これらの事由が1つでも認められれば、債務者は「全ての債務」について免責を得ることができず、破産を申し立てた意味がほとんどなくなってしまいます。
これとは別に、「非免責債権」という概念があります。これは、債務者の行為に問題がなく、全体としての免責が許可された場合でも、特定の種類の債権については、政策的な理由から支払義務が免除されず、倒産手続後も存続するというものです。連邦倒産法典523条に定められた主な非免責債権には、以下のようなものがあります。
- 特定の税金債権
- 詐欺等の不正な手段によって得た金銭や財産に関する債務
- 債権者一覧表に記載しなかった債権
- 扶養義務に関する債務
- 故意または悪意による不法行為によって他者に与えた損害賠償債務
- 飲酒運転等による死亡・傷害に関する損害賠償債務
- 原則として、学生ローン債務
これらの債権は、免責の網の目をすり抜け、債務者は手続終了後もその支払義務を負い続けることになります。Chapter 7は、債務者にとって強力な再起の手段ですが、それは誠実さを前提とし、社会的に保護されるべき特定の債権とのバランスの上に成り立っている制度となっています。