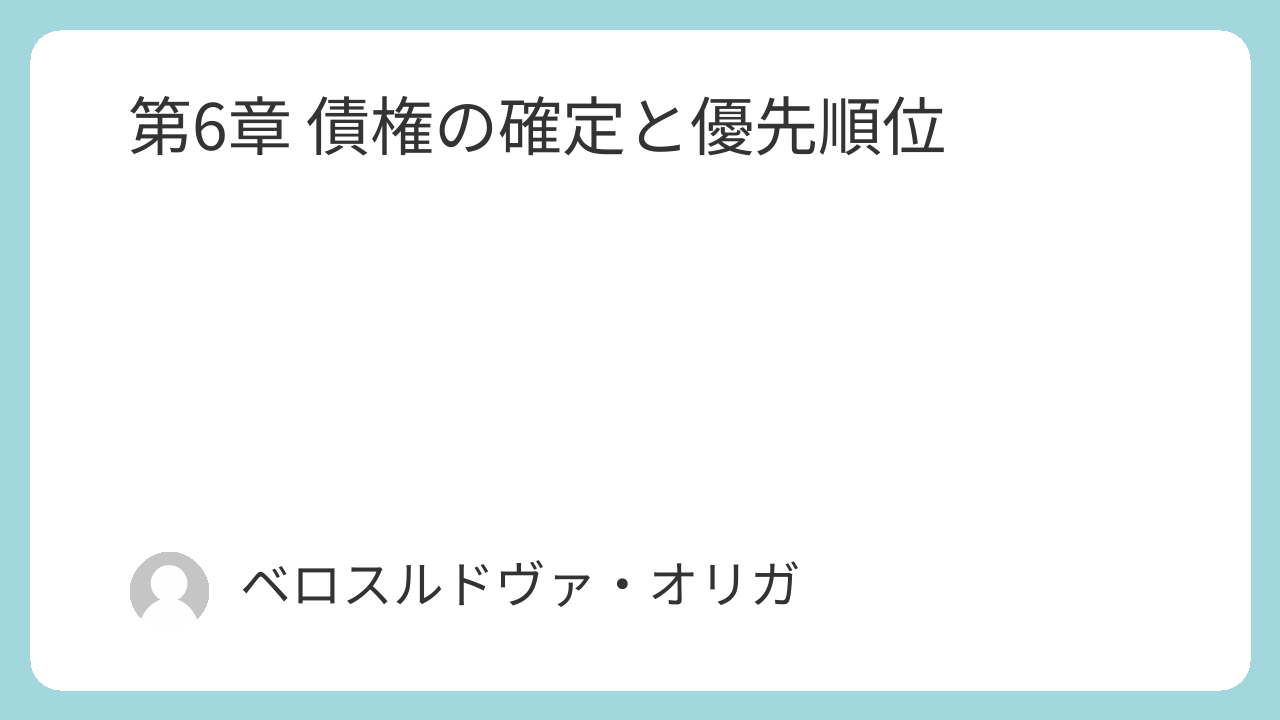倒産手続の核心は、「誰が、何を、どれだけ、そしてどのような順番で受け取るのか」ということです。管財人(またはDIP)が否認権を行使し、資産を売却して形成した倒産財団という限られたパイを、いかにして公平かつ秩序だって分配します。
このプロセスは、2つの大きな段階からなります。第1の段階は、債務者に対して請求権を持つと主張する者が、その権利の内容と金額を法的に確定させる「債権の確定プロセス」です。ここでは、債権者が自らの権利を主張するための「債権届出(Proof of Claim)」という手続が中心となります。第2の段階は、確定した様々な種類の債権を、法が定める厳格なルールに従って分配の順番を決定する「優先順位のルール」です。
さらに本章では、この基本的な分配ルールに対する2つの例外的なメカニズム(①特定の債権者に事実上の優先弁済を許す「相殺権(Setoff)」と、②不正行為を行った債権者の順位を強制的に引き下げる「衡平法上の劣後(Equitable Subordination)」)についても解説します。
債権届出(Proof of Claim)と確定プロセス
債権者が倒産財団からの分配を受けるためには、まず、自らが有効な請求権(Claim)を持っていることを、倒産手続の中で正式に表明する必要があります。このための手続が「債権届出(Proof of Claim)」です。
債権届出書は、債権者が、その債権の発生原因、金額、担保の有無などを記載し、証拠書類を添付して裁判所に提出する書面です。これにより、債権者は「私はこの倒産事件において、これだけの分配を受ける権利があります」と宣言するのです。
- Chapter 7, 12, 13手続: これらの手続では、分配を受けることを望む債権者は、原則として必ず債権届出を行わなければなりません。裁判所が定める期間内(通常は債権者集会の後90日以内)に届出がなければ、その債権者は分配プロセスから除外され、たとえ有効な請求権を持っていたとしても、一銭の配当も受けられなくなってしまいます。
- Chapter 11手続: Chapter 11では、取扱いが少し異なります。債務者が申立て時に提出する負債一覧表に、ある債権が「争いのない(not disputed)」「確定した(liquidated)」「偶発的でない(noncontingent)」ものとして記載されている場合、その債権は法的に届け出られたものと「みなされます」。したがって、その債権者は、一覧表の記載内容(特に金額)に異議がなければ、自ら債権届出を行う必要はありません。しかし、一覧表に記載がない、金額が違う、あるいは「争いあり」と記載されている場合には、自らの権利を守るために、必ず債権届出を行わなければなりません。
債権届出書が提出されると、その債権は、法典上「許可された(allowed)」ものと一応推定されます。つまり、誰も異議を唱えなければ、その債権は記載通りの内容で法的に有効なものとして確定します。しかし、管財人、DIP、債権者等の利害関係者は、その届出に対して「異議(Objection)」を申し立てることができます。異議の理由としては、「州法上、その債務はそもそも無効である」「金額の計算が間違っている」「既に弁済済みである」など様々です。異議が申し立てられた場合、裁判所は審理を開き、その債権を許可すべきか、その金額はいくらが妥当か、といった点について最終的な判断を下します。このプロセスを経て、分配の対象となる各債権の内容が法的に確定していくのです。
債権の種類:担保付債権、無担保債権
担保付債権(Secured Claim)
担保付債権とは、倒産財団に属する特定の財産(担保物、Collateral)に対する有効な担保権(Lien)によって裏付けられた債権です。銀行の不動産に対する抵当権や、機械設備に対する担保権などが典型例です。
担保付債権者は、他のいかなる債権者よりも優先して、その担保物の価値の範囲内で弁済を受ける権利を有します。もし担保物が売却された場合、その売却代金はまず第一にその担保付債権者の弁済に充てられ、残額がなければ他の債権者には回りません。この強力な権利により、担保付債権者は、倒産手続においても比較的安全な地位にいると言えます。
しかし、その権利は万能ではありません。連邦倒産法典第506条(a)項は、重要な原則を定めています。それは、債権が「担保付」とされるのは、あくまで担保物の価値の範囲内に限られるという点です。もし、債権額が担保物の価値を上回っている場合、その債権は2つに分割(bifurcation)されます。
- 担保付債権: 担保物の価値と同額の部分。
- 無担保債権: 債権額のうち、担保物の価値を超過する不足額(deficiency)の部分。
例えば、ある銀行が、評価額700万円の機械設備を担保に、1000万円を貸し付けていたとします。この場合、銀行の1000万円の債権は、700万円の「担保付債権」と、300万円の「無担保債権」に分割されます。銀行は、700万円については担保付債権者として優先的な地位を享受しますが、残りの300万円については、後述する他の多くの無担保債権者と全く同じ立場に置かれることになります。
無担保債権(Unsecured Claim)
無担保債権とは、特定の担保物による裏付けを持たない、その他全ての債権を指します。仕入先に対する買掛金、社債、従業員の給与、賃料、上述の担保価値を超過した部分の債権など、倒産事件における債権の大部分は、この無担保債権に分類されます。これらの債権者は、担保付債権者への支払いが全て完了し、さらに後述する優先的債権への支払いが終わった後に、残った財産があれば、それを債権額に応じて按分比例(pro-rata)で分配されることになります。多くの場合、その配当率は極めて低く、ゼロであることも珍しくありません。
配当の優先順位(Priority Rules)
無担保債権は、全てが横一線で扱われるわけではありません。連邦倒産法典507条は、特定の種類の無担保債権に対し、公共政策上の配慮から、他の一般の無担保債権よりも優先的に弁済を受ける権利を与えています。
507条(a)項が定める主な優先順位は、以下の通りです(上位から順)。
- 扶養義務(Domestic Support Obligations): 離婚に伴う配偶者や子に対する扶養料など。
- 管理費用債権(Administrative Expenses): 実務上、極めて重要な最優先カテゴリーです。管理費用とは、破産申立て後に、倒産財団を維持・管理するために生じた「現実かつ必要」な費用を指します。
- 典型例: 管財人や、財団が雇用した弁護士・会計士等への報酬、申立て後の事業継続に必要な原材料の仕入代金、申立て後の事務所の賃料、申立て後に発生した税金など。
- 趣旨: 最優先の地位を与えることで、専門家や取引先は、倒産した企業と安心して取引をすることができます。もしこの優先順位がなければ、誰もリスクを冒してDIPにサービスや商品を提供しようとはせず、事業再生は不可能になります。
- 非任意申立ての「間隙期」の債権(”Involuntary Gap” Claims): 非任意申立てが行われてから、裁判所が救済命令を出すまでの間に、通常の事業過程で生じた債権。
- 従業員の賃金・給与等(Wages, Salaries, or Commissions): 申立て前180日以内に従業員が稼得した賃金や給与。ただし、1人当たりの上限額が定められています(金額は定期的に調整されます)。
- 従業員退職給付制度への拠出金(Contributions to Employee Benefit Plans): 4の賃金等と同様の期間制限・上限額の範囲内で、従業員のための年金や保険制度への拠出金が優先されます。
- 穀物生産者または漁業者が、破産した穀物貯蔵施設または魚類加工・貯蔵施設に対して有する債権
- 消費者の前払金(Consumer Deposits): 個人が、生活のために商品やサービスを購入するために支払った前払金で、倒産によって商品等が提供されなかったもの。これも1人当たりの上限額が定められています。
- 税金債権(Certain Taxes and Customs Duties): 政府(連邦、州、地方)が有する特定の税金債権。所得税、法人税、源泉徴収税などが含まれます。
これらの優先的債権が、法で定められた順番に従って、全額支払われます。その上で、なお財産が残っている場合に限り、ようやく一般無担保債権者(General Unsecured Creditors)への按分比例での配当が行われます。
相殺権(Setoff)と衡平法上の劣後(Equitable Subordination)
分配の原則には、2つの重要な例外が存在します。
相殺権(Setoff, Section 553)
相殺権とは、二者が互いに金銭債務を負い合っている場合に、それらを対当額で消滅させることができる権利です。例えば、A社がB社に対して100万円の売掛金を持っている一方で、B社から部品を仕入れたことによる80万円の買掛金を負っているとします。この場合、A社は相殺権を行使して、双方の債務を80万円の範囲で消滅させ、B社に対する純粋な20万円の売掛金だけにすることができます。
連邦倒産法典553条は、この州法上の相殺権を、倒産手続においても原則として承認しています。これは、相殺権を持つ債権者に対して、事実上、担保権にも似た強力な保護を与えることを意味します。上記の例でB社が破産した場合、もし相殺が認められなければ、A社はB社に対する80万円の買掛金を全額支払わなければならない一方で、B社から回収できる100万円の売掛金は、一般無担保債権として、わずかな配当しか期待できないかもしれません。しかし、相殺が認められることで、A社は実質的に80万円の債権を100%回収したのと同じ経済的効果を得ることができます。
ただし、倒産法はこの強力な権利に一定の制約を課しています。まず、自動的停止により、申立て後は裁判所の許可なく一方的に相殺を行うことはできません。また、管財人は、申立て前90日間の相殺をチェックし、その相殺によって債権者の地位が不当に改善された(例えば、破綻直前に債務者に預金をさせて相殺したなど)と認められる場合には、その改善分を取り戻すことができます。
衡平法上の劣後(Equitable Subordination, Section 510(c))
衡平法上の劣後とは、裁判所が、衡平法(Equity)の原則に基づき、特定の債権者の請求権の優先順位を同順位または下位の他の債権よりも意図的に引き下げることを命じる救済措置です。これは、法律の条文に明確な違反がなくとも、その債権者の「不正な行為(inequitable conduct)」によって他の債権者が不当な損害を被った場合に適用される、裁判官による裁量的な是正措置です。
この制度が最も頻繁に適用されるのは、債務者企業の経営を支配していた役員や株主といった「インサイダー」に対する債権です。例えば、インサイダーが、会社を私物化して不当な利益を得たり、会社の経営危機を知りながら自らの債権だけを有利な担保付債権に切り替えたり、又は他の債権者を欺くような行為をしたりした場合、裁判所はそのインサイダーの債権を他の一般無担保債権よりもさらに後順位に劣後させることができます。これにより、不正行為を行ったインサイダーは、他の誠実な債権者への分配が全て終わるまで、一切の配当を受けられなくなります。