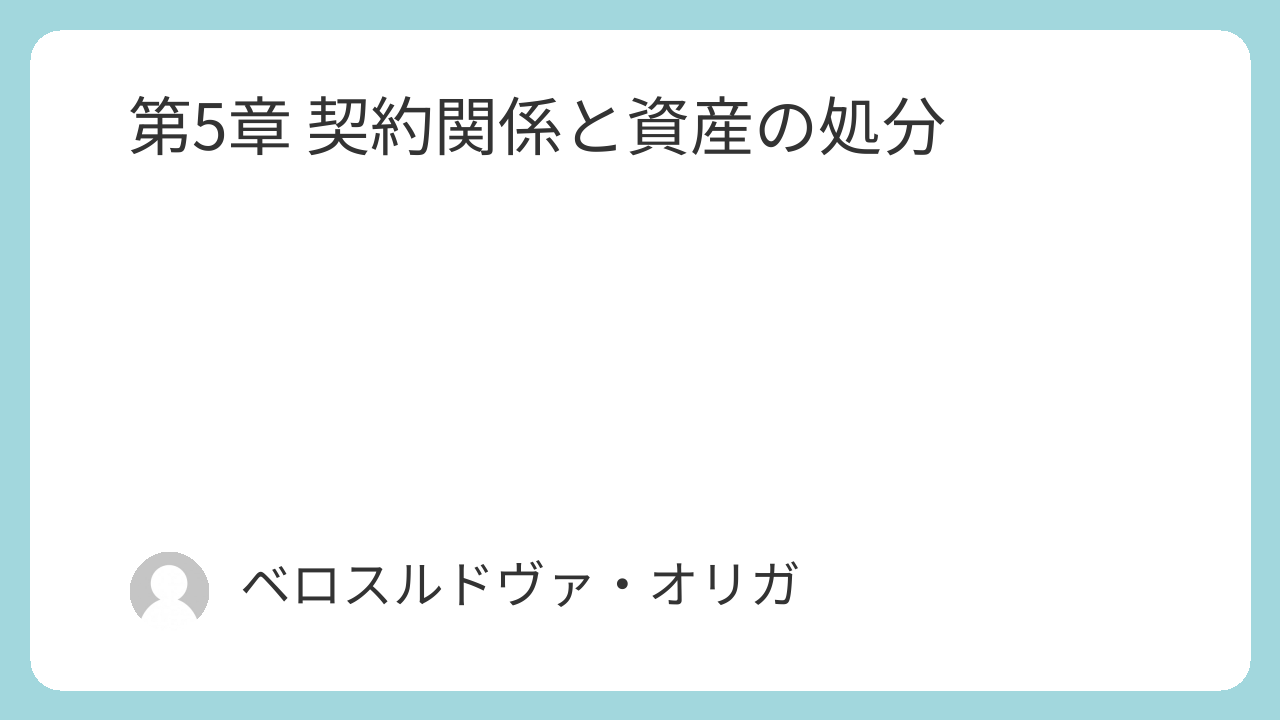倒産した企業の価値は、工場や在庫といった目に見える有形資産だけではありません。むしろ、その真の価値の多くは、サプライヤーとの供給契約、顧客との販売契約、不動産の賃貸借契約、技術のライセンス契約といった、無数の契約関係の中にあります。事業の再建を目指すChapter 11手続においては、これらの契約関係の中から価値あるものを維持し、不採算なものを切り離す作業が、再生の成否を分ける鍵となります。また、清算を目指すChapter 7手続においても、資産を個別に売却するよりも、有利な契約と共に事業の一部を一体として売却する方が、より高い価値を生み出すことが多いです。
このように、倒産財団の価値を最大化するという共通の目標に向かって、契約関係と物理的な資産を柔軟に管理・処分するために、連邦倒産法典は2つの極めて強力なツールを管財人(またはDIP)に与えています。1つは、365条が定める「未履行双務契約および未了リース(Executory Contracts and Unexpired Leases)」の取扱権限であり、もう1つは、363条が定める「財団財産の使用・売却・リース(Use, Sale, or Lease of Property)」の権限です。
未履行双務契約および未了リース(Executory Contracts and Unexpired Leases, Section 365)
連邦倒産法典第365条は、管財人またはDIPに対し、申立て時点で存在する「未履行双務契約」と「未了リース」の運命を、倒産財団にとって最も有利になるように決定する、広範な裁量権を与えています。
「未履行双務契約」とは何か
法典自体には「未履行双務契約(Executory Contract)」の明確な定義はありません。しかし、裁判所や実務家の間で広く受け入れられているのは、ヴァーン・カントリーマン教授が提唱した、いわゆる「Countryman Test」です。これによれば、未履行双務契約とは、「債務者と相手方の双方の義務が、いずれか一方の当事者がその義務の履行を怠れば、それが相手方の履行義務を免除すべきほどの重大な契約違反(material breach)となる程度に、未だ履行されていない契約」を指します。
少し分かりにくい定義ですが、要するに「双方にとって、まだやるべき重要なことが残っている契約」と考えると分かりやすいでしょう。
- 典型例:
- 長期供給契約: サプライヤーには今後も商品を供給する義務があり、債務者にはその代金を支払う義務があります。
- 不動産賃貸借契約: 家主には物件を使用させる義務があり、債務者(借主)には賃料を支払う義務があります。
- ソフトウェア・ライセンス契約: ライセンサーにはライセンスを提供し続ける義務があり、債務者(ライセンシー)にはライセンス料を支払う義務があります。
- 非該当例:
- 金銭消費貸借契約: 貸主は既に金銭を貸し付けており、残っているのは債務者の返済義務だけです。これは双務的ではなく片務的な義務しか残っていないため、未履行双務契約には該当しません。
この区別は重要です。なぜなら、365条が与える特別な選択権は、この「未履行双務契約」にのみ適用されるからです。
債務者の選択権:引受(Assumption)、拒絶(Rejection)、譲渡(Assignment)
管財人またはDIPは、裁判所の承認を得て、各々の未履行双務契約について、以下の3つの選択肢の中から1つを選ぶことができます。この判断は、純粋に財団の利益になるかどうかという「経営判断(Business Judgment)」基準に基づいて行われます。
- 引受(Assumption):
意味: 倒産財団が、その契約を今後も継続し、その契約上の全ての義務を引き継ぐことを選択することです。これは、その契約が財団にとって有益である(例えば、市場価格より安い賃料のリース契約や、有利な条件の供給契約など)と判断した場合に行われます。
要件: 契約を引受けるためには、管財人/DIPは以下の2つの条件を満たさなければなりません。- 不履行の解消(Cure): 申立て時点で存在していた金銭的な不履行(賃料の滞納など)を全て解消し、非金銭的な不履行も解消しなければなりません。
- 将来の履行に関する適切な保証(Adequate Assurance of Future Performance): 将来にわたって契約上の義務をきちんと履行できることを、相手方に対して合理的に保証する必要があります。単なる口約束では不十分であり、具体的な財務計画などを示すことが求められます。
効果: 引き受けられた契約は、倒産財団の正式な資産・負債となります。その結果、引受後に発生する契約上の義務(賃料の支払いなど)は、倒産手続上の費用として極めて優先順位の高い「管理費用債権(Administrative Expense Claim)」として扱われます。
- 拒絶(Rejection):
意味: 財団が、その契約の履行を放棄し、契約関係から離脱することを選択することです。これは、その契約が財団にとって不採算である(例えば、市場価格より高い賃料のリース契約や、赤字の事業に関する契約など)と判断した場合に行われます。
効果: 契約の拒絶は、法律上、「破産申立ての直前における契約違反」とみなされます。これにより、契約の相手方は、契約違反によって生じた損害(将来得られたはずの利益など)の賠償を請求する権利を得ます。しかし、この損害賠償請求権は、優先順位の低い「一般無担保債権」として扱われます。つまり、DIPは、将来にわたる高額な支払義務を、わずかな配当で済む可能性のある一般無担保債権へと転換させることができるのです。これは、不採算事業から撤退し、バランスシートを改善するための強力なツールとなっています。 - 引受と譲渡(Assumption and Assignment):
管財人・DIPは、有利な契約を自ら引き受けて利用するだけでなく、それを第三者に売却(譲渡)して現金化することもできます。例えば、周辺相場より著しく安い賃料の長期リース契約は、それ自体が価値のある資産です。管財人/DIPは、まずそのリース契約を(不履行を解消した上で)引受け、次にその契約を第三者に譲渡し、譲渡対価(プレミアム)を倒産財団の収入とすることができます。この場合も、譲受人(新たな借主)は、家主に対して将来の履行に関する適切な保証を提供する必要があります。
Ipso Facto条項(倒産解除条項)の無効
多くの契約書には、「契約当事者の一方が破産を申し立てた場合、本契約は自動的に解除される」といった趣旨の条項(いわゆる「Ipso Facto条項」または倒産解除条項)が含まれています。もしこの条項が有効であれば、企業がChapter 11を申し立てた瞬間に、事業に必要なリース契約や供給契約が全て失われ、事業再生の道は即座に閉ざされてしまうでしょう。
そこで連邦倒産法典365条(e)項は、このようなIpso Facto条項を原則として無効と定めています。これにより、債務者は、破産を申し立てたという事実だけを理由に、有利な契約を一方的に解除されることから保護されます。これは、債務者に再建の機会を実質的に保障するための、極めて重要な規定です。
知的財産ライセンス契約の特則
365条には、知的財産(特許、著作権など)のライセンス契約に関して、特別な保護規定が設けられています。もし、ライセンサー(ライセンスを与える側)である債務者が、ライセンス契約を「拒絶」した場合、ライセンシー(ライセンスを受ける側)である相手方は、突然事業の基盤となる技術を使えなくなり、深刻な打撃を受ける可能性があります。
この事態を避けるため、365条(n)項は、ライセンシーに対して特別な選択権を与えています。ライセンサーである債務者が契約を拒絶した場合でも、ライセンシーは、契約を終了させる代わりに、契約期間が満了するまでその知的財産を使用し続ける権利を保持することを選択できるのです。ただし、この権利を保持するためには、ライセンシーは契約で定められたライセンス料を支払い続けなければなりません。この規定は、他者の技術に依存して事業を行っている企業が、ライセンサーの倒産によって不意に事業基盤を奪われることを防ぐ、重要なセーフガードとなっています。
資産の売却(Section 363 Sale)
363条は、倒産財団に属する財産の使用、売却、リースに関するルールを定めています。特に、同条が認める資産売却の仕組みは、現代のChapter 11実務において、伝統的な再生計画に代わる、迅速かつ効率的な事業再生・売却手法として、中心的な地位を占めるようになっています。
事業再生手法としての363条売却の実務
かつてのChapter 11は、債務者自身が時間をかけて再生計画を策定し、債権者の投票を経て認可を得るというプロセスが主流でした。しかし、このプロセスは時間がかかり、コストも高く、事業価値が劣化するリスクも伴います。そこで、より迅速に事業の価値を確定し、売却するために広く用いられるようになったのが、「363条売却」です。
これは、Chapter 11手続の早期段階で、会社の事業全体または主要部分を「事業継続体(Going Concern)」として売却してしまう手法です。その典型的なプロセスは以下の通りです。
- マーケティングと入札者の選定: DIPは、投資銀行などと協力し、売却対象となる事業や資産の買い手候補を探します。
- ストーキング・ホースの決定: 複数の候補者の中から、最も有利な条件を提示した者を「Stalking Horse」と呼ばれる最初の入札者として選定し、資産売買契約を締結します。この契約は、その後のオークションにおける最低売却価格と基本条件(「フロア」)を設定する役割を果たします。Stalking Horseは、そのリスクと引き換えに、最終的に他の入札者に敗れた場合の費用補償(ブレークアップ・フィー)などの保護を与えられることが多いです。
- 入札手続の承認: DIPは、Stalking Horseとの契約内容と、今後の公開入札(オークション)のルールを定めた「入札手続(Bidding Procedures)」を裁判所に提出し、その承認を求めます。
- オークションの実施: 裁判所の承認後、他の潜在的な買い手も参加できるオークションが実施されます。オークションでは、Stalking Horseが設定した価格を上回る、より高い価格での入札が競われます。
- 売却の承認: オークションの結果、最も高額かつ有利な条件を提示した「落札者(Winning Bidder)」が決定されます。最終的に、DIPは裁判所に対して、この落札者への資産売却を承認するよう求めます。裁判所は、売却が公正なプロセスを経て行われ、財団にとって最高の価値が実現されたと判断すれば、売却を承認する命令を発します。
この手法により、事業は倒産手続の煩雑さから切り離され、新たな所有者の下で迅速に再出発することが可能となります。
「自由かつ明確な(Free and Clear)」売却と買主の保護
363条売却がこれほど強力なツールとなっている最大の理由は、363条(f)項が、資産を「あらゆる権利・利益から自由かつ純粋な(free and clear of any interest)」状態で売却することを認めている点にあります。
これは、売却対象となる資産に付着していた、あらゆる担保権(Lien)、債権者の請求権、その他の権利(Interest)が、売却によって全て洗い流され、消滅することを意味します。そして、これらの消滅した権利は、資産そのものではなく、その資産の「売却代金(Proceeds)」に付着することになります。
例えば、ある工場に複数の銀行が抵当権を設定していたとしても、363条売却が承認されれば、買主はそれらの抵当権が一切付いていない、まっさらな状態の工場を取得することができます。銀行の抵当権は、工場から切り離され、代わりにその工場の売却代金に対して主張することになります。
この「権利の洗浄効果」は、買主にとって絶大な魅力です。将来、過去の債務を巡る紛争に巻き込まれるリスクがないため、安心して高い価格を提示することができます。これが、363条売却が倒産財団の価値を最大化する上で極めて有効な理由です。
さらに、第363条(m)項は、善意の買主を保護するための強力な規定を置いています。たとえ、売却承認命令が後に上級審で覆されたとしても、買主が「善意(good faith)」であった限り、その売却の有効性自体は影響を受けません。この規定は、売却の「最終性(Finality)」を確保し、買主が安心して取引を完了できるようにすることで、入札への参加意欲を高める重要な役割を果たしています。