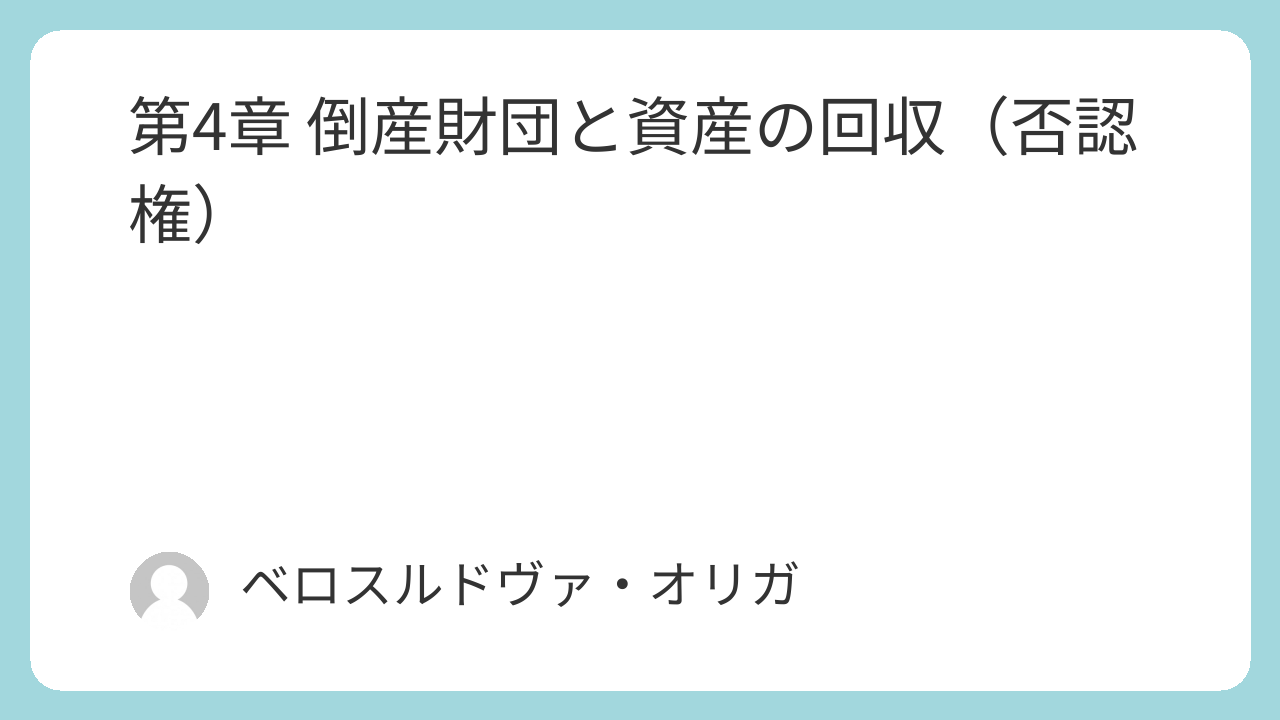破産申立てによる自動的停止の次に焦点となるのは、債権者への分配の原資となるべき資産、すなわち「倒産財団(Bankruptcy Estate)」の形成です。倒産法は、この財団を、債権者全体の利益のために集められ、管理され、最終的に分配されるべき1つの共有財産として捉えます。この財団が大きければ大きいほど、各債権者が受け取る分配も多くなります。したがって、倒産手続における中心的な活動の1つは、この財団の範囲を確定し、その価値を最大化することです。
この資産最大化のプロセスは、2つの段階に分けられます。第一段階は、破産申立ての瞬間に債務者が有していた全ての財産を特定し、1つの集合体として把握することです。第二段階は、よりダイナミックなプロセスであり、申立て前に債務者の手から不当に流出してしまった財産を、管財人(またはDIP)が法典上の特別な権限を行使して取り戻す、資産の「回収」作業です。この強力な回収権限が「否認権(Avoidance Powers)」と呼ばれるものです。
倒産財団(Bankruptcy Estate)の範囲
財団を構成する財産(Property of the Estate, Section 541)
連邦倒産法典541条(a)(1)項は、倒産財団の出発点を定義する、極めて広範かつ包括的な規定です。同条項によれば、倒産財団は「申立てが開始された時点における、財産に関する債務者の全ての法的または衡平法上の利益(all legal or equitable interests of the debtor in property as of the commencement of the case)」から構成されます。
この定義の鍵となるのは、その圧倒的な「広さ」です。財産の種類、所在地、あるいは債務者がそれを占有しているか否かを問いません。
- 有形資産: 不動産、工場設備、在庫商品、現金といった物理的な資産はもちろん財団に含まれます。
- 無形資産: 売掛金、知的財産権(特許権、著作権、商標権)、契約上の権利、さらには債務者が第三者に対して有する訴訟上の請求権(causes of action)といった無形の資産も、全て財団の一部となります。
- 衡平法上の利益: 例えば、債務者が信託の受益者として有する利益なども含まれます。
重要なのは、「申立てが開始された時点(as of the commencement of the case)」という時間的な区切りです。この瞬間、債務者の財産に関するスナップショットが撮られ、それが倒産財団の基本的な構成要素となります。この「時点」の前後で、財産の帰属は劇的に変化します。申立て前に債務者が稼いだ給料は財団に属しますが、申立て後に個人債務者が提供した労働の対価として得る将来の給料は、原則として財団に含まれず、債務者のフレッシュスタートの原資となります。
ただし、この時間的な区切りにはいくつかの重要な例外があります。例えば、申立て後180日以内に、債務者が遺産相続、離婚に伴う財産分与又は生命保険金によって財産を取得した場合、その財産は「後から取得した財産」として倒産財団に組み入れられることが定められています。
このようにして形成された倒産財団は、もはや債務者個人のものではなく、管財人(またはDIP)が全ての債権者の利益のために管理・処分する、1つの独立した法的な集合体となります。
管財人(またはDIP)の否認権(Avoidance Powers)
倒産財団は、申立て時点の債務者の財産だけで構成されるわけではありません。もしそうであれば、支払不能に陥る直前の債務者が、特定の気に入った債権者にだけ借金を返済したり、親族に財産を贈与したり、あるいは資産を不当に安い価格で売却したりすることを、野放しにしてしまうことになります。このような行為は、他の全ての債権者を害し、倒産法が目指す「債権者間の公平な分配」という大原則を根底から覆すものです。
そこで連邦倒産法典は、管財人(またはChapter 11におけるDIP)に対し、このような申立て前の特定の取引の効力を「否認」し、流出した財産を倒産財団に回復させるための、一連の強力な権限を与えています。これが「否認権(Avoidance Powers)」です。否認権の行使は、過去に遡って取引を無効にし、財産を受け取った相手方(被否認者)から、その財産またはその価値に相当する金銭を取り戻すことを可能にします。以下、主要な否認権について解説します。
ストロング・アーム条項(Strong-arm Clause, Section 544)
第544条(a)項、通称「ストロング・アーム条項」は、管財人に、現実には存在しない「仮想的」な地位を与え、その地位から一部の権利を無効化する強力な権限です。この条項の下で、管財人は以下の3つの仮想的な人格を併せ持つことになります。
- 司法上の担保権者(Judicial Lien Creditor): 申立ての瞬間に、債務者に対して債権を取得し、その債権に基づき債務者の財産に対する司法上の担保権(判決に基づく差押えなど)を得た、仮想的な債権者。
- 執行手続を完了した債権者(Creditor with an Execution Returned Unsatisfied): 債務者に対する判決を得て強制執行を試みたが満足を得られなかった、仮想的な債権者。
- 不動産の善意購入者(Bona Fide Purchaser of Real Property): 申立ての瞬間に、債務者から不動産を、取引の対価を支払い、かつ他の権利の存在を知らない「善意」で購入した、仮想的な買主。
この仮想的な地位が最も威力を発揮するのは、担保権の対抗要件の不備(Unperfected Security Interest)を攻撃する場面です。アメリカの各州法(主に統一商事法典(UCC)や不動産登記法)は、貸付銀行などが設定した担保権を第三者に対抗(主張)するためには、UCCファイナンシング・ステートメントの登記や、不動産抵当権の登記といった「対抗要件具備(Perfection)」の手続を要求しています。
もし、ある銀行が債務者の機械設備に担保権を設定しながら、その登記を怠っていたとします。この銀行の担保権は、債務者との間では有効かもしれませんが、登記という公示方法を経ていないため、第三者に対しては主張できない不完全な状態にあります。ここにストロング・アーム条項が登場します。管財人は、「申立ての瞬間に登場した司法上の担保権者」という仮想的な地位に基づき、「私はあなたの登記されていない担保権の存在を知らなかった第三者です。したがって、州法上、あなたの不完全な担保権は私の司法上の担保権に劣後します」と主張することができます。
この主張が認められると、銀行の担保権は否認され、その効力を失います。その結果、この銀行は、担保物から優先的に弁済を受けることができる「担保付債権者」の地位から、他の多くの債権者と同じ立場で按分比例の配当しか受けられない「一般無担保債権者」へと転落してしまいます。そして、本来であれば銀行の担保となっていたはずの機械設備は、無担保の財産として倒産財団に組み込まれ、全ての無担保債権者への分配の原資となります。管財人自身が、申立て前にその担保権の存在を現実に知っていたかどうかは、全く関係がありません。あくまで「仮想的」な地位に基づく、法律上の擬制なのです。
偏頗行為否認(Preferences, Section 547)
債務者が経済的に破綻し始めると、一部の勘の良い債権者は、他の債権者に先んじて自らの債権だけでも回収しようと、債務者に支払いを強く迫ることがあります。債務者側も、重要な取引先や、個人的な関係のある債権者に対してだけは、支払いを続けたいと考えるかもしれません。このような、破産申立て直前の「駆け込み的な弁済」や「えこひいき的な支払い」を「偏頗行為(または偏頗弁済、Preference)」と呼びます。
偏頗行為は、債権者平等の原則に真っ向から反します。そこで547条は、管財人がこのような不公平な財産移転を否認し、支払われた金銭を倒産財団に取り戻すことを認めています。管財人が偏頗行為として取引を否認するためには、以下の6つの要件を全て証明しなければなりません。
- 債務者の財産上の利益の移転であること(a transfer of an interest of the debtor in property)
- 債権者の利益のためになされたものであること(to or for the benefit of a creditor)
- 先行する債務(antecedent debt)の弁済としてなされたものであること(つまり、商品の購入と同時に代金を支払うような同時履行の取引ではなく、過去に発生した借金の返済などであること)
- 債務者が支払不能(insolvent)の時に行われたこと(なお、申立て前90日間の期間内においては、債務者は支払不能であったと法的に「推定」されるため、管財人の証明責任は大幅に軽減されま)
- 申立て前90日以内に行われたこと(ただし、支払いの相手方が、債務者の親族や会社の役員といった「インサイダー(insider)」である場合は、この否認対象期間(look-back period)が1年に延長されます)
- その移転によって、当該債権者が、もしその移転がなされずにChapter 7手続で配当を受けた場合よりも、多くのものを得ることになること(これは、実質的に、無担保債権者が元々の債権額の100%に近い弁済を受けた場合などに満たされます)
これらの要件を満たす典型例は、債務者が破産申立ての1ヶ月前に、複数の無担保の取引債権者の中から1社にだけ、売掛金全額を現金で支払ったようなケースです。
もっとも、申立て前90日間の全ての支払いが否認対象となるわけではありません。547条(c)項は、通常の商取引を保護するため、いくつかの重要な抗弁事由(否認権の例外)を定めています。最も頻繁に主張されるのは以下の3つです。
- 同時的対価交換(Contemporaneous Exchange for New Value): 弁済と引き換えに、同等の新しい価値が債務者に提供された場合。例えば、商品代引き(C.O.D.)での支払いは、先行債務の弁済ではないため、そもそも偏頗行為に当たりません。
- 通常の取引過程における弁済(Ordinary Course of Business): これが最も重要な抗弁です。支払いが、(i) 債務者と当該債権者間の過去の取引慣行に照らして通常の時期・方法で行われ、かつ、(ii) 業界全体の標準的な取引慣行から見ても逸脱していないと証明できれば、その支払いは否認されません。例えば、毎月請求書発行後30日以内に支払うという慣行が定着していたのであれば、その通りの支払いは保護される可能性が高いです。
- 事後的新規価値の提供(Subsequent New Value): 偏頗的な支払いを受けた後で、その債権者が、担保を取ることなく、さらに新たな商品やサービスを債務者に提供した場合。その新規価値の提供分を、先に受けた偏頗弁済額から控除することが認められます。
詐害的譲渡の否認(Fraudulent Transfers, Section 548)
詐害的譲渡の否認は、債務者が債権者を害する意図をもって、あるいは客観的に見て不当に安い価格で資産を処分した場合に、その取引を取り消して財産を回復させる制度です。偏頗行為が「債権者間の公平」を害する行為を対象とするのに対し、詐害的譲渡は「債務者の財産そのものを不当に減少させる」行為を対象とします。548条は、2つのタイプの詐害的譲渡を規定しています。
- 現実的詐害(Actual Fraud): 債務者が、「債権者を妨害し、遅延させ、または欺罔する現実の意図(actual intent to hinder, delay, or defraud)」をもって財産を移転した場合です。債務者の主観的な「悪意」が要件となります。しかし、債務者が心の中の意図を自白することは稀であるため、裁判所は、客観的な状況証拠、いわゆる「詐害性の兆候(badges of fraud)」からその意図を推認します。例えば、(i) 財産をインサイダー(親族や関連会社)に譲渡した、(ii) 譲渡後も債務者がその財産の使用・占有を継続している、(iii) 取引が秘密裏に行われた、(iv) 訴訟を提起された直後に財産を処分した、といった事情が複数存在すれば、現実的詐害の意図が認定されやすくなります。
- 擬制的詐害(Constructive Fraud): こちらは、債務者の主観的な意図を問いません。取引の経済的実質が客観的に見て債権者を害するものであれば、詐害的譲渡とみなされます。管財人は、以下の2つの要素を証明する必要があります。
- (A) 不当な対価: 債務者が、その移転と引き換えに「合理的に等価な価値(reasonably equivalent value)」を受け取らなかったこと。無償での贈与はもちろん、市場価格から著しく低い価格での売却などがこれに該当します。
- (B) 劣悪な財務状況: 上記の不当な対価での取引が行われた時点で、債務者が、(i) 支払不能であった、(ii) 取引後に不合理に僅かな資本しか残されなかった、または (iii) 返済不能な額の負債を負担しようとしていた、といういずれかの財務的窮境にあったこと。
例えば、債務者が支払不能状態にありながら、所有する時価1000万円の土地を、息子に100万円で売却したようなケースは、擬制的詐害の典型例です。
なお、548条の否認対象期間は、申立て前2年です。しかし、管財人は、544条(b)項を通じて、各州が定める詐害的譲渡法(Uniform Voidable Transactions Actなど)を利用することもできます。州法は、連邦倒産法よりも長い否認対象期間(例えば4年)を定めていることが多く、管財人はより有利な法律を選択して、さらに過去に遡って取引を否認することが可能です。