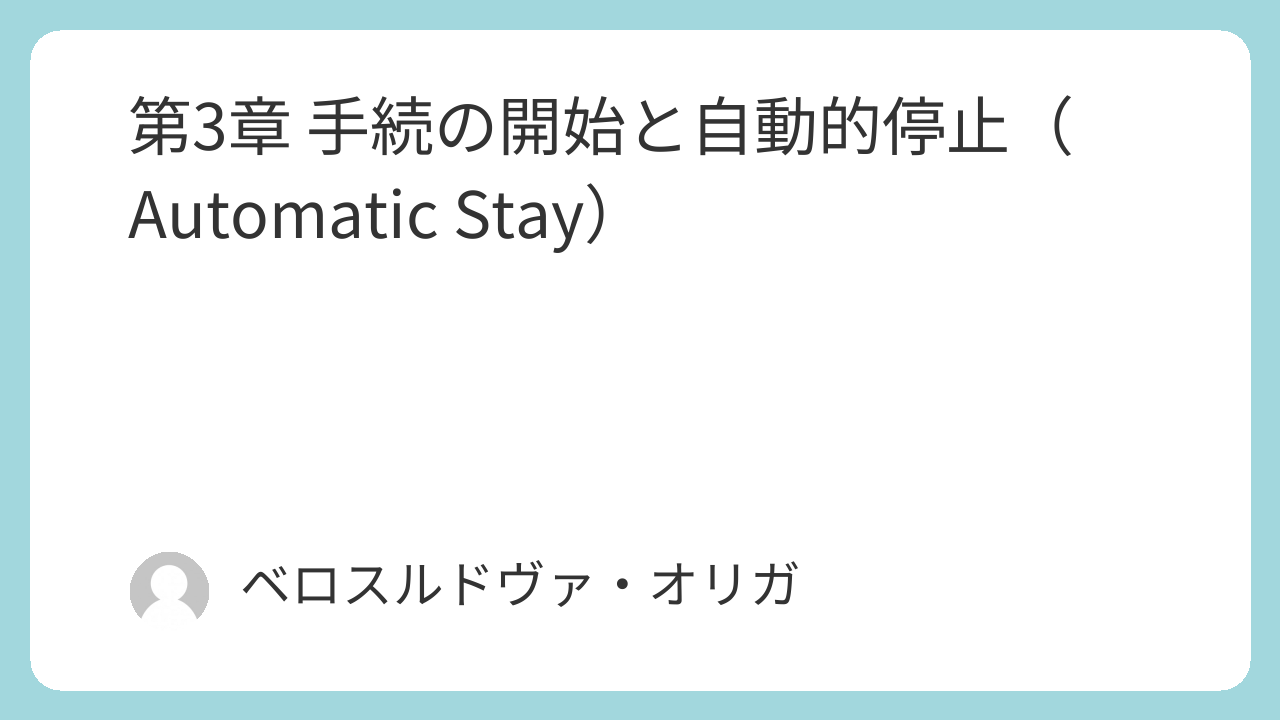「破産申立て(Filing of a Petition)」により破産手続が開始します。それと同時に、全ての債権者の動きをその場で停止させる「自動的停止(Automatic Stay)」が、債務者とその財産(倒産財団)機能します。
破産申立て(任意申立てと非任意申立て)
アメリカの倒産手続は、倒産裁判所に「申立書(Petition)」を提出することによって開始されます。これは、債務者が自らの意思で行うことも、一定の要件を満たした債権者が強制的に行うことも可能です。
任意申立て(Voluntary Cases)
倒産事件の圧倒的多数は、債務者自らが申立書を提出する「任意申立て」によって開始されます。連邦倒産法典301条(Section 301)は、利用を希望するチャプターの下で債務者となる資格のある者であれば、誰でも任意申立てを行うことができると定めています。
重要なのは、任意申立てを行うにあたり、債務者は「支払不能(Insolvent)」であることを証明する必要がないという点です。理論上は、資産が負債を上回っている(支払能力がある)状態でも、将来の資金繰りの悪化を見越して、任意申立てを行うことが可能です。申立書が裁判所に提出されたその瞬間、裁判所の判断を待つまでもなく、自動的に「救済命令(Order for Relief)」が発せられたとみなされ、直ちに倒産手続が開始し、自動的停止の効力が発生します。
もっとも、申立ては単に申立書一枚を提出すれば完了するわけではありません。債務者は申立てと同時に、あるいはその直後に、自らの財務状況を詳細に開示する一連の書類を提出する義務を負います。これには、資産と負債の一覧表(Schedules of Assets and Liabilities)、収入と支出の一覧表、財務状況報告書(Statement of Financial Affairs)、全ての債権者の氏名・住所・債権額を記載した債権者一覧表(Mailing List or Matrix)などが含まれます。これらの書類は、管財人や債権者が債務者の財産状況を正確に把握し、手続を適正に進めるための基礎情報となる、極めて重要なものです。
非任意申立て(Involuntary Cases)
「非任意申立て」は、債務者が支払不能状態にありながらも、資産を隠匿したり、特定の債権者にだけ不公平な弁済(偏頗弁済)を行ったりしている場合に、債権者が強制的にその債務者を倒産手続のテーブルに着かせるための制度です。
しかし、債務者の意思に反して手続を強制する強力な手段であるため、その利用には連邦倒産法典303条(Section 303)の下で厳格な要件が課されています。
- 対象チャプターの限定: 非任意申立てが可能なのは、清算手続であるChapter 7と、再建手続であるChapter 11に限られます。Chapter 13のような個人の返済計画型手続を強制することはできません。
- 申立債権者の要件:
- 債務者の債権者総数が12名以上の場合、合計で一定額(インフレに応じて定期的に調整)以上の無担保債権を有する、3名以上の債権者が共同で申立てを行う必要があります。
- 債権者総数が12名未満の場合は、一定額以上の無担保債権を有する、1名の債権者だけで申立てが可能です。
- 申立ての根拠: 申立債権者は、申立ての根拠として、以下のいずれかを証明しなければなりません。
- 債務者が、その債務の支払期日が到来しているにもかかわらず、一般的にその支払を行っていないこと(generally not paying such debtor’s debts as they become due)。これは非任意申立てにおける最も重要な要件であり、「支払不能」の倒産法上の定義の一つです。単にいくつかの債務の支払いが遅れているだけでは不十分で、債務の数、金額、滞納期間などを総合的に考慮し、「全般的に」支払いが滞っている状態であることが求められます。
- 申立て前の120日以内に、債務者の資産の全部または実質的に全部の管理を目的として、管財人等が選任されていること。
任意申立てと異なり、非任意申立てでは、申立書が提出されても直ちに救済命令が発せられるわけではありません。債務者には、申立てに対して反論し、争う機会が与えられます。債務者が異議を申し立てた場合、裁判所は審理を開き、申立債権者が上記の要件を満たしているかを判断します。審理の結果、裁判所が要件を満たしていると判断して初めて、救済命令が発せられ、本格的な倒産手続が開始されます。
もし、裁判所が申立てを棄却した場合、申立てを行った債権者は、債務者が受けた損害(弁護士費用や逸失利益など)を賠償する責任を負う可能性があります。さらに、申立てが悪意(bad faith)で行われたと認定された場合には、懲罰的損害賠償を命じられるリスクもあります。
自動的停止(Automatic Stay)
自動的停止の強力な効力と目的
自動的停止の目的は2つあります。第1に、債務者側の視点から、絶え間ない債権者からの取立圧力から解放し、自らの状況を冷静に評価し、再建への道を模索するための「呼吸を置く期間(breathing spell)」を与えることです。第2に、債権者側の視点から、個々の債権者による抜け駆け的な債権回収行為(いわゆる「早い者勝ち」)を禁止し、全ての債権者が倒産手続という統一されたプラットフォームの下で、公平な分配を受ける機会を保障することです。これにより、倒産財団の資産の散逸を防ぎ、その価値を最大化することが可能となります。
その名の通り、この停止命令は「自動的」に、申立ての瞬間に発効します。裁判所が個別に命令を発する必要も、債権者に通知が到達する必要もありません。法律の規定そのものによって当然に効力が生じます。この即時性と包括性が、自動的停止を極めて強力なものにしています。
効力の範囲と全世界的効力
自動的停止が禁止する行為は、第362条(a)項に網羅的に列挙されており、その範囲は極めて広いです。主なものを以下に挙げます。
- 申立て前の原因に基づいて発生した債権に関する、訴訟の提起または継続((a)(1))。
- 申立て前の判決の執行((a)(2))。
- 倒産財団に属する財産の占有を取得し、またはその財産に対し支配権を及ぼす一切の行為((a)(3))。(これは非常に広範な規定であり、例えば、債務者が賃借している不動産からの追い出しや、債務者が所有する物品の引き揚げなどが含まれます。)
- 倒産財団に属する財産に対する担保権の設定、完成、または実行((a)(4))。
- 申立て前の債権を回収するための、債務者に対するあらゆる取立行為((a)(6))。(電話や手紙による支払いの要求もこれに含まれます。)
- 申立て前の債務と債権の相殺((a)(7))。
アメリカの裁判所は、この自動的停止の効力は「全世界的(worldwide)」に及ぶと解釈しています。つまり、アメリカ国外にいる債権者が、アメリカ国外で行う取立行為であっても、アメリカの倒産裁判所がその債権者に対して人的管轄権(personal jurisdiction)を有する限り、自動的停止の対象となります。日本企業がアメリカ企業の倒産に関与する場合、この点を理解しておくことは極めて重要です。アメリカで取引先が破産を申し立てたことを知りながら、日本国内でその取引先に対する訴訟を提起したり売掛金と買掛金を相殺したりする行為は、自動的停止に違反し、後述する制裁の対象となる可能性があります。
自動的停止の例外と解除(Relief from Stay)
これほど強力な自動的停止も、絶対的なものではありません。法典は、公益性の高い特定の行為などを、その効力の対象外とする「例外」を設けています。第362条(b)項に列挙されている主な例外には、以下のようなものがあります。
- 債務者に対する刑事手続の開始または継続。
- 扶養料や養育費の徴収に関する特定の行為。
- 政府機関による警察権または規制権(police or regulatory power)の行使。(政府が国民の健康や安全、福祉を守るために行う行政措置を保護するものであり、例えば、環境汚染に対する是正命令や、事業許可の取消しなどが含まれます。ただし、政府が単に金銭的な利益を保護しようとする行為は、この例外には当たりません。)
また、自動的停止によって不利益を受ける債権者は、永久にその権利行使を禁じられるわけではありません。債権者は、倒産裁判所に対して「自動的停止の解除(Relief from the Stay)」を申し立てることができます。裁判所がこの申立てを認める主な理由は、第362条(d)項に定められています。
- 正当な理由がある場合((d)(1)): 「正当な理由」の最も典型的な例が、「適切な保護(Adequate Protection)」の欠如です。これは主に担保付債権者に関わる問題です。例えば、銀行がある機械設備を担保に融資をしていた場合、Chapter 11手続中に債務者がその機械を使い続けることで、機械の価値は経年劣化により減少していきます。この価値の減少は、銀行の担保権の価値を毀損するものです。この場合、債務者は、価値の減少分を補うために、銀行に対して定期的に金銭を支払ったり、別の資産を追加で担保として提供したりといった「適切な保護」を提供しなければなりません。債務者が適切な保護を提供できない場合、銀行は「正当な理由」があるとして、停止の解除を求め、担保権を実行(機械を差し押さえて売却)することが認められます。
- 債務者に衡平な持分(エクイティ)がなく、かつ、その財産が有効な再建に必要でない場合((d)(2)): この要件は、債権者が以下の2つの点を両方とも証明した場合に認められます。
- (A) 債務者がその財産にエクイティを有していないこと。つまり、その財産の価値を、その財産を担保する債務の額が上回っている状態であること。
- (B) その財産が、有効な再建(an effective reorganization)にとって必要不可欠ではないこと。
例えば、債務者が所有しているが、主要な事業とは無関係の遊休不動産があり、その価値が抵当権の設定額を下回っているような場合、抵当権者である銀行は、この(d)(2)項を根拠に停止の解除を求め、抵当権を実行して不動産を競売にかけることが可能となります。
自動的停止に違反した行為は、原則として「無効(void)」です。さらに、意図的に停止に違反した債権者に対しては、裁判所は、債務者が被った実損害(弁護士費用を含む)の賠償を命じることができ、場合によっては懲罰的損害賠償を課すこともあります。