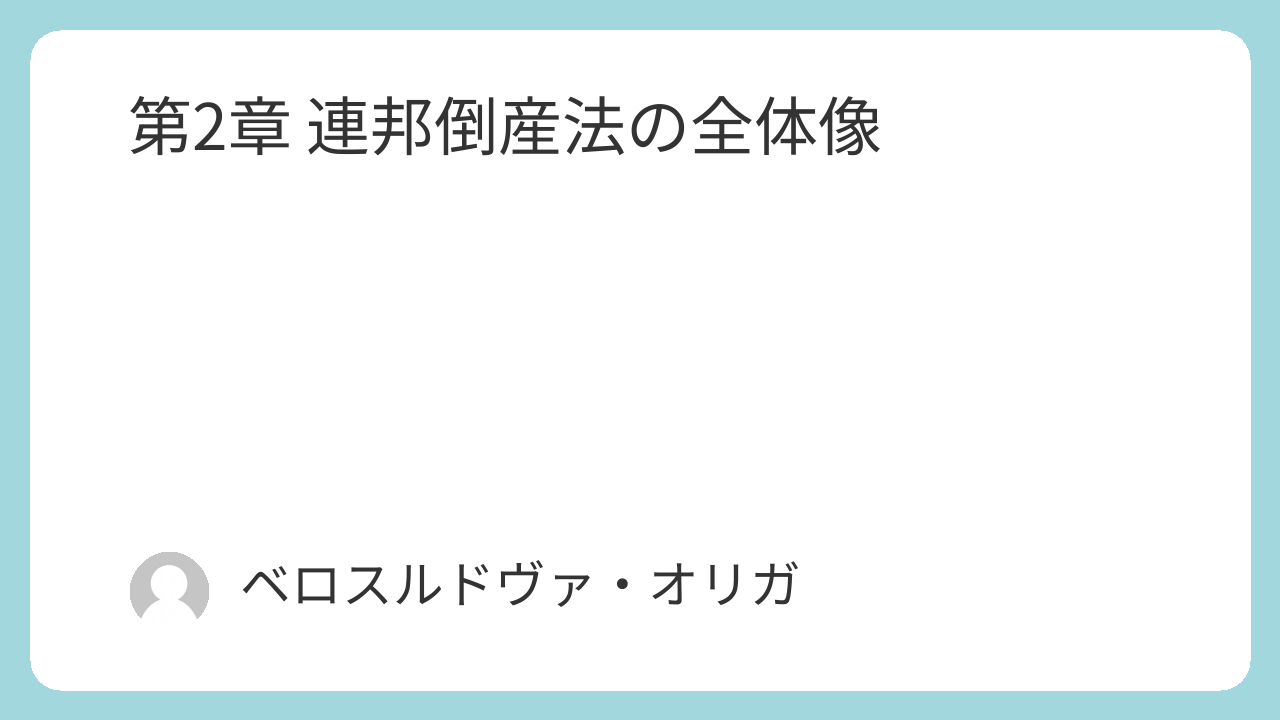連邦倒産法典(Title 11 U.S. Code)の構成
アメリカの倒産法は、合衆国法典(United States Code)の第11編に収められていることから、一般に「Title 11」または「Bankruptcy Code(倒産法典)」と呼ばれます。この法典は、極めて体系的な構造を持っているのが特徴です。
法典は複数の「章(Chapter)」から構成されており、その番号によって役割が明確に分かれています。
- 総則規定:Chapter 1, 3, 5
これらの章には、個別の倒産手続の種類にかかわらず、横断的に適用される基本的なルールが定められています。いわば、倒産法全体の「OS(オペレーティングシステム)」のような役割を果たします。Chapter 1には用語の定義や裁判所の権限が、Chapter 3には手続の開始方法や自動的停止(Automatic Stay)が、Chapter 5には倒産財団の範囲や否認権、債権の優先順位といった、倒産手続の根幹をなす規定が置かれています。 - 各則規定:Chapter 7, 9, 11, 12, 13, 15
これらの章は、それぞれ異なる目的と対象を持つ、具体的な倒産手続の種類を定めています。債務者は、自身の状況や目的に応じて、これらのチャプターの中から利用する手続を選択することになります。例えば、事業を清算したい法人はChapter 7を、事業を継続しながら再建したい企業はChapter 11を選択します。
この「総則」と「各則」が組み合わさって1つの手続が進行します。例えば、Chapter 11による再生手続が申し立てられた場合、その手続の具体的なルールはChapter 11の条文に従いますが、同時にChapter 1, 3, 5の総則規定も全面的に適用されます。
主要チャプターの概観(Chapter 7, 11, 13, 15)
連邦倒産法典には複数の手続が用意されていますが、実務上、特に重要なのは以下の4つのチャプターです。
- Chapter 7:清算手続(Liquidation)
Chapter 7は、最も基本的な倒産手続であり、「清算型」と呼ばれます。その目的は、管財人(Trustee)が債務者の資産(個人の場合は免除財産を除く)を公平かつ効率的に売却・換価し、その代金を法で定められた優先順位に従って債権者に分配することにあります。
個人と法人の両方が利用できますが、最終的な目的は異なります。個人債務者にとって、Chapter 7の最終目標は、過去の債務の大部分について支払義務を免除してもらう「免責(Discharge)」を得て、「フレッシュスタート」を切ることです。一方、法人にとってChapter 7は、通常、その事業活動の終焉を意味します。資産は全て売却され、法人は解散・消滅に至るのが一般的です。 - Chapter 11:再建手続(Reorganization)
Chapter 11は、アメリカ倒産法の華とも言える手続であり、「再生型」の代表格です。その主たる目的は、債務者(特に企業)が事業活動を継続しながら、債務を整理・削減し、再生計画(Plan of Reorganization)を策定・実行することで、経営危機から脱却することにあります。
Chapter 11の最大の特徴は、原則として管財人が選任されず、既存の経営陣が「占有継続債務者(Debtor in Possession, DIP)」として、管財人とほぼ同等の強力な権限を持って事業の運営と再建手続を主導する点にあります。このDIP制度の存在が、経営の継続性を保ち、柔軟かつ迅速な再建を可能にしています。大企業だけでなく、複雑な資産を持つ個人も利用することができます。 - Chapter 13:個人債務整理(Adjustment of Debts of an Individual with Regular Income)
Chapter 13は、定期的な収入のある個人債務者のための再生型手続です。Chapter 7のように資産を全て手放すのではなく、債務者は将来の収入の一部を原資として、3年から5年間にわたる返済計画(Plan)を作成し、裁判所の認可を得てその計画に従って返済を行っていきます。計画通りに返済を完了すれば、残りの債務の多くが免責されます。住宅ローンを滞納しているが自宅は手放したくない個人などが、この手続を選択することが多いです。 - Chapter 15:国際倒産(Cross-Border Insolvency)
Chapter 15は、複数の国にまたがる国際的な倒産事件を処理するための手続を定めます。これは国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)が作成したモデル法を基礎としており、外国で行われている主たる倒産手続をアメリカ国内で承認し、その外国管財人に対してアメリカ国内での資産調査や保全活動、訴訟提起などの権限を与えることで、国際的な協力を促進することを目的とします。日本企業がアメリカの子会社や取引先の倒産に関与する際に、極めて重要な意味を持つチャプターです。
倒産裁判所(Bankruptcy Court)の役割と管轄
アメリカの倒産事件は、連邦裁判所の一部である「倒産裁判所(Bankruptcy Court)」という専門裁判所が専属的に取り扱います。倒産裁判所は、各連邦地方裁判所(District Court)の管轄区域ごとに設置されており、倒産事件に関する専門知識を持つ裁判官(Bankruptcy Judge)が審理を担当します。
倒産裁判所の役割は多岐にわたります。単に法律問題を判断するだけでなく、手続全体の進行を監督し、利害関係者間の紛争を解決し、再生計画や各種申立ての認否を決定するなど、手続のあらゆる局面に深く関与します。その判断は、債務者、ひいては数多くの債権者や従業員の利害を左右する、極めて強力なものです。
主要な関係者
- 債務者(Debtor)
倒産手続の主役であり、破産申立てを行った個人または法人のことです。債務者の目標は、利用するチャプターによって異なります。Chapter 7の個人であれば免責によるフレッシュスタート、Chapter 11の企業であれば事業の再建です。
特にChapter 11において、債務者は「占有継続債務者(DIP)」として特別な地位を得ます。DIPは、自らの事業と財産を管理・運営し続けるだけでなく、管財人が持つ資産回収のための否認権など、法典上の強力な権限を行使することができます。経営の継続性を保ちながら自らの手で再建を進めることができる反面、全ての債権者に対する受託者(Fiduciary)としての重い責任を負うことになります。 - 債権者(Creditor)と債権者委員会(Creditors’ Committee)
債権者とは、債務者に対して金銭的な請求権(Claim)を持つ個人や法人のことです。その権利がどの程度保護され、どのような順番で支払いを受けられるかによって、大きく以下の3つの階層に分類されます。- 担保付債権者(Secured Creditor): 不動産や特定の資産に担保権(Lien)を設定しており、その担保物の価値の範囲内で他の債権者に優先して弁済を受けられる権利を持ちます。銀行やリース会社などが典型です。優先的無担保債権者(Priority Unsecured Creditor): 担保権は持たないものの、倒産法が定める特定の政策的理由(例:手続費用の確保、租税の徴収、従業員の保護など)から、他の一般の債権者よりも優先的に支払いを受ける権利を持つ債権者です。一般無担保債権者(General Unsecured Creditor): 上記のいずれにも属さない、担保も法定の優先権も持たない債権者です。取引先、社債権者、損害賠償請求権者などがこれに含まれ、倒産手続における債権者の大多数を占めます。
- 管財人(Trustee)と連邦管財官(U.S. Trustee)
名称が似ているため混同されやすいですが、その役割は全く異なります。
管財人(Trustee)は、個別の倒産事件を管理・運営するために選任される、民間の弁護士や会計士です。その役割はチャプターによって異なります。Chapter 7では、管財人は債務者の財産を収集・換価し、債権者に分配する主導的な役割を担います。Chapter 13では、債務者から返済計画に基づく支払金を受領し、それを債権者に分配する役割を果たします。Chapter 11では、前述の通りDIPが原則として手続を主導するため、管財人が選任されるのは、DIPによる詐欺や不正行為など、特別な「原因(for cause)」がある場合に限られます。
一方、連邦管財官(U.S. Trustee)は、司法省に所属する連邦政府の職員です。彼らの役割は、個別の事件の当事者として財産を管理することではなく、倒産制度全体の公正さと効率性を監督することにあります。いわば、倒産制度の「警察官」や「番人」のような存在です。連邦管財官の具体的な職務には、民間の管財人や債権者委員会を任命・監督すること、債務者の提出書類をチェックし濫用がないか監視すること、専門家(弁護士など)の報酬の妥当性を審査することなどが含まれます。