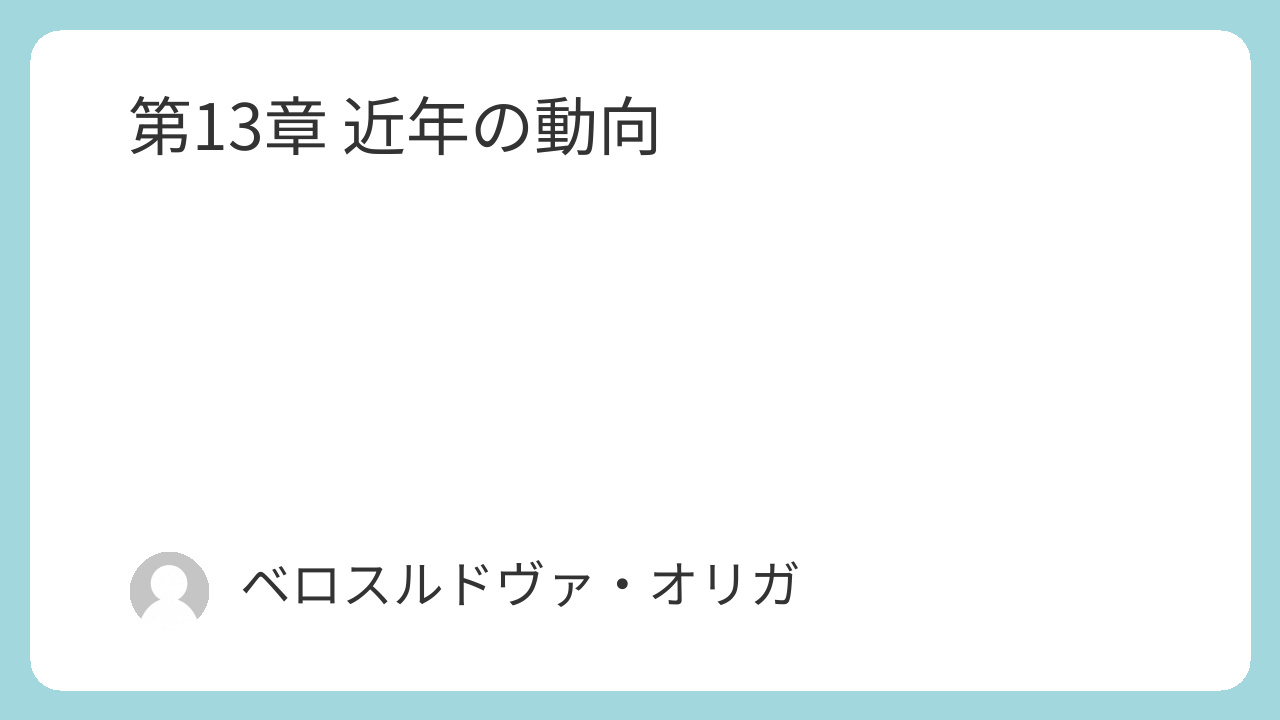アメリカ合衆国の連邦倒産法は、社会経済の変化や新たなビジネスモデルの登場に伴い、常に進化を続けています。1978年に制定された現行法典は、その柔軟性によって多くの課題に対応してきましたが、近年、従来の枠組みでは想定されていなかった複雑な問題が頻発しています。特に、大量不法行為(Mass Tort)責任を処理するための倒産手続の利用や、暗号資産(Crypto Assets)という新しい資産クラスを巡る法的混乱は、倒産実務に新たな議論をもたらしています。
1. 大量不法行為(Mass Tort)と倒産手続の交錯
近年、アスベスト(石綿)関連疾患、オピオイド(麻薬性鎮痛薬)中毒、製品欠陥(欠陥のある医療機器や除草剤など)といった大量不法行為に起因する巨額の損害賠償責任に直面した企業が、その解決策としてChapter 11を利用するケースが増えています。
(1) なぜ倒産手続が利用されるのか
倒産手続の外では、多数の被害者が個別に異なる州の裁判所で訴訟を提起するため、企業は防御コストの増大と判決結果の不確実性という問題に直面します。これに対し、Chapter11手続は以下のメリットを提供します。
- 自動的停止(Automatic Stay): 全ての訴訟が停止され、企業は事業を継続しながら問題解決に取り組むことができるようになります。
- 請求の一括処理: 全ての請求を1つの倒産裁判所に集約し、将来発生しうる請求も含めて、一括的かつ終局的に解決することが可能です(請求評価プロセスの確立)。
- 再建計画による解決: 被害者救済のための信託(Trust)を設立し、企業の資産の一部を拠出することで、責任問題を解決しつつ事業を継続する道が開かれます。
しかし、本来は財務的苦境にある企業を救済するための倒産手続を、現状は健全な企業が不法行為責任を限定するために利用することに対しては、強い批判があります。この文脈で、特に「第三者免責」と「テキサス・ツー・ステップ」が激しい論争の的となっています。
(2) 争点:第三者免責(Third-Party Releases)の可否
大量不法行為関連の倒産事件では、再建計画において、倒産した債務者自身だけでなく、債務者と関係のある第三者(親会社、オーナー一族、役員、関連会社など)に対する請求も免責(Release)することがしばしば試みられます。特に、債権者(被害者)の同意を得ることなく、これらの第三者を免責することを「非合意的第三者免責(Nonconsensual Third-Party Releases)」と呼びます。
この第三者免責は、責任追及から逃れたい第三者が、その見返りとして被害者救済信託に多額の資金を拠出することを促し、事件の全体的解決に資するという側面があります。しかし、連邦倒産法には第三者免責を明示的に許可する規定はなく、その可否については巡回区控訴裁判所間で判断が分かれていました(Circuit Split)。
この問題を象徴するのが、オピオイド危機を引き起こしたとされるPurdue Pharma社のChapter11事件です。同社の再建計画案には、同社を所有するSackler家が約60億ドルを拠出する見返りに、Sackler家に対するオピオイド関連の民事責任を免責する条項が含まれていました。
この計画案は倒産裁判所及び第2巡回区控訴裁判所によって承認されましたが、連邦政府(司法省)が異議を唱え、事件は連邦最高裁判所に持ち込まれました。2024年6月、最高裁は5対4の僅差で、連邦倒産法は債権者の同意なしに第三者(Sackler家)を免責することを許可していないとの判決を下しました(Harrington v. Purdue Pharma L.P.)。
この最高裁判決は、第三者免責を前提として構築されてきた大量不法行為関連倒産の解決実務に大きな打撃を与えました。企業や関係者が倒産手続を通じて不法行為責任から完全に解放される道が、著しく狭まるためです。
(3) 手続の濫用:「テキサス・ツー・ステップ(Texas Two-Step)」戦略
もう1つの大きな論点は、財務的に健全な大企業が、不法行為責任を限定するために用いる会社再編戦略、通称「テキサス・ツー・ステップ」です。
この戦略は、特定の州法(特にテキサス州やデラウェア州)の「会社分割(Divisive Merger)」制度を利用します。手順は以下の通りです。
- ステップ1(会社分割): 企業は、既存の事業部門と優良資産を承継する新会社(AssetCo)と、不法行為責任(及び限定的な資産)を承継する別の新会社(LiabilityCo)に分割されます。
- ステップ2(Chapter11申請): 分割直後、責任を負わされたLiabilityCoがChapter11の適用を申請します。
この戦略の狙いは、自動的停止によってLiabilityCo(ひいてはグループ全体)に対する訴訟を停止させ、責任をLiabilityCoの限定的な資産の範囲内に封じ込めることにあります。
この戦略を積極的に活用したのが、ベビーパウダーに含まれるタルク(滑石)の発がん性を巡り数万件の訴訟に直面していた医薬品メーカーです。当該企業は2021年にテキサス州法を利用して会社を分割し、責任を承継させた子会社LTL Managementを設立、直ちにChapter 11を申請しました。
しかし、この戦略は被害者側から「倒産制度の濫用」であると強く批判されました。Chapter11は「誠実に(in good faith)」申し立てられなければならず、正当な倒産目的を欠く申立ては却下(Dismissal)される可能性があります。
2023年1月、第3巡回区控訴裁判所は、LTL Managementは切迫した財務的苦境(financial distress)に直面しておらず、そのChapter11申請は正当な倒産目的を欠くため、却下されるべきであるとの判決を下しました。この判決を受けて、LTL Managementは2度にわたるChapter11申請を却下される結果となりました。
第3巡回区の判断は、他の裁判所にも影響を与えており、テキサス・ツー・ステップ戦略の有効性は大きく揺らいでいます。財務的に健全な企業が、単に訴訟戦略上の優位性を得る目的で倒産手続を利用することに対して、裁判所は厳しい姿勢で臨むようになっています。
2. 暗号資産(Crypto Assets)企業の倒産
2022年以降、暗号資産市場の混乱に伴い、FTX、Celsius Network、Voyager Digital、BlockFiといった大手暗号資産交換業者やレンディングプラットフォームの大型倒産が相次ぎました。これらの事件は、暗号資産という新しいデジタル資産の特性に起因する、前例のない法的課題を浮き彫りにしました。
(1) 法的課題①:顧客資産の所有権
最も根本的かつ重要な争点は、「顧客がプラットフォームに預けていた暗号資産は誰のものか」という問題です。
もし顧客資産が、信託(Trust)または寄託(Bailment)の法理に基づき、プラットフォームの資産とは分離されて保管されていると認められれば、それは倒産財団(Bankruptcy Estate)を構成せず、顧客は資産の返還を受けることができます。
しかし、多くのプラットフォームの利用規約(Terms of Service)は曖昧であり、プラットフォーム側が顧客資産を自由に運用(再投資や貸付など)できる権限を有している場合が多く見られます。
Celsius Network事件において、倒産裁判所は、利息が付与される「Earn」プログラムに預けられていた暗響資産については、利用規約に基づき所有権がCelsiusに移転しており、したがって倒産財団に含まれるとの判断を示しました。その結果、当該プログラムの顧客は、一般無担保債権者として扱われることになりました。他方で、単なる保管目的の「Custody」アカウントの資産については、所有権が顧客に留保されていると判断されました。
FTX事件においても、日本の暗号資産法制のおかげで、日本の顧客に対しては例外的に資産の返還を行いましたが、米国本土含め世界的には、顧客資産の分別管理が極めて杜撰であったことが明らかになっており、顧客資産が倒産財団に含まれるか否かが大きな争点となっています。これらの判断は、個別の利用規約の解釈と、適用法令、実際の資産管理状況に基づいて行われます。
(2) 法的課題②:暗号資産の法的性質と評価
暗号資産が連邦倒産法上どのように分類されるか(コモディティか、証券か、通貨か、あるいは独自の分類か)も重要な論点です。この分類は、関連する規制当局(CFTCやSEC)の管轄や、倒産手続における取扱いに影響を与えます。
また、暗号資産は価格変動が極めて激しいため、その評価(Valuation)も困難な課題です。どの時点の価格を基準に債権額を算定すべきか(例えば、破産申立日か、弁済実行日か)について争いが生じます。多くの事件では、申立日時点での米ドル換算額を基準とする伝統的なアプローチが採用されていますが、その後の価格変動によっては債権者間に不公平感を生じさせる可能性があります。
(3) 法的課題③:否認権の適用
暗号資産取引の匿名性や即時性は、否認権(偏頗弁済や詐害的譲渡)の適用においても特有の問題を生じさせます。
例えば、倒産直前期にプラットフォームから暗号資産を引き出した顧客は、偏頗弁済否認の対象となる可能性があります。しかし、ブロックチェーン上の取引記録から「移転(Transfer)」の時期を特定することや、取引の相手方を特定することが困難な場合があります。
さらに、DeFi(分散型金融)プロトコルを介した取引の場合、中央管理者が存在しないため、誰を相手取って否認権を行使すべきか、スマートコントラクトによって自動実行された取引を「巻き戻す」ことが法的に可能かといった、より複雑な問題が生じます。
(4) 国際的側面と管轄の問題
暗号資産ビジネスは本質的に国境がなく、多くの企業はバミューダ、ケイマン諸島、バハマといったオフショア地域に法人を設立しています。FTXグループがバハマに本拠を置いていたように、資産や関係者が世界中に分散しているため、国際倒産(Cross-border Insolvency)の側面が強く現れます。
どの国の倒産手続が主導権を握るのか、Chapter15(外国倒産手続の承認・支援)を通じた国際協力が不可欠となりますが、各国の法制度の違いや、資産の追跡の困難さから、手続は複雑化・長期化する傾向にあります。
3. 近年の重要判例の動向と今後の展望
(1) 知的財産権の取扱い:Mission Product判決
倒産手続における知的財産ライセンス契約の取扱いは、長年の課題でした。連邦倒産法365条(n)は、ライセンサー(債務者)が契約を「拒絶(Rejection)」した場合でも、ライセンシーが一定の知的財産権(特許や著作権など)を引き続き使用できる権利を保護しています。しかし、商標(Trademark)はこの保護対象に含まれていませんでした。
2019年の連邦最高裁判決(Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC)は、債務者(ライセンサー)による契約の拒絶は、契約違反(Breach)を構成するが、契約の終了(Termination)を意味するものではないと判示しました。これにより、たとえ商標ライセンス契約であっても、拒絶によってライセンシーが既に付与されていた使用権が直ちに消滅するわけではないことが明確化されました。この判決は、ライセンシーの保護を強化するものとして歓迎されています。
(2) 優先順位の厳格化:Jevic判決
連邦倒産法は、債権の優先順位(Priority)を厳格に定めています。2017年の連邦最高裁判決(Czyzewski v. Jevic Holding Corp.)は、この優先順位の原則の重要性を再確認しました。
同判決は、Chapter11手続を終了させる際に用いられる「構造的却下(Structured Dismissal)」(和解による配当と手続の却下を組み合わせた手法)において、影響を受ける債権者の同意がない限り、法典が定める優先順位に反する配当を行うことは許されないと判示しました。この判決は、手続の柔軟性よりも、法典の規律を重視する姿勢を示したものです。
(3) 裁判管轄(Venue)選択とフォーラム・ショッピング
近年の傾向として、大規模なChapter11事件が特定の倒産裁判所(特にデラウェア州、ニューヨーク州南部地区、そして最近ではテキサス州南部地区)に集中する「フォーラム・ショッピング(Forum Shopping)」が問題視されています。企業は、自社に有利な判例法が確立されていたり、手続の迅速性や裁判官の専門性が期待できる裁判所を選好します。
これに対して、企業の主要な事業拠点や関係者の所在地と無関係な裁判所で手続が行われることへの批判が高まっており、連邦議会では裁判管轄ルールの厳格化を目指す法改正の動きも出ています。