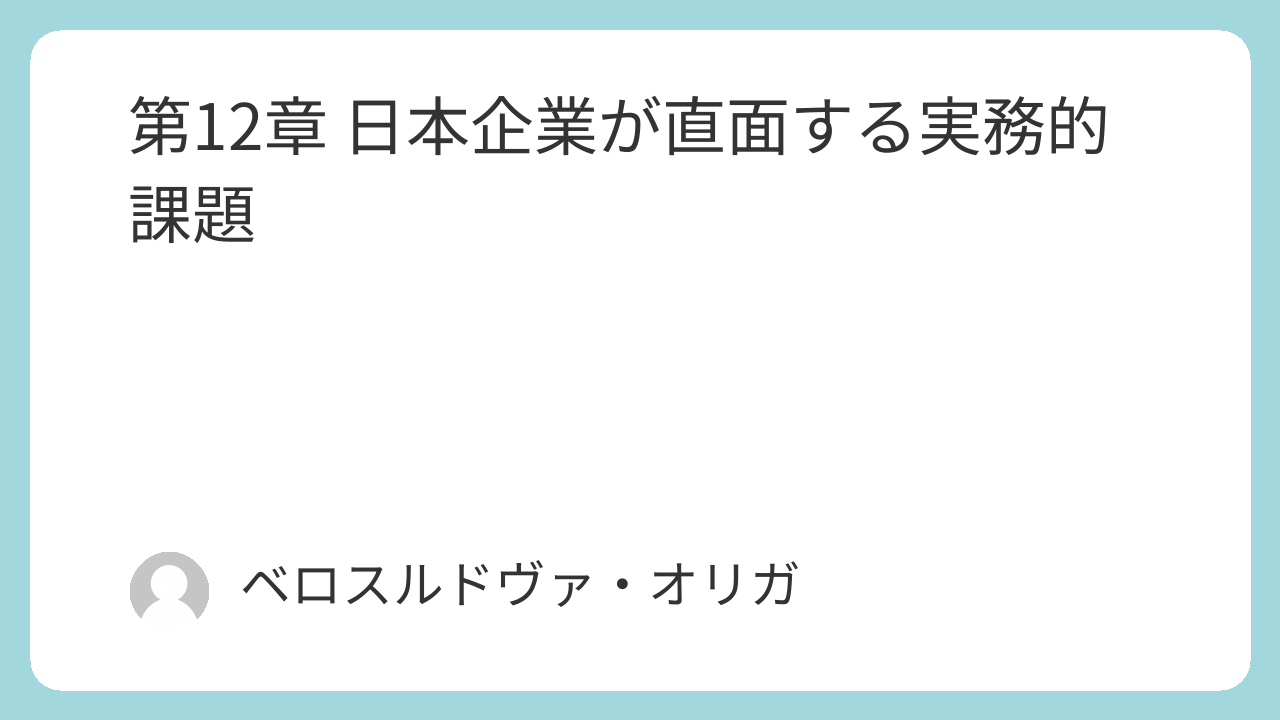米国の仮想通貨取引所やシェアオフィス事業者のChapter11申請が日本のニュースを騒がせたように、グローバルに事業を展開する日本企業にとって、アメリカ合衆国の連邦倒産法は決して対岸の火事ではありません。現地子会社が経営難に陥る可能性や重要な取引先が突然Chapter11を申請するリスクは常に存在します。
本章では、日本企業が直面する主要な2つの局面、すなわち「アメリカ子会社の倒産」と「アメリカの取引先の倒産」に焦点を当て、具体的なリスクと実務的な対応策について述べます。
1. アメリカ子会社の倒産対応
アメリカに子会社を設立して事業を行う際、多くの日本企業は、万が一現地事業が失敗しても、そのリスクが日本本社に波及しないことを期待します。会社法上、親会社と子会社は別個の法人格を有し、株主有限責任の原則が適用されるため、この期待は原則として保護されます。しかし、アメリカの倒産実務においては、一定の要件の下でこの原則が修正され、親会社が子会社の債務について責任を負ったり、親会社の資産が子会社の倒産手続に取り込まれたりするリスクが存在します。
(1) 倒産隔離(Bankruptcy Remoteness)の重要性
子会社のリスクを親会社から遮断することを「倒産隔離(Bankruptcy Remoteness)」と呼びます。特にストラクチャード・ファイナンスの分野で発達してきた概念ですが、一般の事業会社においても極めて重要です。倒産隔離を実現するためには、平時から親会社と子会社の間の「形式」と「実態」の両面において、明確な分離を維持する必要があります。
具体的には、以下の点に留意すべきです。
- コーポレート・ガバナンスの分離: 取締役会や株主総会を別々に開催し、議事録を適切に作成・保管します。親会社の役職員が子会社の役員を兼任する場合でも、それぞれの立場に応じた忠実義務(Fiduciary Duty)を果たす必要があります。
- 財務・会計の分離: 銀行口座、会計帳簿を明確に分離します。親会社からの過剰な資金援助や、グループ内での恣意的な資金移動は避けるべきです。
- 事業運営の分離: 資産を混同させず、日常業務の意思決定を子会社自身が行う体制を構築します。対外的にも、親会社と子会社が一体であるかのような誤解を与えないように注意が必要です。
これらの分離が不十分な場合、後述する「実質的統合」や「法人格否認」のリスクが高まります。
(2) 実質的統合(Substantive Consolidation)の法理とリスク
日本企業にとって最も警戒すべきリスクの一つが、「実質的統合(Substantive Consolidation)」です。これは、倒産手続において、法的には別個の法人格を有する複数の関連会社(例えば親会社と子会社)を、あたかも1つの会社であるかのように扱い、それらの資産と負債をプールして、全債権者に対して一括して配当を行うという、衡平法上の救済措置です。連邦倒産法105条(a)が定める裁判所の広範な権限に基づき認められています。
実質的統合が命じられると、以下の重大な結果が生じます。
- リスクの共有: 仮に日本親会社自身は健全であっても、経営不振のアメリカ子会社と統合されてしまえば、親会社の資産が子会社の債権者の引き当てとなってしまいます。
- グループ内債権の消滅: 親会社が子会社に対して有していた貸付金などのグループ内債権(Intercompany Claims)は、統合によって消滅してしまいます(相殺)。
実質的統合を認めるか否かの判断基準は、判例法によって形成されてきました。近年の潮流として最も重要なのは、第3巡回区控訴裁判所が示した In re Owens Corning 事件(2005年)の判決です。同判決は、実質的統合は「最後の手段として限定的に(sparingly used)」適用されるべきであるとし、より厳格な基準を採用しました。統合を求める側(多くは子会社の債権者委員会)は、以下のいずれかを立証しなければならないと判示しています。
- 債権者の依拠: 債権者が取引を行う際、対象となる関連会社グループを単一の事業体であると認識し、その認識に依拠していたこと。
- 分離不可能性: 関連会社間の資産と負債が絶望的に混同(hopelessly commingled)しており、それらを分離するためのコストが非現実的であること。
この Owens Corning 基準の下では、単に親会社が子会社を支配している、あるいは財務報告が連結されているといった事実だけでは、直ちに実質的統合が認められるわけではありません。重要なのは、債権者がどのように認識していたか、客観的に資産・負債が分離可能かという点です。
日本企業への示唆:
日本企業は、Owens Corning基準を踏まえ、実質的統合のリスクを最小化するための対策を講じる必要があります。平時においては、前述の倒産隔離策を徹底し、資産や負債が「絶望的に混同」していると評価されないよう、明確な管理体制を構築すべきです。特に、キャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を利用している場合は、グループ内での資金移動の記録を明確に残し、各社の残高を即時に特定できるようにしておくことが肝要です。
また、子会社の債権者に対し、取引主体が子会社単独であることを明示し、親会社が保証(Parent Guarantee)を提供していない限り、親会社の信用力に依拠させないような対応も重要となります。
万が一、子会社が倒産手続を開始し、債権者側から実質的統合の申立てがなされた場合には、日本親会社は迅速に弁護士を起用し、詳細な証拠を提出して反論する必要があります。これは極めて専門的かつ事実認定が重視される争いとなります。
(3) 親会社責任のその他の根拠
実質的統合以外にも、親会社が子会社の倒産に関連して責任を追及されるリスクが存在します。
① 法人格否認(Piercing the Corporate Veil)
これは倒産法固有の法理ではなく、一般の会社法上の法理です。親会社が子会社を完全に支配し、子会社を単なる「道具(instrumentality)」や「分身(alter ego)」として利用し、それによって債権者を害するような不正行為や詐欺行為を行った場合、裁判所は子会社の法人格を否認し、親会社に直接責任を負わせることがあります。その適用は限定的であり、単なる支配関係だけでは認められません。
② 詐害的譲渡(Fraudulent Transfer)
子会社が倒産する直前期に、親会社に対して不当に有利な取引(例えば、不当に高額な配当、廉価での資産売却、不当なマネジメントフィーの支払いなど)を行っていた場合、それは詐害的譲渡(連邦倒産法第548条または州法)として否認される可能性があります。特に、子会社が支払不能状態にあり、かつ「合理的に同等の対価(reasonably equivalent value)」を受け取っていなかった場合には、「擬制詐害的譲渡(Constructive Fraudulent Transfer)」として、親会社の悪意がなくとも否認の対象となります。
日本企業は、経営不振の子会社から資金を引き揚げる際には、その取引の対価の合理性について慎重に検討すべきです。
③ 衡平法上の劣後(Equitable Subordination)
親会社が子会社に対して債権(貸付金など)を有している場合、その債権の優先順位が他の一般債権者よりも劣後させられる可能性があります。これが「衡平法上の劣後(Equitable Subordination)」(連邦倒産法第510条(c))です。
この措置は、債権者(ここでは親会社)が何らかの「不正な行為(inequitable conduct)」を行い、それによって他の債権者に損害を与えたり不当な利益を得た場合に認められます。親会社は子会社の内部情報にアクセスできる「インサイダー」であるため、その行動は厳しく審査される傾向にあります。例えば、支配的地位を利用して自己に有利な取引を強要した場合などが典型例です。
また、親会社からの貸付金が、実態としては「資本(Equity)」とみなされる場合(資本再構成:Recharacterization)も、返済の優先順位は劣後します。特に、子会社設立時の資本が過少(Undercapitalization)であり、通常の金融機関であれば融資を行わないような状況で親会社が貸付を行っていた場合などに、このリスクが高まります。
日本企業としては、子会社への資金供給の際には、その性質(貸付か資本か)を明確にし、貸付とするならば、契約条件を独立第三者間の取引(アームズ・レングス)と同等のものに設定し、形式を整えておくことが重要です。
2. 取引先のアメリカ企業倒産への対応
日本企業がサプライヤー、販売代理店、ライセンシーなどとしてアメリカ企業と取引を行っている場合、その取引先が突然、連邦倒産法(多くの場合Chapter 11)の適用を申請することがあります。この場合、日本企業は債権者として、迅速かつ戦略的に対応しなければ、債権回収が困難になるだけでなく、予期せぬ法的紛争に巻き込まれる可能性があります。
(1) 自動的停止(Automatic Stay)への対応
アメリカ倒産法の最も強力な特徴の1つが、「自動的停止(Automatic Stay)」(連邦倒産法第362条)です。破産申立てが行われた瞬間に、債務者(倒産した取引先)に対するほぼ全ての債権回収行為、訴訟追行、担保権実行が自動的に禁止されます。
① 全世界的効力(Worldwide Stay)
自動的停止の効力は、アメリカ国内に留まりません。アメリカの倒産裁判所は、自動的停止は全世界的に効力を有する(Worldwide Stay)との立場をとっています。これは、倒産財団(Bankruptcy Estate)を構成する財産が世界のどこにあろうと保護されるべきであるという考え方に基づくものです。
したがって、日本企業が日本国内において、倒産したアメリカ企業の資産(例えば日本にある在庫や売掛金)に対して差押えを行ったり、訴訟を提起したりすることは、原則として自動的停止に違反する行為となります。自動的停止に違反する行為は無効であり、故意に違反した場合には、懲罰的損害賠償を含む制裁(Sanctions)の対象となる可能性があります。
② 実務的対応
日本企業が取引先のアメリカ企業から倒産申立ての通知を受け取った場合(又はその事実を知った場合)、直ちに以下の対応を取る必要があります。
- 債権回収行為の即時停止: 督促状の送付、電話による催促、担保権の実行手続などを直ちに停止します。
- 訴訟手続の中断: 進行中の訴訟がある場合は、訴訟代理人を通じて裁判所に手続の中断を申し出る必要があります。
- 情報収集: 倒産裁判所の事件記録を確認し、申立て日、事件番号、債務者代理人などの基本情報を把握します。
なお、契約書によく見られる「倒産申立てを行った場合には契約を解除できる」といった条項(Ipso Facto条項、倒産解除条項)は、連邦倒産法上、原則として無効とされる点(第365条(e)(1))にも注意が必要です。したがって、取引先が倒産したからといって、直ちに契約を解除することはできません。
③ 自動的停止の解除(Relief from Stay)
自動的停止は絶対的なものではありません。債権者は、倒産裁判所に対して自動的停止の解除(Relief from Stay)を申し立てることができます。例えば、債権者が有する担保権の目的物の価値が時間とともに下落しており、債務者がその価値下落に対して「適切な保護(Adequate Protection)」を提供できない場合などに、解除が認められる可能性があります(第362条(d))。
(2) 債権回収の戦略
倒産手続において、一般無担保債権者(General Unsecured Creditor)の回収率は極めて低いのが現実です。そのため、日本企業は、自社の債権が一般無担保債権よりも優先的に取り扱われる可能性を追求する必要があります。
① 取戻権(Reclamation Rights)
取引先(買主)の倒産直前に商品を納入していた場合、売主(日本企業)は一定の要件の下で、その商品を取り戻す権利(Reclamation Rights)を有する可能性があります。
連邦倒産法第546条(c)は、売主が以下の要件を満たす場合に取戻権を認めています。
- 債務者(買主)が支払不能状態にあるときに、通常業務の過程で商品が販売されたこと。
- 債務者が商品を受領してから45日以内に破産申立てが行われたこと。
- 売主が、商品受領後45日以内、または(45日目が破産申立日以降の場合は)破産申立日から20日以内に、書面による取戻請求(Reclamation Demand)を行ったこと。
この権利は時間的制約が非常に厳格です。取引先の倒産を知った場合、日本企業は直ちに納入記録を確認し、要件を満たす商品があれば、期限内に適切な書面請求を行う必要があります。
② 管理費用債権(Administrative Expenses)
取戻権の要件を満たさない場合でも、破産申立て前の20日以内に債務者が受領した商品(Goods)については、その価額が「管理費用債権(Administrative Expenses)」として扱われます(連邦倒産法503条(b)(9))。管理費用債権は、一般無担保債権に優先して支払われるため、回収可能性が大幅に高まります。この権利は自動的に発生するため、取戻請求のような特別な書面請求は不要ですが、債権届出(Proof of Claim)において、その性質を明記することが重要です。
③ 相殺権(Setoff Rights)
日本企業が倒産した取引先に対して債務(例えば買掛金や未払いのリベート)を負っている場合、自社の債権(売掛金など)と相殺する権利(Setoff Rights)が認められる可能性があります(連邦倒産法553条)。相殺は、実質的に債権全額を回収する効果をもたらすため、非常に強力な手段です。
ただし、相殺権の行使には注意が必要です。自動的停止が発効している間は、債権者が一方的に相殺を行うことは禁止されます。相殺を実行するには、倒産裁判所に自動的停止の解除を申し立てるか、債務者の同意を得る必要があります。実務上は、相殺権の存在を主張しつつ、裁判所の許可(または債務者との合意)が得られるまで、支払いを留保(Administrative Freeze)することが多いです。
④ クリティカル・ベンダーの法理(Critical Vendor Doctrine)
Chapter 11手続においては、債務者(倒産企業)が事業を継続し、再建を図るために不可欠な取引先(Critical Vendor)に対しては、裁判所の許可を得て、破産申立て前の債権であっても優先的に弁済を行うことが認められる場合があります。
もし日本企業が、倒産企業にとって代替不可能な部品や技術を提供している唯一のサプライヤーである場合、このクリティカル・ベンダーとしての指定を求めて債務者と交渉する余地があります。指定されれば、申立て前の債権を早期に回収できる可能性がありますが、その見返りとして、申立て後も有利な条件で取引を継続することを要求されるのが通常です。
(3) 偏頗弁済否認(Preference)リスクとその防御
債権回収とは逆の局面として、日本企業が最も警戒すべきリスクの1つが、偏頗弁済否認(Preference)です。これは、倒産申立て前の一定期間(通常は90日間、インサイダーの場合は1年間)に、債務者から受け取った弁済が、管財人(またはDIP)によって否認され、その返還を求められる制度です(連邦倒産法547条)。
この制度の趣旨は、特定の債権者だけが「駆け込み弁済」を受けることを防ぎ、債権者間の平等を確保することにあります。日本の否認権制度と比較して、アメリカの偏頗弁済否認は、債務者や債権者の主観的意図(害意など)を要件とせず、形式的・機械的に適用される傾向が強い点に特徴があります。
① 否認の要件
偏頗弁済否認が成立するためには、主に以下の要件が全て満たされる必要があります。
- 既存の債務(Antecedent Debt)に関する弁済であること。
- 債務者が支払不能状態にある間に行われたこと(申立前90日間は支払不能が推定されます)。
- 申立前90日以内(インサイダーは1年以内)に行われたこと。
- その弁済によって、当該債権者が、仮にChapter 7(清算)手続が行われた場合に受け取るであろう配当よりも多くを受け取ることになること。
日本企業が、取引先から通常のサイクルで売掛金の支払いを受けていたとしても、それが申立て前90日以内であれば、形式的にはこれらの要件を満たしてしまう可能性が高いのです。
② 防御策(抗弁事由)
偏頗弁済否認の要件が一見満たされる場合でも、連邦倒産法はいくつかの重要な防御策(抗弁事由)を定めています。日本企業が否認請求を受けた場合、これらの抗弁を駆使して対抗することになります。
- 同時交換(Contemporaneous Exchange for New Value):
弁済と同時に新たな価値(New Value)が提供された場合は、否認の対象となりません(547条(c)(1))。例えば、代金引換(COD)での取引がこれに該当します。前払いの場合は、そもそも「既存の債務」に関する弁済ではないため、否認の対象外となります。 - 通常業務の過程(Ordinary Course of Business):
これが実務上最も頻繁に利用される抗弁です(第547条(c)(2))。当該弁済が、両者間の通常の取引過程で行われたもの、または、当該業界の標準的な取引慣行に従って行われたものである場合は、否認されません。
この「通常性」の判断は、過去の取引履歴(支払サイト、遅延の程度、支払方法など)との比較によって行われます。倒産直前期に突然、支払サイト(締め日から実際に代金が支払われるまでの期間)が短縮されたり、強い督促に応じて特別な支払いが行われたりした場合は、「通常性」が否定されるリスクが高まります。 - その後の新たな価値(Subsequent New Value):
偏頗弁済を受け取った後、さらに新たな商品やサービスを無担保で提供した場合、その新たな価値の分だけ否認額から控除されます(第547条(c)(4))。これは、倒産直前まで取引を継続した債権者を保護する趣旨です。
③ 実務的対応
偏頗弁済否認の請求は、倒産手続開始後、数ヶ月から数年経ってから突然送られてくることが多いです(時効は原則として申立て日から2年)。請求を受けた日本企業はまず取引記録を精査し、上記の抗弁事由が成立するかどうかを検討する必要があります。特に「通常業務の過程」の抗弁を立証するためには、過去数年分の詳細な取引データが必要となるため、平時からの記録管理が重要です。
多くのケースでは、訴訟(Adversary Proceeding)に移行する前に、管財人・DIPとの交渉による和解が図られます。抗弁の成否の見通しと訴訟コストを勘案し、合理的な和解額を目指すことになります。
3. 日米倒産法制の比較と実務的示唆
これまで見てきましたように、アメリカの連邦倒産法は、日本の倒産法制(会社更生法、民事再生法、破産法)とは多くの点で異なっています。その差異を理解することは、日本企業がリスクを適切に管理する上で重要です。
(1) DIP型原則と経営陣の継続性
日本の民事再生法はDIP(Debtor in Possession:占有継続債務者)型を原則としていますが、会社更生法では管財人型が原則です。一方、アメリカの再生手続であるChapter 11では、強力なDIP型が原則であり、不正行為などがない限り、旧経営陣が引き続き事業運営と再建計画策定の主導権を握ります。
これは、事業の継続性を重視するアメリカの再建思想の表れですが、債権者の視点からは、経営失敗の責任を問う機会が限定的であるとも言えます。日本企業が債権者の立場にある場合、債務者の経営陣の動向を注視し、必要に応じて債権者委員会(Creditors’ Committee)に参加するなどして、積極的に手続に関与することが求められます。
(2) 手続の迅速性とプレパッケージ型実務
アメリカのChapter11手続は、日本の再建手続と比較して、より迅速に進む傾向があります。特に、事前に主要な債権者と再建計画案について合意を形成した上で申立てを行う「プレパッケージ型(Prepackaged)」や「プリアレンジ型(Prearranged)」の実務が広く普及しています。これにより、申立てから数週間から数ヶ月で再建計画が認可されるケースも珍しくありません。
日本企業が主要な債権者である場合、水面下での交渉段階から関与し、自社の利益を計画案に反映させる機会を逃さないようにする必要があります。手続が開始されてから対応するのでは遅すぎる場合があります。
(3) 債権者間の衡平と形式的要件
アメリカの倒産法は、債権者間の衡平を重視する一方で、その実現手段は極めて形式的・機械的である場合が多いです。前述の偏頗弁済否認の適用や、取戻権の時間的制約の厳格さはその典型です。
日本企業は、アメリカの倒産手続においては、「実質的に不当ではないから大丈夫だろう」という感覚は通用しないことを認識すべきです。法定された要件と期限を厳格に遵守し、必要な手続を遅滞なく行うことが、権利保護の前提となります。