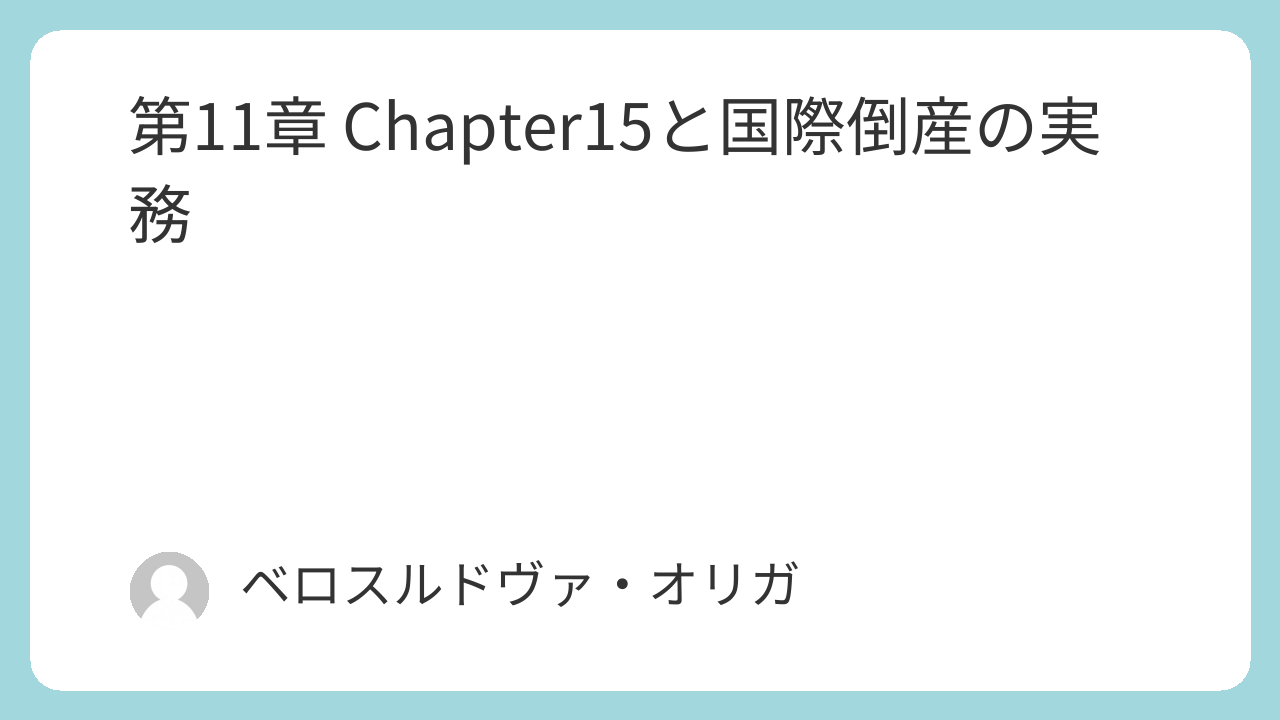多国籍企業が経営危機に陥ったとき、その倒産処理は一国の法制度だけでは完結しません。各国の倒産法制が、自国内の資産と債権者だけを優先する「属地主義(Territoriality)」的な対応に終始すれば、資産の散逸や不公平な分配、非効率な手続の乱立といった問題が生じ、企業全体の価値を最大化し、全ての債権者に公平な分配を行うという倒産法の基本理念を達成することができなくなってしまいます。
このような国際倒産の課題に対応するために、アメリカが2005年のBAPCPA改正で導入したのが「Chapter 15」です。これは、単なる国内法の改正ではなく、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)が策定した「クロスボーダー倒産モデル法(Model Law on Cross-Border Insolvency)」を、ほぼそのまま国内法として採り入れたものでした。
国際倒産の課題とUNCITRALモデル法
Chapter 15を理解するためには、まずその背景にある国際的な課題と、その解決策として提示されたUNCITRALモデル法の理念を把握する必要があります。
かつての国際倒産実務は、各国の裁判所が自国の管轄内にある資産を囲い込み、自国の債権者のためだけに手続を進めるという、いわば「資産争奪戦」となっていました。外国で行われている倒産手続の効力は自国内では及ばないという「属地主義」の考え方が根強かったのです。これに対し、企業を1つの経済的実体と捉え、主たる倒産手続が開始された国の裁判所が全世界の資産と債権者を対象に統一的な手続を進めるべきだという「普遍主義(Universality)」の理念も提唱されてきましたが、各国の主権・法制度の違いから、その実現は困難でした。
この対立を乗り越え、実用的で柔軟な解決策を提供するために国連主導で策定されたのが、UNCITRALモデル法です。その目的は、以下の5点に集約されます。
- 協力の促進: 各国の裁判所間・法律家間の協力を促進する。
- 法的確実性の向上: 国際的な貿易・投資における法的確実性を高める。
- 公正かつ効率的な手続の実現: 倒産者の財産の価値を保護しつつ、公正かつ効率的な手続運営を図る。
- 資産の保護: 倒産者の財産の価値を最大化するため、資産の保護と回収を促進する。
- 事業再生の促進: 経営危機に陥った企業の事業再生を促進する。
このモデル法は、各国に共通のルールブックを提供することで、外国手続への「アクセス」、「承認」、承認後の「支援」という明確な道筋を示しました。Chapter 15は、このモデル法の思想と構造を忠実に受け継いだものとなっています。
Chapter 15の構造
Chapter 15は、それ自体がChapter7やChapter11のような、完全な自己完結型の倒産手続ではありません。その本質は、外国で進行中の倒産手続(Foreign Proceeding)をアメリカの裁判所が法的に「承認(Recognition)」し、その外国手続を「支援(Assistance)」するためのゲートウェイです。
そのプロセスは、外国手続において債務者の財産や業務を管理する権限を与えられた者、すなわち「外国代表者(Foreign Representative)」(日本の破産管財人や再生債務者代理人等)が、アメリカの倒産裁判所に対して「承認申立て(Petition for Recognition)」を行うことから始まります。
外国倒産手続の承認申立て
外国代表者は、アメリカ国内にある資産の保全や債権者からの訴訟の停止、資産の回収といった目的を達成するために、まずアメリカの裁判所に、自らが管轄する外国手続を正式なものとして認めてもらう必要があります。
この承認申立てが認められるための要件は、1517条に定められています。裁判所は、(1)申立ての対象が法典の定義する「外国倒産手続」に該当し、(2)申立人がその手続における「外国代表者」であることを確認すれば、原則として承認命令を出さなければなりません。ただし、その承認がアメリカの「公序(public policy)」に著しく反する場合には、承認を拒否することができます。
主たる利益の中心地(COMI)の判断
承認申立てにおいて裁判所が下す最も重要な判断は、その外国手続が「外国主手続(Foreign Main Proceeding)」なのか、それとも「外国従手続(Foreign Non-main Proceeding)」なのかという認定です。この区別によって、承認後にアメリカ国内で得られる支援のレベルが劇的に変わります。
この認定の鍵を握るのが「主たる利益の中心地(Center of Main Interests、通称COMI)」という概念です。
- 外国主手続: 債務者の「COMI」が存在する国で行われている手続。
- 外国従手続: 債務者がCOMI以外の国に「事業拠点(Establishment)」を有しており、その国で行われている手続。
では、「COMI」はどのように判断されるのでしょうか。法典は「債務者の登録上の事務所(registered office)の所在地」がCOMIであると推定する規定を設けています。しかし、これはあくまで「推定」であり、債権者などの利害関係者は反証によりこの推定を覆すことができます。
裁判所は、登録地だけでなく、客観的な要素を総合的に考慮してCOMIを判断します。例えば、
- 会社の経営判断が日常的に行われている場所(本社機能の所在地)
- 主要な資産や従業員が存在する場所
- 主要な債権者が認識している事業の中心地
- 公開されている情報(ウェブサイトや年次報告書等)で会社が自らをどのように表示しているか
といった要素が考慮されます。日本企業の場合、登記上の本店が日本にあれば、日本の民事再生手続や破産手続はアメリカで「外国主手続」として承認される可能性が高いです。しかし、実質的な本社機能や主要な事業活動がアメリカにあるような場合には、日本の手続が従手続と認定されたり、アメリカで独自のChapter11手続が開始されたりする可能性もあります。
承認の効果と国際的協力
外国手続が主手続として承認されるか、従手続として承認されるかで、その効果は大きく異なります。
主手続(Main Proceeding)の認定と効果
外国手続が「主手続」として承認された場合、次のような効果が生じます。
- 自動的停止の全面適用: Chapter11の申立てと同様に、連邦倒産法典362条が定める自動的停止が、アメリカ国内の全ての資産と債務者に対して自動的に発動します。これにより、債権者による個別の訴訟提起や資産の差押えは、裁判所の個別命令を待つことなく即座に禁止されます。
- DIP・管財人権限の付与: 外国代表者は、アメリカ国内において、DIP又はChapter7手続の管財人が有する強力な権限の多くを行使することが認められます。これには、債務者の事業を運営する権限や、第5章で解説した財団財産の使用・売却・リースの権限が含まれます。
- 否認権の行使: 最も重要な点として、外国代表者は、アメリカ国内で、アメリカの連邦倒産法典が定める否認権(偏頗行為否認や詐害的譲渡否認など)を行使して、不当に流出した資産を取り戻すための訴訟を提起することができます。
これらの自動的な効力により、外国代表者は、アメリカ国内で迅速かつ強力に資産を保全し、価値の最大化を図ることが可能となります。
従手続(Non-main Proceeding)の認定と効果
一方、外国手続が「従手続」として承認された場合、自動的な効力は発生しません。アメリカ国内での支援は全て裁判所の裁量に委ねられます。
- 自動的停止は発動しない: 債権者の活動を止めるためには、外国代表者は、裁判所に対して個別に差止命令を求める必要があります。
- 支援内容は個別判断: 裁判所は、外国代表者の申立てに基づき、資産の保全や証拠収集、管財人の任命等、外国手続を支援するために「適切」かつ「必要」と判断したあらゆる救済措置を個別具体的に命じることができます。
国際的協力(Cooperation and Coordination)
Chapter15の根底に流れる最も重要な理念は「協力」です。1525条は、アメリカの裁判所に対し、外国の裁判所や外国代表者と最大限の協力を図ることを義務付けています。また、アメリカ国内で選任された管財人等に対しても、外国代表者と協力することを求めています。
この協力は、複数の国で倒産手続が並行して進行する「並行手続(Concurrent Proceedings)」において特に重要となります。例えば、日本で主手続が、アメリカで従手続がそれぞれ同時に進行している場合、両国の裁判所や管財人は互いに直接コミュニケーションを取り、資産の売却方法や債権者への分配計画について調整し、矛盾や衝突を避けるための協定(プロトコル)を結ぶことが奨励されます。このような国境を越えた協調行動によって、属地主義の弊害を乗り越え、グローバルな倒産事件の全体最適解を導き出すことを目指しています。
日本企業にとっても、アメリカの取引先が倒産した場合や自社・子会社がアメリカに資産を有したまま日本で法的整理手続に入る場合、Chapter15は、アメリカ国内での権利と資産を守り、予測可能な形で手続を進めるための不可欠な知識であり強力なツールとなります。