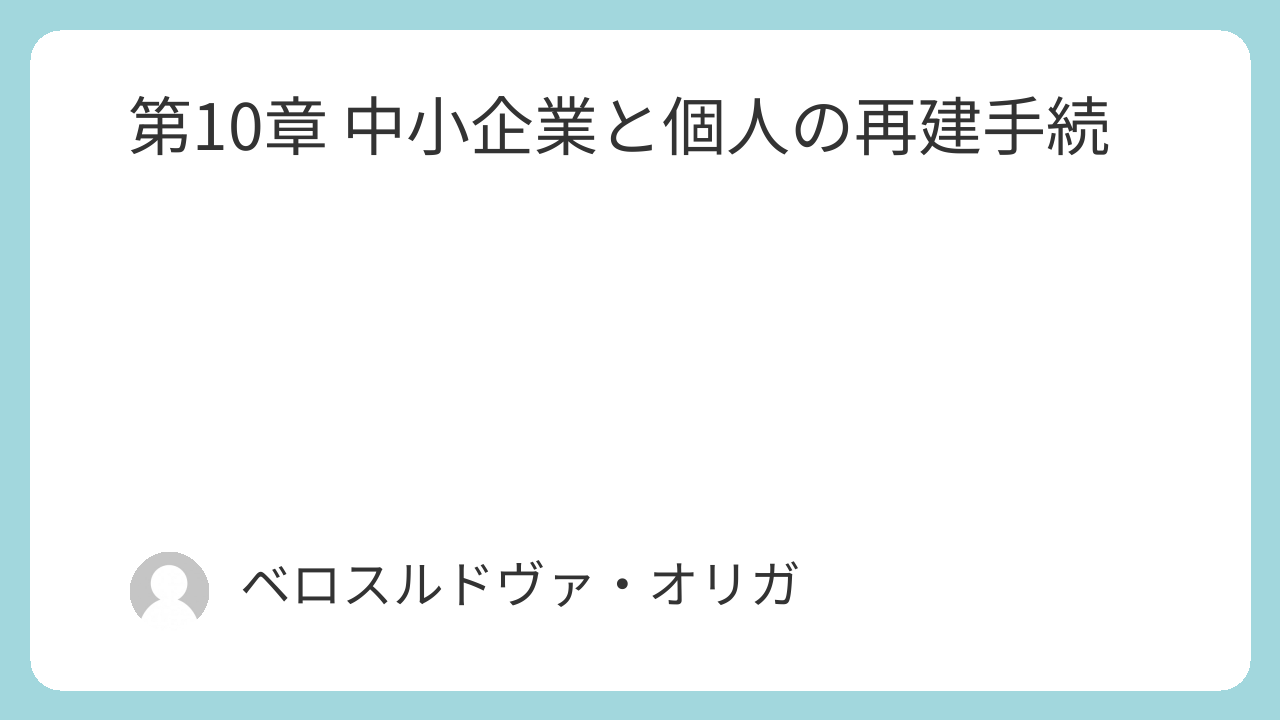前章のChapter 11は、巨大企業の複雑な利害関係を調整し、大規模な事業を再建するためのツールでした。しかし、その手続の複雑さ、費用の高さ、ルールの厳格さから、中小企業や個人事業主、住宅ローン・消費者向けローン等に苦しむ個人にとっては、使いづらいものです。
そこで、倒産法が提供する「再建」という機会を、より多くの経済主体に開かれたものにするために、連邦倒産法典は2つの重要な専門的再建手続を用意しています。1つは、2019年の法改正によって創設された、中小企業のための迅速かつ低コストな再建の道である「Subchapter V(サブチャプター・ファイブ)」。もう1つは、定期的な収入のある個人が、資産を失うことなく生活を立て直すためのツールである「Chapter 13」です。
中小企業向け特則:Subchapter V
中小企業再建法(Small Business Reorganization Act of 2019、SBRA)の概要と特徴
Chapter 11の中に新設されたSubchapter Vは、対象となる「中小企業債務者(small business debtor)」に対して、伝統的なChapter11よりも迅速(faster)、安価(cheaper)、債務者フレンドリー(more debtor-friendly)な再建プロセスを提供します。
- 対象となる債務者: Subchapter Vを利用できるのは、事業を営む個人・法人で、その負債総額(偶発的・非確定債務を除く)が、法で定める上限額(2024年時点では約750万ドル、この上限額はインフレに応じて定期的に調整されます)を超えない者です。
- 基本理念: その核心は、プロセスを簡素化し、当事者間の合意形成を促し、そして最終的には、事業を継続する意思のある誠実な事業主が、その事業の所有権を維持しながら再生することを可能にすることにあります。
手続の迅速化とコスト軽減
Subchapter Vは、伝統的なChapter11のプロセスから、中小企業にとって特に負担の重い要素を大胆に削ぎ落としています。
- Subchapter Vにおける管財人の役割: 申立後、連邦管財官は、Subchapter Vの事件を専門に扱う「管財人(Subchapter V Trustee)」を選任します。しかし、この管財人は、Chapter 7のように資産を清算したり、Chapter 11の例外的な管財人のように経営権を掌握したりする存在ではありません。その主たる役割は、「手続の円滑化(facilitating the development of a consensual plan of reorganization)」、すなわち、債務者と債権者の間の交渉を仲介し、円満な合意による再生計画の策定を支援することにあります。この調停役のような管財人の存在が、対立的な訴訟を減らし、コストと時間を節約する上で大きな効果を発揮します。
- 債権者委員会の原則不設置: 伝統的なChapter 11では、通常、無担保債権者の利益を代表する「債権者委員会」が組織され、その委員会が雇用する弁護士や会計士の費用は、全て倒産財団(つまり債務者)の負担となります。これは中小企業にとって致命的なコスト負担でした。Subchapter Vでは、この債権者委員会は原則として設置されません。これにより、管理費用が劇的に削減されます。
- 計画提出と開示説明書の簡素化: 債務者は、原則として申立てから90日以内に再生計画を提出しなければならないという、迅速なスケジュールが課されます。他方、伝統的なChapter11で必須とされる、裁判所の事前承認を要する「開示説明書」の作成が不要とされています。計画の承認に必要な「適切な情報」は、再生計画書そのものに盛り込むことで足りるとされ、これにより審理プロセスが1つ省略され、迅速に手続を進めることができるようにしています。
計画認可要件の緩和と事業主の保護:絶対的優先原則の変革
Subchapter Vがもたらした最も革命的な変革は、計画の認可要件、特に「絶対的優先の原則(Absolute Priority Rule, APR)」の取扱いに見られます。
前章でお伝えした通り、伝統的なChapter11のクラムダウンにおいて、APRは、無担保債権者のクラスが全額の弁済を受けない限り、それより劣後する株主(事業主)は、再生後の会社の所有権を一切保持できないと定めます。これは、個人事業主や同族経営の中小企業にとって、たとえ会社の再生に成功したとしても自らの事業を失うことを意味する過酷なルールでした。
Subchapter Vは、このAPRを適用しません。その代わりに、1191条(b)項は、新たな基準を設けています。たとえ無担保債権者のクラスが計画に反対し、かつ、全額の弁済を受けられない場合でも、計画が以下の条件を満たせば、裁判所は再生計画を認可(クラムダウン)することができるのです。
- 再生計画が、債務者の「将来の可処分所得(projected disposable income)」の全てを、3〜5年間にわたって計画に基づく支払いに充てることを定めていること。
「可処分所得」とは、債務者が事業の継続・維持・運営に合理的に必要な支出を支払った後に残る、全ての現金・現金同等物を意味します。つまり、事業主は、事業に必要な経費を支払い、自らの生活に必要な合理的な給与を受け取った上で、残った利益の全てを、3〜5年間、債権者への返済に充てます。これを約束することで、無担保債権者に100%返済できなくとも、事業の所有権(株式)を維持し続けることが許されるのです。
Chapter 13:個人債務者の再建
Chapter 13は、アメリカの一般市民にとって最も身近な再生型倒産手続です。これは、巨額の事業負債を抱える企業ではなく、住宅ローン・自動車ローン・クレジットカード・医療費といった負債に苦しむ「定期的な収入のある個人」を対象としています。将来の収入を原資として、規律ある返済計画を通じて生活を立て直していくことを目的としています。
適用要件と返済計画
Chapter13を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
- 定期的な収入: 債務者は、給与・年金・事業収入など、返済計画を遂行するのに十分な安定的かつ定期的な収入がなければなりません。
- 債務額の上限: 債務者の負債総額は、法で定める上限額(担保付債務と無担保債務のそれぞれに上限が設けられており定期的に調整されます)を超えてはなりません。この上限を超える個人は、Chapter11の利用を検討する必要があります。
Chapter13の手続の核心は、債務者が提出する「返済計画(Repayment Plan)」にあります。この計画は、今後3年間または5年間(債務者の収入が州の中央値を上回る場合は原則5年間)にわたり、将来の収入の一部を、Chapter13の管財人を通じて各債権者にどのように分配していくかを定めるものです。
Chapter 7との比較とChapter 13の利点
多くの個人債務者は、Chapter7とChapter13のどちらを利用すべきかという選択に直面します。Chapter13には、Chapter7にはない、いくつかの強力なメリットが存在します。
- 住宅ローンの延滞解消と自宅の保持: Chapter13が持つ最大の利点の一つが、住宅ローンが延滞している場合に、自宅を差し押さえから守ることができる点です。債務者は、返済計画の中で、通常の月々の住宅ローン支払いを継続しつつ、それとは別に、申立て時点で溜まっていた延滞額(arrears)を、計画期間(3~5年)にわたって分割で返済していくことができます。これにより、債務者は最終的に延滞を完全に解消し、大切な自宅を維持することが可能となります。これは、Chapter7では不可能なChapter13独自の強力な機能です。
- 担保付債権の「クラムダウン」: 自宅についている第一順位抵当権以外の担保付債権の多くについては、「クラムダウン」することが可能です。最も典型的な例が自動車ローンです。例えば、自動車ローンの残債が200万円あるが、その自動車の現在の市場価値(担保価値)が120万円しかない場合、債務者は計画の中で、120万円(とその利息)だけを担保付債権として支払います。残りの80万円の不足額は無担保債権として扱われ、他の無担保債権と同様に、ごく一部の配当しか受けられないことが多いです。これにより、債務者は担保物の価値以上の支払いを強制されずに済みます。
- 非免責債権の取扱いと「スーパー・ディスチャージ」: Chapter 13では、Chapter 7では免責されない特定の債務(例えば、離婚に伴う財産分与に関する債務など)も、計画を完了することで免責される場合があります。かつてこの免責範囲は非常に広かったため「スーパー・ディスチャージ」と呼ばれましたが、2005年のBAPCPA改正でその範囲は狭められました。しかし、依然としてChapter7よりも広い免責が得られる場合があり、特定の種類の債務を抱える者にとっては大きなメリットとなります。
- 財産の保持: Chapter7では、免除財産を超える資産は管財人によって売却されてしまいます。一方、Chapter13では、債務者は全ての資産を保持することができます。ただし、その代償として、後述する「最善の利益テスト」に基づき、非免除財産の価値に相当する金額以上を、計画期間中に無担保債権者に支払う必要があります。
計画の認可要件
Chapter13の返済計画が裁判所に認可されるためには、Chapter11と同様、いくつかの重要な要件を満たさなければなりません。
- 最善の利益テスト(Best Interests Test): 計画の下で無担保債権者が受け取る分配総額は、債務者がChapter 7を申し立てて資産を清算した場合に受け取れたであろう分配額以上でなければなりません。これにより、債権者がChapter 13によって不利益を被らないことが保証されます。
- 可処分所得テスト(Disposable Income Test): 債務者は、計画期間中、自らの「可処分所得」の全てを計画の支払いに充てなければなりません。可処分所得とは、収入から、自身と扶養家族の生活維持に合理的に必要な費用を差し引いた残額です。
- 実行可能性(Feasibility): 債務者が、計画で定められた全ての支払いを、将来にわたって実行できる能力があることを示さなければなりません。
これらの要件を満たし、計画が認可され、そして債務者が3〜5年間にわたる支払いを誠実に完了したとき、裁判所は免責許可決定を下します。これにより、計画で支払われなかった残りの債務の多くが消滅し、債務者は経済的再生を果たすことができます。