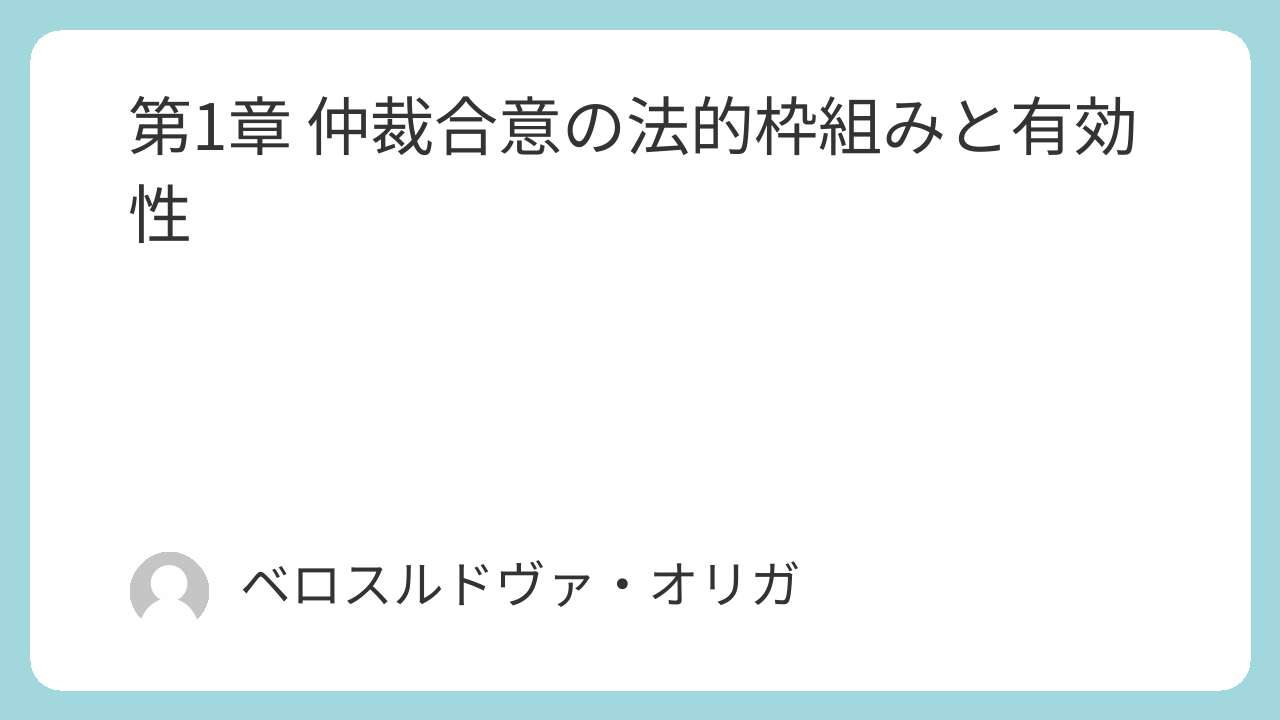国際仲裁の全プロセスは、当事者間の「仲裁合意」から始まります。この合意がなければ、仲裁廷が紛争を審理する権限も、その判断が国際的に執行される根拠も存在しません。
しかし、ひとたび紛争が現実に発生すると、当事者の一方は、かつて自らが交わした仲裁合意の有効性や範囲に疑問を呈し、仲裁ではなく自国に有利な裁判所での解決を試みることが少なくありません。そのため、仲裁合意がどのような法的枠組みによって支えられ、いかなる場合に有効と判断されるのかを正確に理解することは、国際ビジネスに携わる者にとって不可欠の知識です。
本章では、この仲裁合意をめぐる基本的な法的枠組みと有効性の原則について、国際的なスタンダードとなっているルールを中心に解説します。
1. 仲裁合意の重要性と種類
(1) 仲裁手続の基礎としての仲裁合意
序章で述べた通り、仲裁は当事者の合意に基づく紛争解決手続です。当事者が、特定の紛争を裁判所ではなく仲裁という私的な手続に付託することに合意して初めて、仲裁の道が開けます。この合意は、当事者が裁判を受ける権利という基本的な権利を放棄し、その代わりに仲裁という手段を選択するという重要な法的効果を持ちます。
この合意は、ポジティブな効果とネガティブな効果を併せ持ちます。ポジティブな効果とは、当事者に対して、仲裁手続に誠実に参加し、紛争解決に協力する義務を課すことです。一方、ネガティブな効果とは、仲裁合意の対象となる紛争について、各国の裁判所に訴訟を提起することを妨げる効力です。国際取引において仲裁が好まれる大きな理由の一つは、このネガティブな効果によって、いずれかの当事者が自国に有利な裁判所で不意打ち的に訴訟を起こす「フォーラム・ショッピング」のリスクを排除できる点にあります。
(2) 仲裁合意の種類
仲裁合意は、締結されるタイミングによって、主に二つの種類に分類されます。
a. 仲裁条項(Arbitration Clause)
仲裁条項は、将来発生する可能性のある紛争を仲裁に付託することを定めるもので、通常は売買契約、合弁契約、ライセンス契約といった主たる商事契約の一条項として盛り込まれます。国際商事仲裁の大半は、この仲裁条項に基づいて行われます。
紛争がまだ現実化していない契約交渉の段階では、当事者双方が冷静かつ協力的な関係にあるため、中立的で公平な紛争解決手続として仲裁条項に合意することは比較的容易です。しかし、一度紛争が勃発すると、当事者間の対立が深まり、新たな合意を形成することは極めて困難になります。そのため、国際的な契約を締結する際には、将来のリスク管理の一環として、適切に設計された仲裁条項を盛り込んでおくことが極めて重要です。
b. 付託合意(Submission Agreement)
付託合意は、既に発生した特定の紛争を仲裁によって解決するために締結される合意です。主契約に仲裁条項がなかった場合や、仲裁条項の有効性に疑義がある場合に、紛争発生後に改めて締結されます。
付託合意では、対象となる紛争が具体的に特定されているため、仲裁の範囲が明確であるという利点があります。しかし、紛争発生後に対立する当事者間で新たな合意を形成することは、交渉が難航しがちで、実務上、付託合意が締結されるケースは仲裁条項に比べてはるかに少ないのが実情です。
2. 仲裁合意の有効性の原則
歴史的に、特に英米法の裁判所は、自らの司法権を奪うものとして仲裁合意に対して敵対的な態度をとっていました。「仲裁合意はいつでも取消可能である」という判例法理が存在し、当事者の一方が合意を破って訴訟を提起しても、裁判所はそれを受理し、仲裁を強制することはありませんでした。
しかし、20世紀に入り、国際取引が拡大するにつれて、中立的で実効的な紛争解決手段の必要性が高まり、この状況は劇的に変化しました。1923年のジュネーブ議定書を経て、1958年に採択されたニューヨーク条約は、この流れを決定的なものにしました。同条約の第2条は、締約国に対して書面による仲裁合意を「承認し」、当事者を仲裁に付託することを義務付け、仲裁合意に国際的な執行力を与えました。
この「仲裁に好意的(Pro-arbitration)」な姿勢は、その後に制定されたUNCITRALモデル法や各国の国内仲裁法にも受け継がれ、今日では「仲裁合意は原則として有効かつ執行可能である」という原則が、国際的なスタンダードとして確立されています。
この原則の下では、仲裁合意の有効性を争う側が、その無効原因を主張・立証する責任を負います。そして、その無効原因は、ニューヨーク条約や各国の仲裁法で定められた極めて限定的なものに限られます。ニューヨーク条約第2条3項は、仲裁合意が「無効、作動不能又は履行不可能(null and void, inoperative or incapable of being performed)」であると裁判所が認定した場合にのみ、仲裁への付託を拒否できるとしています。これは、詐欺、強迫、公序違反といった、あらゆる契約に共通して適用される無効原因に限定して解釈されるのが一般的であり、単に仲裁が不便であるとか、訴訟の方が望ましいといった理由で仲裁合意を無効にすることはできません。
3. 仲裁合意の形式的有効要件
仲裁合意の有効性が国際的に承認されるための最も基本的な要件が、その形式です。ニューヨーク条約第2条は、その適用対象を「書面による合意(agreement in writing)」に限定しています。これは、口頭での仲裁合意を条約の保護対象から除外する重要な規定です。
(1) ニューヨーク条約における「書面要件」
ニューヨーク条約2条2項は、「書面による合意」をさらに具体的に、「契約中の仲裁条項又は当事者により署名され若しくは交換された書簡若しくは電報に含まれる仲裁合意」と定義しています。この定義は、以下の二つの類型を想定しています。
- 当事者によって署名された契約書中の仲裁条項: これは最も典型的なケースです。契約書全体に当事者の署名があれば、その中の一条項である仲裁条項も「署名された」ものとして扱われます。
- 交換された書簡または電報に含まれる仲裁合意: 契約書が一つにまとめられていなくても、当事者間で交換された複数の文書(手紙、テレックス、電報など)のやり取りの中で仲裁への合意が記録されていれば、書面要件を満たします。
この条文の文言は、1958年当時の商慣習を反映したものであり、現代の電子的な通信手段(Eメール、メッセージアプリなど)を直接想定していません。そのため、Eメールの交換だけでこの「交換された書簡」の要件を満たすかについては、各国の裁判所の判断が分かれる時期がありました。しかし、現在では、UNCITRALが2006年に採択した勧告の後押しもあり、Eメールのように内容が記録として残り、当事者間のやり取りが確認できる電子的な通信も、この要件を満たすという解釈が国際的な主流となっています。
(2) UNCITRALモデル法における要件の近代化
UNCITRALモデル法は、この書面要件を現代の商取引の実態に合わせてより柔軟に規定しています。特に2006年の改正では、書面要件の解釈について2つの選択肢を提示しました。
- 選択肢 I:仲裁合意の内容が何らかの形式で記録されていれば、書面要件を満たすとするものです。たとえ合意自体が口頭や行為によってなされたとしても、その内容が議事録や確認メール、一方の当事者が作成したメモなどに記録として残っていれば有効とされます。署名や文書の交換は必須ではありません。
- 選択肢 II:書面要件そのものを撤廃するものです。この立場では、仲裁合意の成立は、他の契約と同様に、各国の契約法の一般原則(意思表示の一致など)によって判断され、形式は問われません。
多くの国が選択肢Iまたはそれに類する柔軟な規定を国内法に取り入れており、国際仲裁における形式要件は緩和される傾向にあります。
(3) 参照による援用(Incorporation by Reference)
実務上、契約書本体には詳細な仲裁条項を記載せず、「本契約から生じるすべての紛争は、〇〇業界団体の標準取引条件書に定めるところにより解決される」といった形で、別の文書に含まれる仲裁条項を引用(参照)することがあります。
このような参照が有効と認められるためには、多くの国の法制度で、①参照先の文書に仲裁条項が含まれていること、そして②主契約の文言が、その仲裁条項を契約の一部とする意図を明確に示していること、が必要とされます。特に、契約の当事者ではない第三者が作成した標準取引条件などを参照する場合には、当事者が仲裁条項の存在を認識し、それに合意したと評価できるかどうかが慎重に判断されます。
4. 仲裁合意の分離可能性(Separability)
仲裁合意の有効性を支える最も重要かつ洗練された法理の一つが、「分離可能性の原則」です。これは、契約書に含まれる仲裁条項が、その契約の他の実体的な条項(売買の目的物、代金、履行期など)から法的に「分離可能」で、「独立」した合意であるとみなす原則です。
この原則は、UNCITRALモデル法第16条1項に明確に規定されており、今日では世界のほぼすべての法域で承認されています。
UNCITRALモデル法 第16条1項(抜粋)
契約の一部を構成する仲裁条項は、当該契約の他の条項から独立した合意として取り扱われるものとする。仲裁廷が当該契約は無効であると決定した場合であっても、そのこと自体から当然に仲裁条項が無効となるものではない。
(1) 分離可能性の原則の意義
もし分離可能性の原則がなければ、どうなるでしょうか。例えば、買主が「売主による詐欺があったため、売買契約全体が無効だ」と主張したとします。この主張が認められれば、売買契約の一部である仲裁条項も一体として無効となり、仲裁廷はそもそもこの紛争を審理する管轄権を失ってしまいます。その結果、詐欺があったかどうかの判断は、仲裁廷ではなく、いずれかの国の裁判所で行われることになり、当事者が当初意図した「紛争は仲裁で解決する」という合意が骨抜きになってしまいます。
分離可能性の原則は、このような事態を防ぎます。この原則によれば、たとえ主契約が無効であると主張されても、それとは独立した「仲裁条項」自体の有効性は当然には失われません。そして、主契約が無効であるか否かという問題そのものを判断する権限は、有効に存続する仲裁条項に基づき、まさにその仲裁廷に与えられるのです。つまり、この原則は、仲裁合意に「自らの有効性を揺るがしかねない紛争でさえも、自らが指定する手続(仲裁)で解決する」という自己完結的な力を与えるものです。
(2) 分離可能性の原則の帰結
この原則から、以下の重要な帰結が導かれます。
- 主契約の無効、終了、履行不能といった主張は、それ自体では仲裁条項の有効性に影響を与えません。
- 逆に、仲裁条項自体が無効であっても、主契約の他の部分の有効性には影響を与えません。
- 主契約に適用される法(準拠法)と、仲裁条項に適用される法が、別個に決定される可能性があります。
この原則は、仲裁廷が自らの管轄権の有無を判断する権能、すなわち次に述べる「コンペテンス・コンペテンス」の理論的基礎となっています。
5. コンペテンス・コンペテンス(Competence-Competence)
コンペテンス・コンペテンスとは、仲裁廷が、自らの管轄権(ドイツ語で Kompetenz)に関する異議について、自ら判断する権能(competence)を持つという原則です。これもUNCITRALモデル法第16条1項に規定され、国際的に広く承認されています。
この原則により、一方当事者が「仲裁合意は無効だ」「この紛争は仲裁合意の範囲外だ」といった管轄権に関する異議を申し立てた場合でも、まずは仲裁廷自身がその異議について審理し、判断を下すことができます。裁判所が仲裁手続に先立って、あるいは手続中に頻繁に介入し、管轄権の有無を判断するとなると、仲裁手続は遅延し、妨害される恐れがあります。コンペテンス・コンペテンスは、このような裁判所の過度な介入を排し、仲裁手続の自律性と効率性を確保するための重要な原則です。
(1) 仲裁廷と裁判所の管轄権判断の分配
もっとも、仲裁廷による管轄権の判断が最終的なものとなるわけではありません。仲裁廷の判断は、仲裁手続の後の段階で、通常は仲裁地の裁判所による司法審査の対象となります。
問題は、「誰が、いつ、管轄権に関する判断を最初に行うか」という点であり、この点に関する各国の法制度のアプローチは一様ではありません。
- フランス型(Prima Facie アプローチ): フランスの裁判所は、仲裁合意が「明らかに無効」でない限り、管轄権に関する判断をまず仲裁廷に委ね、自らは手続に介入しません。仲裁廷の判断が出た後に、取消訴訟の中で初めて本格的な司法審査を行います。これは、仲裁廷のコンペテンス・コンペテンスを最大限尊重するアプローチです。
- アメリカ型(完全な司法審査アプローチ): アメリカの裁判所は、仲裁を命じるかどうかの申立てがあった段階で、仲裁合意の有効性や範囲について完全な審理を行い、終局的な判断を下すのが一般的です。裁判所が管轄権を認めなければ、そもそも仲裁手続は開始されません。
- モデル法のアプローチ: UNCITRALモデル法第8条は、裁判所に対し、仲裁合意が「無効、作動不能又は履行不可能」であると「認定(finds)」しない限り、当事者を仲裁に付託するよう求めており、アメリカ型に近いアプローチと解釈されることが多いですが、各国の運用には幅があります。
この管轄権判断の分配に関する各国のスタンスの違いは、国際仲裁においてどの国を仲裁地として選ぶかを決定する上で、極めて重要な考慮要素となります。
本章で見てきたように、仲裁合意は、国際的な条約と各国の法制度、洗練された法理によって、その有効性と執行可能性が強力に支えられています。これらの法的枠組みが、国際商事仲裁を信頼に足る紛争解決インフラとして機能させているのです。次の章では、この仲裁合にどの国の法律が適用されるのか(準拠法)、そしてどのような紛争が仲裁になじむのか(仲裁可能性)という、さらに深掘りしたテーマを扱います。