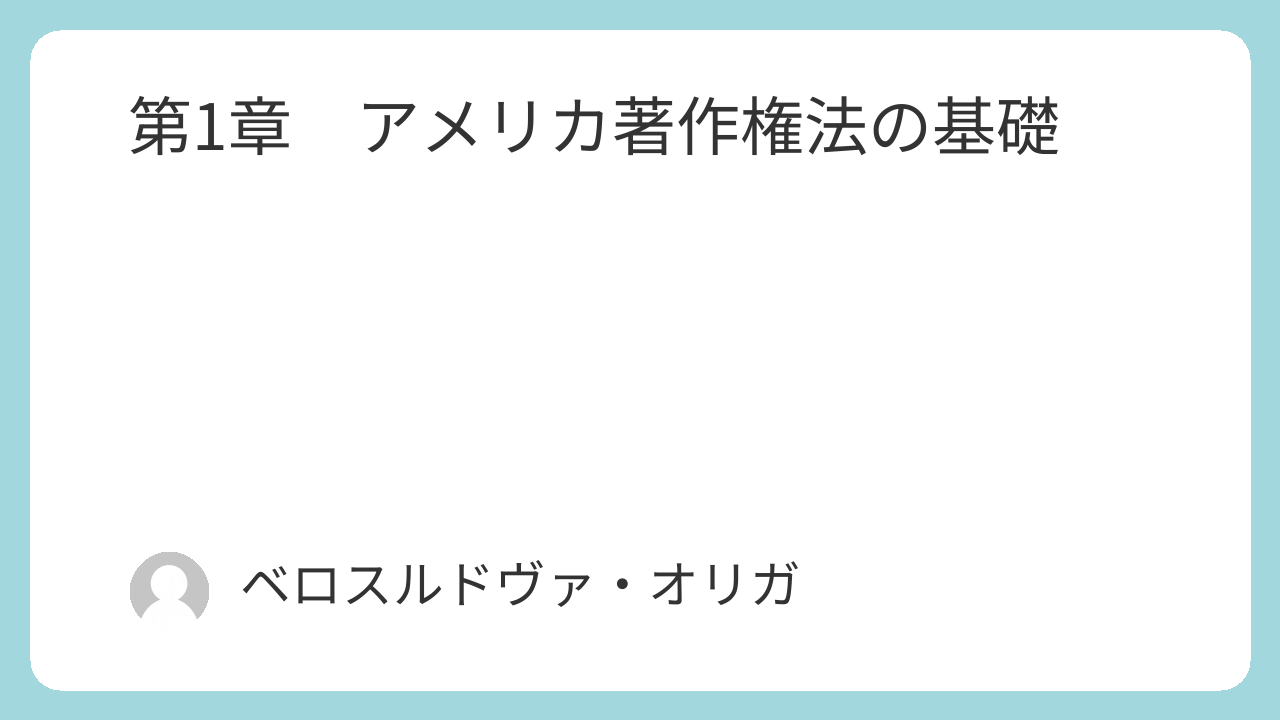1. 著作権法の目的
「知識、解明された真実、概念、そしてアイデアといった、人類の最も高貴な創造物は、一度他者に任意に伝えられた後は、空気のように誰もが自由に利用できるというのが法の一般原則である。」
ルイス・ブランダイス連邦最高裁判事(International News Service v. Associated Press事件反対意見)
なぜ社会は、形のない「知」、すなわち情報やアイデアに権利を認めるのでしょうか。この問いに対する答えは、著作権法の根幹をなす2つの対照的な思想に集約されます。
1つは、ヨーロッパ大陸法の伝統に深く根ざす自然権的アプローチです。18世紀の哲学者ジョン・ロックが提唱したように、人は自らの労働の成果を享受する自然な権利を持つという考え方です。この思想によれば、著作者が知的・精神的労働を通じて生み出した作品はその人格の延長であり、その成果をコントロールし、対価を得ることは著作者の固有の権利であるとされます。この「著作者の権利(author’s rights)」という考え方は、作品の改変を防ぐ「同一性保持権」や著作者名を表示する「氏名表示権」といった著作者人格権(moral rights)の保護を重視し、フランスやドイツの著作権法の根幹をなしています。
これに対し、アメリカやイギリスのコモンローの伝統において支配的なのが、功利主義的アプローチです。この考え方の核心は、個々の著作者の利益そのものではなく社会全体の利益、即ち、公共の福祉の増進にあります。この思想は、アメリカ合衆国憲法1条8節8項、通称「著作権・特許条項」に明確に体現されています。
To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.
(著作者および発明者に、期間限定で、その著作および発明に対し排他的な権利を保障することにより、科学および有用な技術の進歩を促進するため)
ここには著作者の自然権への言及はなく、目的はあくまで「科学および有用な技術の進歩の促進」とされています。著作権とは、その目的を達成するための手段にすぎません。情報やアイデアは、一度公にされると容易に模倣され、その生産に投じられたコストを回収することが困難になるという「公共財」としての性質を持ちます。もし誰もが自由にコピーできるのであれば、創造活動への投資インセンティブは失われ、結果として社会が享受できるはずの新たな作品は生まれにくくなるでしょう。
そこで、この「市場の失敗」を回避するため、著作者に一定期間の排他的な独占権を与えることで、創造活動への経済的インセンティブを確保するというのが、功利主義的な著作権制度の基本的な設計思想です。著作者への報酬は、あくまで社会全体の利益を最大化するための手段として位置づけられています。ただし、この独占権は無制限ではありません。憲法が「期間限定で(for limited Times)」と釘を刺しているように、保護期間が終了した著作物はパブリックドメイン(公有)となり、誰もが自由に利用できる社会の共有財産となります。
このように、アメリカの著作権法は、創造へのインセンティブ(保護)と、知識の自由な流通(アクセス)という2つの要請の間に、絶妙なバランスを保とうとする制度なのです。この功利主義的な思想は、後の章で詳述する「アイデアと表現の二分論」や「フェアユース」といった、アメリカ著作権法を特徴づける重要な法理の根底にも流れています。
2. 米国著作権法の歴史的変遷
著作権法の発展は、常にテクノロジーの進化との闘いの歴史でした。15世紀にグーテンベルクの活版印刷技術がイギリスに伝わると、書籍の大量複製が可能となり、王室と出版業者の双方に大きな衝撃を与えました。王室は、異端思想や反体制的な言説の拡散を恐れ、出版許可制を導入します。1557年には、ロンドンの出版業者ギルドである書籍出版業組合(Stationer’s Company)に独占的な出版権を与え、その見返りに検閲と統制の役割を担わせました。
この組合による独占は1世紀以上続きましたが、1695年に失効すると、市場は混乱に陥ります。これを受けて1710年に制定されたのが、世界初の近代的な著作権法であるアン女王条例(Statute of Anne)です。この法律は、組合の既得権益を保護する側面もありましたが、歴史的に重要な転換をもたらしました。すなわち、保護の主体を出版業者から「著作者(Authors)」へと移し、その目的を「学識ある人々が有用な著作物を創作・執筆することの奨励」にあると宣言したのです。また、保護期間を、新規著作物については14年(著作者が生存していればさらに14年の更新が可能)と定め 、期間満了後はパブリックドメインに帰属させることで、独占と公共の利益のバランスを図りました。このアン女王条例の基本構造は、そのままアメリカ初の連邦著作権法である1790年法のモデルとなりました。
その後、アメリカの著作権法は数度の改正を経て、20世紀の産業社会に対応すべく1909年に包括的な改正が行われます。1909年著作権法は、保護対象を「著作者のすべての著作物(all the writings of an author)」へと拡大し、保護期間を28年の初回期間と28年の更新期間からなる最大56年としました。しかし、この法律は大きな問題を抱えていました。それは、連邦法の保護が「刊行(publication)」によって開始されるという点です。未刊行の著作物は各州のコモンロー(判例法)で保護され、刊行された著作物は連邦法で保護されるという二元的なシステムは、権利保護の境界線を曖昧にし多くの混乱を生みました。また、刊行されたすべての著作物に著作権表示(copyright notice)を義務付け、これを怠ると権利が消滅するという厳格な「方式主義」は、多くの著作者を意図せずして権利喪失の罠に陥れました。
これらの問題点を解消し、20世紀後半の新たなテクノロジーに対応するため、20年以上にわたる全面的な見直しの末に制定されたのが、現行法である1976年著作権法です。この法律は、アメリカ著作権法に革命的な変化をもたらしました。
- 単一の連邦システム: 州のコモンローによる著作権を原則として連邦法が先占(preempt)し 、著作物が「有形的媒体に固定(fixed in any tangible medium of expression)」された時点で、刊行・未刊行を問わず連邦著作権法による保護が開始されることになりました。
- 保護期間の伸長: 保護期間は、原則として「著作者の死後50年(後に70年に延長)」という単一の期間に統一されました。
- 方式主義の緩和: 著作権表示の義務は緩和され、表示がなくとも直ちに権利が消滅することはなくなりました。(1988年のベルヌ条約加盟に伴う改正で、表示義務は完全に撤廃されました。)
1976年法の制定後も、コンピュータプログラム、デジタル録音技術、インターネットの登場といったテクノロジーの進歩に対応するため、法律は改正を重ねています。特に、1998年のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)は、オンラインサービスプロバイダの責任を制限するセーフハーバー規定や、技術的保護手段の回避を禁止する規定を設け、デジタル時代の著作権法の骨格となっています。
3. 知的財産権の中での著作権法の位置づけ
著作権法は、「知的財産法」という大きな枠組みの一つです。ビジネス実務においては、著作権・特許・商標・営業秘密といった異なる権利が、1つの製品やサービスに複雑に絡み合っていることが少なくありません。それぞれの法制度の目的と保護対象を正確に理解することは、効果的な知財戦略を立てる上で不可欠です。
特許法(Patent Law)
特許法は、新規かつ有用で自明でない「発明(inventions)」、即ち、技術的思想を保護します。保護対象は、製品の構造や化学物質といった「物」の発明と、製造方法などの「方法」の発明です。著作権がアイデアそのものは保護せず、その「表現(expression)」を保護するのに対し、特許はアイデア(技術的思想)そのものに独占権を与えます。その代わり、権利取得には米国特許商標庁(USPTO)による厳格な審査を経て登録される必要があり、保護期間も出願から20年と比較的短期間です。しかし、一度権利が成立すれば、独自に同じものを発明した者(独立発明者)に対しても権利行使が可能な、非常に強力な独占権となります。
商標法(Trademark Law)
商標法は、商品やサービスの出所を識別するための「標識(marks)」、すなわちブランド名やロゴなどを保護します。その目的は、創作のインセンティブ確保ではなく、事業者間の公正な競争の維持と、消費者が商品やサービスの出所を混同しないようにすることにあります。権利は、特許や著作権のように創作によって生じるのではなく、その標識を商業的に「使用(use)」することによって発生します。使用を続ける限り、権利は半永久的に存続し得ます。侵害の判断基準は、著作権の「実質的類似性」とは異なり、「消費者の混同のおそれ(likelihood of confusion)」があるか否かです。
営業秘密法(Trade Secret Law)
営業秘密法は、企業の競争上の優位性の源泉となる、公に知られていない有用な情報(顧客リスト、製造ノウハウ、コカ・コーラのレシピなど)を保護します 。特許のように新規性や非自明性といった要件は不要ですが 、その情報が「秘密」として管理されていることが保護の絶対条件です。保護の範囲は、不正な手段(窃盗、詐欺、契約違反など)による情報の取得や使用(misappropriation)に限られ、リバースエンジニアリングや独自開発によって同じ情報を得た者には権利が及びません。秘密である限り、保護期間に定めはありません 。
これらと比較すると、著作権法は「独創的な表現(original expression)」を保護対象とし、「固定(fixation)」された時点で権利が自動的に発生し、「著作者の死後70年」という長期間にわたり、「依拠(copying)」に基づく侵害行為を規制する、という独自の位置づけにあることがわかります。